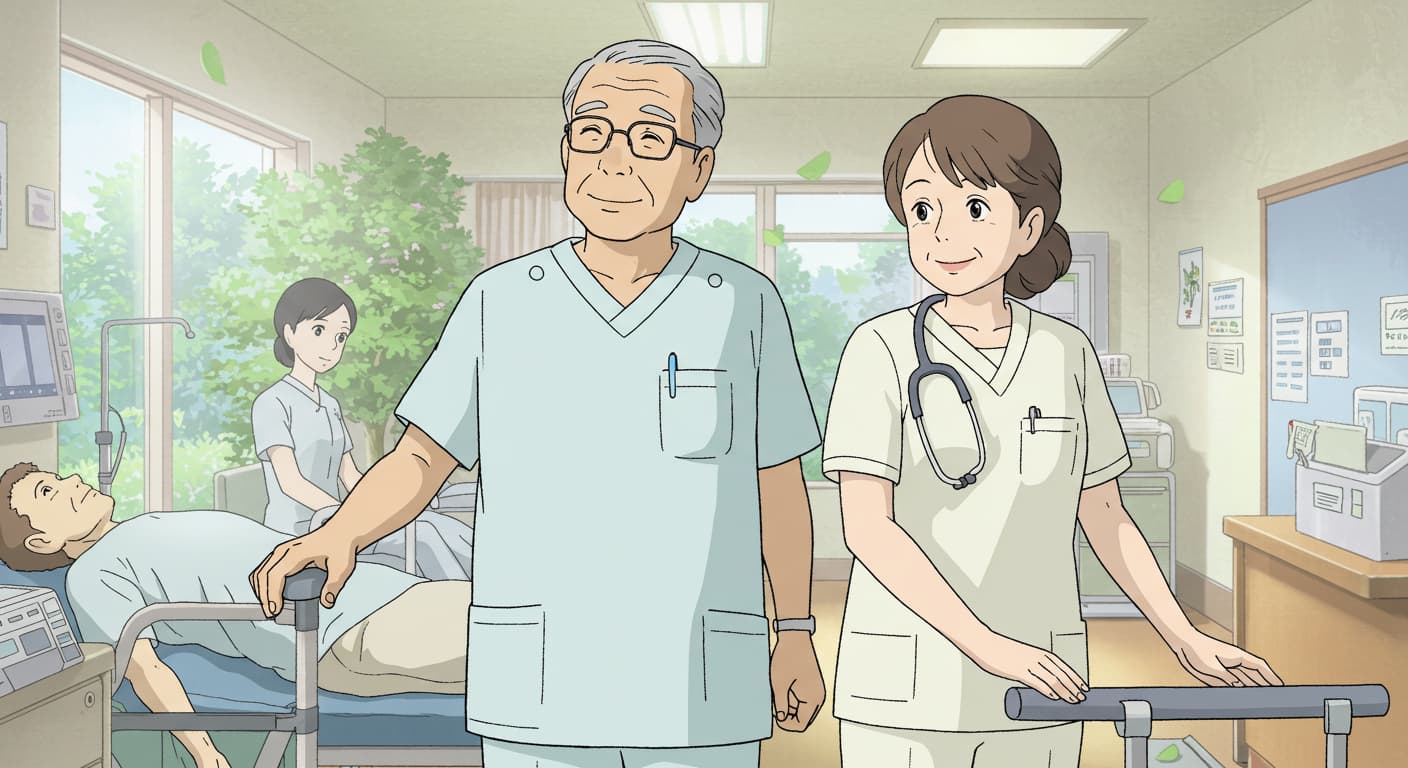「理学療法士として一生働いたら、年金はいくらもらえるんだろう?」
ふとした瞬間に、そんな不安が頭をよぎったことはありませんか。
毎日忙しく働き、患者さんと向き合ってきたのに、老後のお金だけは、なぜか誰もはっきり教えてくれない——。
そのモヤモヤが、「理学療法士の年金」という疑問につながっているはずです。
実は、理学療法士の年金は働き方・転職・知識の有無によって、将来の安心度が大きく変わります。
ポイント
この記事では、制度の難しい話だけでなく、「知らないままだと後悔しやすいポイント」と、今から何を考え、どう動けばいいのかを、現実ベースで整理します。

読み終えたとき、「不安の正体」と「次に取るべき行動」が、きっとクリアになっているはずです。
Contents
理学療法士の年金の仕組みをわかりやすく解説
「理学療法士って、将来いくら年金がもらえるんだろう?」
「転職したら年金は不利になる?」
そんな不安から「理学療法士の年金」と検索して、この記事にたどり着いた方も多いはずです。
特に理学療法士は、病院・介護施設・訪問・公務員・フリーランスなど、
働き方によって年金制度が大きく変わる職種です。
ここでは、年金の基本構造から、理学療法士ならではの注意点、

そして転職を考える人が必ず知っておくべき視点まで、噛み砕いて解説します。
「年金と合わせて、理学療法士の退職金額も必ず確認しておきましょう」
国民年金と厚生年金の違い
まず、日本の年金制度は大きく分けて2階建て構造になっています。
- 国民年金(1階部分)
- 厚生年金(2階部分)
国民年金は、
20歳以上60歳未満のすべての人が加入する基礎年金です。
一方、厚生年金は、
会社員や公務員など、雇用されて働く人が上乗せで加入する年金です。
簡単に言うと、
国民年金だけ → 最低限の年金
国民年金+厚生年金 → 比較的手厚い年金
という違いがあります。
そのため、
- どの制度に加入していた期間が長いか
- どれくらいの収入で働いていたか
によって、老後にもらえる年金額には大きな差が生まれます。
理学療法士が加入する年金制度は?
理学療法士の多くは、民間病院・介護施設などで雇用される会社員として働いています。
この場合、
国民年金+厚生年金
に加入することになります。
つまり、一般的な会社員と同じ年金制度です。
一方で、
- フリーランス
- 個人事業主
- 非常勤・パートのみ
といった働き方をしている理学療法士は、国民年金のみの加入になるケースが多くなります。
ここで重要なのは、
「理学療法士だから年金が少ない」のではなく、
「どの働き方を選んだか」で年金が変わる
という点です。
転職を考える際には、
- 年収
- 働きやすさ
- スキルアップ
だけでなく、将来の年金という長期視点も含めて考える必要があります。
公務員と民間で加入する制度の違い
理学療法士の中には、市立病院や県立病院などで働く公務員PTもいます。
以前は、公務員は共済年金という別制度に加入していましたが、
現在は制度が統合され、
国民年金+厚生年金
という点では、民間病院の理学療法士と同じ仕組みになっています。
ただし実務上は、
- 給与水準が比較的安定している
- 勤続年数が長くなりやすい
といった理由から、結果的に厚生年金の受給額が多くなる傾向があります。
逆に、
- 転職回数が多い
- 非常勤期間が長い
- 一時的に国民年金のみの期間がある
場合は、将来の年金額が想定より少なくなる可能性があります。
だからこそ、
「今の働き方が、将来どんな年金につながるのか」
を一度、冷静に整理してみることが重要です。
理学療法士は、
比較的長く働ける専門職である一方、老後資金は“制度任せ”にしづらい職種でもあります。
年金の仕組みを理解することは、不安を減らすだけでなく、

転職やキャリア選択の軸をはっきりさせる武器になります。
理学療法士はいくら年金をもらえるのか?
「理学療法士として働き続けた場合、老後はいくら年金がもらえるのか?」
これは、転職や働き方を考え始めた理学療法士が必ず一度はぶつかる不安です。
結論から言うと、理学療法士だから年金が特別に多い・少ないということはありません。

年金額を左右するのは、勤務形態・収入・勤続年数です。
ここでは、民間勤務・公務員勤務それぞれの目安と、
生活イメージがしやすいモデルケース別に、現実的な年金水準を解説します。
「老後の安心は、現役時代の生活レベルと貯蓄に大きく左右されます」
民間勤務の場合の年金の目安
民間病院や介護施設で働く理学療法士の多くは、国民年金+厚生年金に加入しています。
仮に、
- 平均年収:400万〜450万円
- 20代〜60歳まで正社員として勤務
という一般的なケースを想定すると、65歳以降にもらえる年金額の目安は、
月額:約13万〜16万円前後
(年額:約160万〜190万円程度)となることが多いです。
ここで注意したいのは、
- 転職回数が多い
- 非常勤・パート期間が長い
- 産休・育休後に収入が下がった
といった場合、
厚生年金部分が減り、月10万円台前半になることも珍しくありません。

「老後は年金だけで生活できる」と考えるには、やや心許ない金額だと感じる人が多いでしょう。
公務員勤務の場合の年金の目安
市立病院・県立病院などで働く公務員理学療法士も、現在は民間と同じく国民年金+厚生年金です。
ただし実際の年金額は、
- 給与が安定している
- 勤続年数が長くなりやすい
という理由から、民間よりやや高めになる傾向があります。
モデルとして、
- 平均年収:500万円前後
- 定年まで勤務
した場合、
月額:約16万〜18万円前後
(年額:約190万〜220万円程度)が、現実的なラインです。
「公務員=年金がかなり多い」というイメージを持っている人もいますが、
劇的に差がつくわけではない点は理解しておく必要があります。
モデルケース別の年金支給例(独身・夫婦・子あり)
年金額は同じでも、家族構成によって生活の余裕は大きく変わります。
独身・民間勤務の場合
- 年金:月14万円
- 住居:持ち家(ローン完済)
最低限の生活は可能ですが、医療費・趣味・旅行には工夫が必要です。
夫婦2人(共働きPT)の場合
- 夫:月15万円
- 妻:月13万円
- 合計:月28万円
このケースでは、比較的安定した老後生活が見込めます。
配偶者が専業・子どもありの場合
- 本人:月15万円
- 配偶者:国民年金のみ(月6万〜7万円)
合計は月22万円前後。
住宅費や支援が残っている場合は、年金だけでは不足する可能性があります。
ここで重要なのは、
「年金額そのもの」よりも、「どんな老後を送りたいか」から逆算すること
です。

理学療法士は、年金だけに頼ると不安が残りやすい職種です。
だからこそ、
- 働き方の選択
- 転職タイミング
- 早めの資産形成
を含めて、現役時代から老後を見据えたキャリア設計が欠かせません。
「理学療法士の年金」と検索した今このタイミングこそ、将来を具体的に考え始めるベストな時期です。
知らないと損!理学療法士が使える年金制度と加算
「理学療法士の年金は少ないって聞くけど、何か対策はできないの?」
「制度が複雑すぎて、正直よく分からない…」
そう感じて「理学療法士の年金」について不安を感じる人は非常に多いです。
実は年金制度は、知っているかどうかで将来受け取れる金額に差が出る仕組みになっています。
ここでは、競合記事ではさらっとしか触れられないことが多い、
理学療法士が必ず知っておくべき年金の「加算制度」「セーフティネット」「増やす方法」を、

転職を考えている人にも分かりやすく解説します。
「年金が少なくなる背景には、昇給しにくい給与構造があります」
加給年金・振替加算などのオプション
まず押さえておきたいのが、「加給年金」と「振替加算」です。
加給年金とは?
加給年金は、
厚生年金に20年以上加入している人が、65歳時点で扶養している配偶者や子どもがいる場合に、
年金に上乗せされる制度です。
配偶者が65歳未満の場合、年間約40万円前後が加算されるケースもあります。
理学療法士の場合、
- 配偶者が専業またはパート
- 自分が主たる生計維持者
という家庭では、対象になる可能性が高い制度です。
振替加算とは?
振替加算は、
配偶者が65歳になったタイミングで、加給年金が終了した代わりに配偶者の年金に上乗せされる制度です。
金額は生年月日などによって異なりますが、年間数万円〜十数万円程度になることが多いです。
どちらも、

「申請しないと受け取れない可能性がある」
点が最大の注意点です。
障害年金や遺族年金も把握しておこう
年金というと「老後のお金」というイメージが強いですが、実は現役世代を守る制度でもあります。
障害年金
病気やケガで、働くことや日常生活に支障が出た場合、年齢に関係なく受給できる可能性があるのが障害年金です。
理学療法士は、
- 腰痛・ヘルニア
- メンタル不調
- 慢性的な疾患
など、職業特性上リスクを抱えやすい職種でもあります。
「自分は対象にならないだろう」と思い込まず、
制度として存在することを知っておくだけでも、将来の安心感は大きく変わります。
遺族年金
万が一のことがあった場合、配偶者や子どもに支給されるのが遺族年金です。
厚生年金に加入していれば、
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金(条件あり)
が支給対象になります。
特に、
- 配偶者が専業・低収入
- 子どもがいる
理学療法士にとっては、家族を守る重要な制度です。
年金額を増やすための裏ワザ・任意加入や追納
「今からできることはないの?」そう思った方も多いはずです。

結論として、理学療法士でも年金額を増やす手段はあります。
国民年金の追納
学生時代などに、
- 免除
- 猶予
を受けていた期間がある場合、10年以内であれば追納可能です。
追納することで、
- 将来の年金額アップ
- 受給資格期間の確保
につながります。
任意加入制度
60歳以降も、受給資格期間が足りない場合などは、国民年金に任意加入することができます。
また、
- フリーランスPT
- 非常勤中心の働き方
を選ぶ場合も、意識的な加入・積立が将来を左右します。
厚生年金に長く加入するという戦略
裏ワザというより、最も堅実な方法がこれです。
つまり、
「正社員・厚生年金加入期間をいかに確保するか」
という視点。
転職を考える理学療法士にとって、
- 年収
- 働きやすさ
- やりがい
に加えて、
年金・社会保障まで含めて比較することは、長期的に見て非常に重要です。
年金制度は「難しいから後回し」にされがちですが、理解した人から得をする仕組みでもあります。

「理学療法士の年金」と調べた今こそ、将来のお金とキャリアをセットで考えるチャンスです。
実際の声から学ぶ!理学療法士の年金事情
「制度の説明は分かったけれど、結局、現場で働いてきた理学療法士は年金をどう感じているのかが知りたい」
——そう思っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、実際に年金を受け取り始めた・受給が見えてきた理学療法士のリアルな声をもとに、
年金の「現実」と「学び」を整理します。
これから転職や働き方を考える人にとって、

将来を具体的にイメージするためのヒントになるはずです。
先輩のリアルな支給額と感想
まずは、実際に年金を受給している・受給直前の理学療法士の声です。
ケース①:民間病院勤務・定年退職(男性・65歳)
- 勤務歴:民間病院 約38年
- 平均年収:400万円台
- 年金支給額:月約14万円
本人の感想:
「正直、もっともらえると思っていた。
生活はできるけど、年金だけだと余裕はない。退職金と貯蓄がなかったら不安だったと思う。」
ケース②:公務員理学療法士・定年退職(男性・65歳)
- 勤務歴:市立病院 約40年
- 平均年収:500万円前後
- 年金支給額:月約17万円
本人の感想:
「民間よりは少し多いけど、『公務員だから安心』というほどではない。
若い頃から年金を過信しすぎていたと思う。」

どちらのケースにも共通しているのは、「思ったより多くない」という実感です。
「老後まで考えると、割に合わないと感じてしまう理由も見えてきます」
「もっと備えておけばよかった」失敗談
次に多いのが、現役時代の判断を後悔している声です。
失敗談①:非常勤期間を甘く見ていた
「子育てや体力的な理由で、非常勤で働いていた期間が長かった。
その分、厚生年金がほとんど積み上がっていなかった。」
「当時は働きやすさを優先したけど、
今振り返ると、年金への影響を理解していなかったのが一番の後悔。」
失敗談②:制度を知らず、加算を受け取れなかった
「加給年金や振替加算を、自動でもらえるものだと勘違いしていた。
結果的に、数年分受け取り損ねた可能性があると聞いてショックだった。」

制度を知らないことが、そのまま損につながる典型例です。
「これをやってよかった!」成功事例
一方で、年金に対して比較的満足している理学療法士もいます。
成功例①:厚生年金を意識して働き方を選んだ
「一時期フリーランスも考えたけど、
将来を考えて厚生年金に入れる働き方を優先した。結果的に、老後の不安はかなり小さい。」
成功例②:早めに年金+資産形成をセットで考えた
「30代で『年金だけじゃ足りない』と気づいて、iDeCoや積立投資を始めた。
今は、年金はベース、貯蓄は上乗せという感覚で安心している。」
成功している人たちに共通するのは、
- 年金を過信しなかった
- 制度を理解しようとした
- 転職や働き方を長期視点で選んだ
という点です。
「理学療法士の年金」について疑問を持つ今このタイミングは、

将来の自分から見て“正解だった選択”をするための分岐点とも言えます。
先輩たちの声は、不安を煽るためではなく、後悔を避けるためのヒントとして活かしてください。
年金だけでは不安なあなたへ|今からできる対策
ここまで読んで、「理学療法士の年金、思っていたより少ないかもしれない」「年金だけで老後を乗り切るのは正直不安」
そう感じた方も多いのではないでしょうか。
実際、「理学療法士の年金」について疑問を持つ人の多くは、
将来への漠然とした不安を、具体的な行動に変えたい段階にいます。
大切なのは、今すぐ大きな決断をすることではなく、選択肢を知り、小さく動き始めることです。

ここでは、理学療法士が現実的に取り組みやすい3つの対策を解説します。
iDeCo・NISAで資産形成を始める
年金不安への対策として、最も王道で再現性が高いのがiDeCo・NISAです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、
老後資金づくりに特化した制度で、掛金が全額所得控除になるのが最大のメリットです。
理学療法士の場合、
- 民間病院勤務(会社員)
- 公務員PT
どちらも利用可能で、
節税しながら老後資金を積み立てられる点は非常に魅力的です。
一方で、
- 原則60歳まで引き出せない
という制約もあるため、「老後専用」と割り切って使うのがポイントです。
NISA(つみたて投資枠)
NISAは、
- 運用益が非課税
- 比較的自由に引き出せる
という特徴があります。
「いきなりiDeCoは不安」という人は、まずNISAから始めるのも十分アリです。

重要なのは、金額の大小ではなく、早く始めることです。
月5,000円でも、20年・30年続ければ、年金の“上乗せ”として大きな差になります。
退職金と年金のバランスを考える
理学療法士の老後資金を考えるうえで、年金とセットで考えるべきなのが退職金です。
特に、
- 公務員理学療法士
- 大規模法人に長く勤めているPT
の場合、退職金は老後資金の大きな柱になります。
一方で、
- 転職回数が多い
- 中小法人中心
- 退職金制度が弱い or ない
場合は、年金+自助努力が前提になります。
ここで重要なのは、
「自分は退職金がどれくらい見込めるのか」
を、一度具体的な数字で把握することです。
退職金が少ないと分かれば、
- 資産形成を厚くする
- 働き方を見直す
など、早めに戦略を立てることができます。
副業や資格取得で収入源を増やす方法
年金対策というと、
「節約」「投資」ばかりに目が向きがちですが、収入源を増やす視点も非常に重要です。
理学療法士は、
- 専門知識
- 現場経験
- 説明力
といった強みを活かしやすい職種です。
現実的な副業例
- 医療・介護系ライター
- 健康・運動指導
- オンライン相談・発信
- 社内外研修・教育分野
これらは、
- 体力消耗が少ない
- 長く続けやすい
という点で、将来の年金代わりの収入になり得ます。
また、
- 資格取得
- 専門分野の深掘り
によって、定年後も働ける選択肢を残すこともできます。
年金不安への対策は、「どれか一つを完璧にやる」必要はありません。
・年金(ベース)
・資産形成(上乗せ)
・収入源(保険)
この3つを少しずつ組み合わせることが、
理学療法士にとって最も現実的で、ストレスの少ない老後対策です。
「理学療法士の年金」について疑問を持つ今この瞬間が、将来への不安を、行動に変える最適なタイミングです。

できることから、無理のない一歩を踏み出していきましょう。
「年金に不安があるなら、現役時代に収入源を増やす選択もあります」
理学療法士の年金に関するよくある質問
「理学療法士の年金って少ないって聞くけど本当?」
「転職を繰り返すと将来かなり不利になる?」「60歳以降も働いたら年金はどうなるの?」
「理学療法士の年金」について疑問を持つ人の多くは、
制度そのものよりも、自分のキャリア選択が将来にどう影響するのかを知りたいと感じています。
ここでは、特に質問が多く、かつ他記事では曖昧にされがちなポイントを、

理学療法士の働き方に即して分かりやすく解説します。
「年金が少ない」と聞くけど本当?
結論から言うと、
理学療法士だから特別に年金が少ない、というわけではありません。
ただし、
「思っているより少ない」と感じる人が多い
のは事実です。
理由はシンプルで、
- 平均年収が極端に高い職種ではない
- 年金制度そのものが「最低限の生活」を想定している
からです。
例えば、民間病院勤務の理学療法士が、正社員として長く働いた場合でも、
月13万〜16万円前後
が現実的な年金水準になります。
これは決して「少なすぎる」わけではありませんが、
- 物価上昇
- 医療費
- 住居費
を考えると、年金だけで余裕のある老後とは言いにくいのが実情です。
そのため、
「年金が少ない」というより、「年金だけに頼るのは厳しい」
と理解する方が正確です。
転職や離職すると年金はどうなる?
理学療法士は転職が比較的多い職種のため、この質問は非常に多いです。
まず安心してほしいのは、
転職=年金がリセットされることはありません。

これまで納めた年金記録は、すべて通算されます。
ただし注意点があります。
① 厚生年金に加入していない期間が長いと不利
例えば、
- 非常勤・パート期間が長い
- フリーランスとして働く
- 離職中に国民年金を免除・未納にしている
こうした期間が増えると、将来の年金額は確実に下がります。
② 離職中の手続きを忘れると「未納」になる
転職の合間に、
- 国民年金への切り替え
- 保険料の免除・猶予申請
をしないと、未納期間になってしまうリスクがあります。
未納は、
- 将来の年金額が減る
- 障害年金・遺族年金の受給要件を満たせなくなる
という点で、特に注意が必要です。
転職を考えている理学療法士は、
「働いていない期間の年金手続き」
まで含めて、キャリアを考えることが重要です。
60歳以降も働く場合はどうなる?
近年、理学療法士は、
- 60歳以降も働く
- 定年後に再雇用・非常勤で続ける
ケースが増えています。

この場合の年金は、働き方によって扱いが変わります。
① 60〜65歳まで働く場合
厚生年金に加入して働けば、
- 年金保険料を納め続ける
- 将来の年金額が少しずつ増える
というメリットがあります。
また、
「在職老齢年金」
という仕組みにより、
給与と年金の合計額が一定以上になると、年金の一部が調整されることもあります。
② 65歳以降も働く場合
65歳を過ぎてからも、
- 厚生年金に加入
- 働き続ける
ことで、年金額はその後も増加します。
また、
- 年金の受給開始を繰り下げる
ことで、
1年遅らせるごとに年金額が増える
という選択肢もあります。

理学療法士は、体力や働き方を調整すれば、比較的長く現役を続けやすい専門職です。
その強みを活かして、
「年金+少し働く」
という設計をすることで、老後の不安を大きく減らすことも可能です。
「理学療法士の年金」について疑問を持ったあなたは、すでに一歩先の視点で将来を考え始めています。
制度を正しく理解することが、
不安を減らし、後悔しない転職・キャリア選択につながります。
「将来の年金を考えて、転職を検討する理学療法士も増えています」
まとめ
「理学療法士の年金」について疑問を持つ背景には、
老後のお金への不安と、転職や働き方の選択が将来にどう影響するのか知りたいという切実な悩みがあります。
ここまでの内容を、
理学療法士が後悔しない判断をするための重要ポイントに絞って整理します。
- 理学療法士だから年金が特別に少ないわけではない
年金額は職種ではなく、加入制度・年収・勤続年数で決まる。 - 現実的な年金額は月13〜18万円前後が目安
生活はできても、年金だけで余裕のある老後は難しいケースが多い。 - 転職しても年金はリセットされない
これまでの加入期間は通算されるが、厚生年金に入らない期間が長いと不利になる。 - 離職中の年金手続きを忘れると「未納」リスクがある
未納は将来の年金額減少だけでなく、障害年金・遺族年金にも影響する。 - 非常勤・フリーランス期間は年金が薄くなりやすい
働きやすさと将来の年金のバランスを意識することが重要。 - 60歳以降も働くことで年金を増やす選択肢がある
厚生年金に加入して働き続ける、受給開始を繰り下げるなどの戦略が使える。 - 年金は「最低限の土台」と考えるべき
iDeCo・NISA・退職金・副業などと組み合わせて老後資金を設計する必要がある。 - 年金を理解することは、転職判断の質を高める
年収や働きやすさだけでなく、長期的な安心を基準に職場を選べるようになる。
理学療法士は、
専門職として長く働ける一方で、年金を「なんとなく」で考えると後悔しやすい職種でもあります。
だからこそ、
「理学療法士の年金」と調べた今このタイミングで、
制度を知り、自分のキャリアとお金を結びつけて考えることが、将来の不安を大きく減らす一歩になります。
年金は変えられないものではなく、知識と選択で“結果が変わる仕組み”です。

ぜひ、これからの働き方を考える材料として活かしてください。