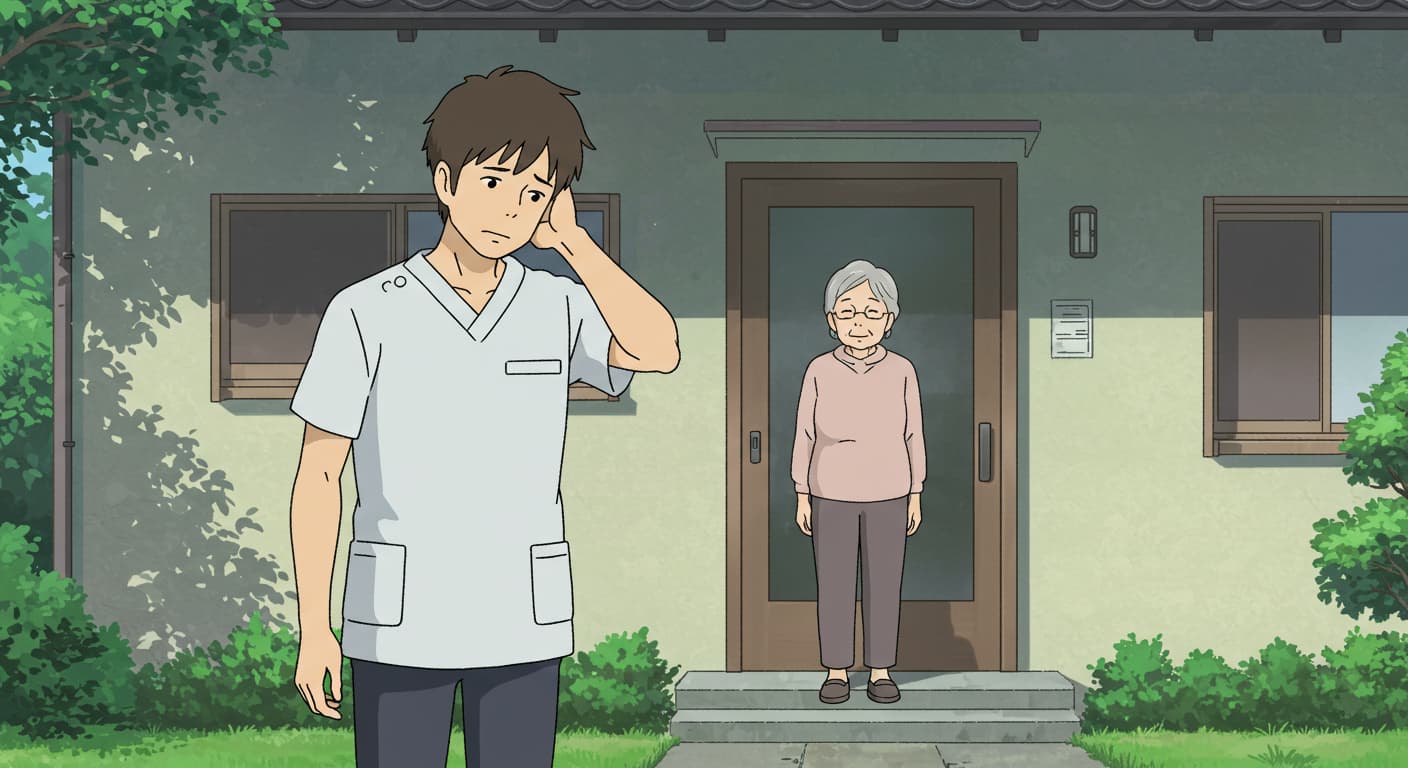「もう限界…。でも休めないから辞められない。」そんなふうに自分を責めながら、訪問リハの仕事を続けていませんか?
実は、あなたが苦しくなるのは“あなたの弱さ”ではありません。
業界の構造そのものが、あなたを休ませない仕組みになっているからです。
管理者の本音、経営側の裏事情、現場が声を上げられない理由… これらの“表には出ない真実”を知った瞬間、 多くのPT・OT・STが「だから私は休めなかったんだ…」と深く納得します。
もし今、「辞めたい」「しんどい」「この先が不安」 と感じているなら、この記事はまさに“あなたのための内容”です。

この続きを知れば、今の苦しさの正体と、あなたが取るべき一番正しい選択肢が見えてきます。
Contents
訪問リハビリで「休めない」と感じるのはなぜか?
「急に休んだら利用者さんに迷惑がかかる…」
「休みたいと思っても代わりがいない…」
「毎日ギリギリで働いていて、辞めたい気持ちが強くなってきた…」
訪問リハビリで働く多くのPT・OT・STが抱えているのが、“休みにくい職場環境”という深刻な悩みです。
訪問リハビリで「休めない」「辞めたい」と感じる人の多くは、
- 心の余裕がなくなっている
- 人間関係やシフトに不満がある
- 疲れが取れない状態が続いている
- この先、働き続けられるか不安を感じている
しかし、その“しんどさ”には理由があります。

本記事では、訪問リハが休めない構造的な問題と、PTとしての心理負担の正体を徹底解説します。
「訪問リハの給料や単位の仕組みを詳しく知りたい方はこちらも参考になります。」
利用者や家族に迷惑をかけたくない心理的プレッシャー
訪問リハビリは、利用者とPTが1対1で深く関わる仕事です。そのため、急に休むと「申し訳ない」という感情が他職種より強く出る傾向があります。
▶なぜ訪問は“休み=迷惑”になりやすいのか?
- 担当制で利用者との関係が濃い
- 代行がすぐ見つからない
- 利用者・家族からの信頼が積み重なっている
- 「あなたでないと」と言われることが多い
このように、PT自身が抱える“使命感”が強すぎて、自分を犠牲にしてしまうケースが非常に多いのです。
▶心理的負担の正体は「責任感の強さ」
訪問リハで休めないと感じる人ほど、
- 真面目
- 責任感が強い
- 利用者思い
- 丁寧な仕事をする
こうした優秀なPTが潰れていく現状は、業界全体の課題と言えます。
代わりがいないシフト体制・慢性的な人手不足の現実
訪問リハの最大の問題は、“代わりがいない”ことを前提に運営されている事業所が多いことです。
▶現場でよくあるケース
- PT1~2名で何十名もの利用者を担当している
- 新人が入ってもすぐ辞めるためシフトが改善しない
- 管理者も訪問で手一杯でフォローできない
- 採用が追いつかず、常に人が足りない
訪問看護ステーションは近年急増していますが、リハスタッフの採用はどこも困難です。

結果として、1人が抱える利用者数が増え、 休みにくい雰囲気が生まれます。
▶訪問は「替えの効きにくい仕事」
訪問は“その人の生活に入り込む”リハビリ。急に担当が変わると利用者が不安になることから、PT自身が「私が行かなきゃ…」と追い込まれます。
しかし本来は、これは職場の組織体制の問題であり、PT個人の責任ではありません。
休みづらい職場文化・上司や同僚の目が気になる
訪問リハビリでは、職場文化が原因で休みづらいケースも多いです。
▶具体的にどんな文化があるのか?
- 「急な休み=迷惑」という空気がある
- ベテランが休まないので新人も休めない
- 有給を取りづらい雰囲気
- 体調不良でも出勤するのが“当たり前”の職場
このような事業所にいると、本来正当な権利である有給取得すら罪悪感を抱くようになります。
これは非常に危険な状態で、心身をすり減らして「辞めたい気持ち」が強くなる典型的なパターンです。
▶「見られている」感覚が強い職場は要注意
訪問リハでありがちなのが、
- 連絡が遅いと怒られる
- 移動時間や休憩を監視されている
- 訪問件数が多いほど評価される文化
こうした環境にいると、休むどころか毎日の業務にも追われ続けてしまいます。
休暇を申請する具体的な方法がわからない、言い出せない
訪問リハで休めないと感じる人の多くが抱えるもう一つの問題が、「休みたいと言い出しにくい」という悩みです。
▶よくあるPTの本音
- どう言えば角が立たないか分からない
- 急に休むと利用者さんが困るのが見える
- 上司が忙しそうで話しかけづらい
- 同僚の負担を増やしたくない

しかし、これはあなたの問題ではなく、「相談しにくい組織」側の問題です。
▶言い出しにくさを解消するためのポイント
- 早めの相談(最低1〜2週間前)
- 理由は簡潔でOK(詳細説明は不要)
- 代行者の調整は上司が担うべき仕事
- 体調不良は即時申請で問題なし
訪問は責任が重い仕事ですが、休むこと=悪ではありません。
むしろ、休める環境を作れない職場が問題です。
訪問リハビリで「休めない」「辞めたい」と感じる背景には、個人の努力では解決できない構造的な問題が多く潜んでいます。
無理に頑張り続けるほど、 心身が限界を迎え、取り返しのつかない状態になることも。

あなたが悪いわけではありません。
休めない環境・文化・体制を放置している職場側に責任があります。
「訪問リハビリを辞めたい」と思う瞬間とは?
「もう限界かもしれない…」
「訪問リハを辞めたいという気持ちが消えない」
そんな思いを抱えてこの記事を読んでいるあなたは、 相当なストレスを抱えているはずです。
訪問リハビリは、専門性が高くやりがいのある仕事ですが、その一方で“負担が蓄積しやすい働き方”でもあります。
実際に、訪問リハの退職理由を深掘りしていくと、 多くのPT・OT・STが次のような瞬間に「辞めたい」と感じています。
どれもあなたが悪いわけではなく、構造・環境・制度・職場の体制が影響していることがほとんどです。

ここでは、“リアルな辞めたい瞬間”を徹底的に解説します。
「訪問リハの仕事内容や働き方そのものについては、こちらの記事で深掘りしています。」
休めないストレスが限界に達したとき
訪問リハが「辞めたい」と最も強く感じる原因は、休めない=心身の回復ができないという構造的な問題です。
▶休めないと感じる具体的な状況
- 担当利用者が多すぎて、休むと他のスタッフに迷惑がかかる
- 「あなたじゃないとダメ」と言われて断りづらい
- シフトを管理する人が忙しく、申請しづらい
- 体調不良でも訪問をキャンセルしづらい空気
- 事業所の人数が少なく代行がいない
訪問は“担当制”のため、罪悪感が生まれやすく、普通以上に休みが取りにくい職場文化になりがちです。
▶この状況が続くとどうなるか?
- 慢性的な疲労
- 睡眠不足
- 休日でも仕事を思い出して休まらない
- メンタルがすり減る
- 「辞めたい」が口癖になる

この段階まで来たら、あなたの心身を守ることが最優先です。
利用者や家族とのトラブルやクレーム対応に疲れたとき
訪問リハは利用者や家族との距離が近い分、対人ストレスを感じる場面が多くなります。
▶訪問ならではのトラブル例
- 家族からの無理な要望(ほぼ介護希望など)
- リハビリ内容への不満
- 訪問時間の細かい指定・クレーム
- 在宅介護のストレスがPTに向けられる
- PTの判断を試すような言動
訪問は1対1で全てを受け止めるため、病院よりも精神的負担が重くのしかかります。
▶クレーム対応が積み重なると…
- 家に行く前から緊張する
- 移動中も気持ちが沈む
- 利用者対応のために自分の気持ちが消耗する
- 「自分には向いていない」と感じる
クレームはあなたの能力不足ではなく、訪問という環境特有のストレス要因です。
将来が見えずキャリアに不安を感じたとき
訪問リハは将来性が高いと言われていますが、「見通しが立たない」と感じて辞めたいと思うPTも一定数います。
▶キャリアに不安を感じる理由
- 管理者や役職者への道が見えない
- スキルを磨けている実感がない
- ただ訪問件数をこなすだけになっている
- 給与・昇給制度が不透明
- 他の職種の方がキャリアプランが明確に見える
訪問リハでキャリア視点を持つには、学べる環境かどうかが非常に重要です。
▶「このままでいいのか?」と感じ始めたら
- 自分のキャリア希望(専門性・役職・働き方)を明確にする
- 今の職場で実現可能か冷静に判断する
- 専門性を伸ばす働き方(呼吸・心リハ・生活期の強化)を検討する
キャリアの不安は、あなたの問題ではなく、職場が成長環境を提供できていないことが原因の場合も多いです。
体力・メンタルの消耗が激しく健康に影響を感じたとき
訪問リハは「体力的にも精神的にもキツい」と言われることがあります。
▶体力的な負担の例
- 1日4〜6件の訪問で移動が多い
- 階段の昇降、狭い家の中での介助
- 夏場・冬場の移動ストレス
病院とは違い、訪問は体力を削る要素が多いのが特徴です。
▶メンタルに影響が出やすい理由
- クレーム対応
- 孤独感(1人で判断する場面が多い)
- 同僚と話す時間が少ない
- 担当制によるプレッシャー
これらが積み重なると、次のような症状が出始めます。
- 寝ても疲れが取れない
- 毎朝仕事が憂うつ
- 趣味に興味がなくなる
- 利用者宅へ向かう足取りが重い
- 突然涙が出る・頭痛・動悸

もし当てはまるなら、もう限界のサインです。
その職場や環境が、あなたの心身に合っていない可能性が高いです。
訪問リハビリはやりがいのある仕事ですが、 辞めたいと感じる瞬間が多いのも事実です。
しかし大切なのは、あなたが悪いのではなく、環境や体制、職場の問題が原因であることがほとんどだという点です。
休みづらさ・辞めたい気持ちは「あなたのせい」ではない理由
訪問リハビリで働く多くのPT・OT・STが、「休めない」「辞めたい」という感情を抱えています。
しかしまず伝えたいのは、そのしんどさは“あなたの能力不足”や“甘え”では全くないということ。
あなたが悪いのではなく、訪問リハという業界特有の構造や、職場の体制が原因であることがほとんどです。

この記事では、他では語られない“休めない本当の理由”を、構造・比較・職場の依存という3つの視点から深掘りしていきます。
訪問リハ業界特有の構造的な問題
訪問リハは理想的な働き方に見える一方で、「休みにくさ」が生まれやすい構造的な課題を抱えています。
▶① 担当制ゆえに「あなたじゃないとダメ」が生まれやすい
訪問リハは1対1の関係が濃く、 利用者との信頼関係が強くなるのが特徴です。
その結果、
- あなた以外のPTでは不安
- 「先生じゃなきゃダメ」と家族に言われる
- 急な代行が利用者を混乱させる
このように、休みにくさが“制度そのもの”に内包されている側面があります。
「担当制が精神的負担になる人には、こちらの記事もおすすめです。」
▶② 最低人数で回す事業所が多い(採用難)
訪問看護ステーションの多くは、“ギリギリの人数”で運営しています。
- PT・OTを採用したくても応募が来ない
- 新人が定着しない
- リハ枠が埋まっておらず依頼が多い
結果として、誰か1人が休むと事業所が回らなくなる構造が出来上がります。
▶③ 経営的に「休む=減収」になりやすい仕組み
訪問リハは1件ごとの売上で成り立つため、 欠勤するとそのまま収益が落ちる構造です。
そのため、
- 管理者が休みに対して厳しい
- 休んだ分の訪問件数を後日に回される
- 「次は休みにくい…」という圧力が生まれる
これらはすべて業界の構造的な問題であり、あなたの努力でどうにかできるものではありません。
他の現場(病院・老健・デイサービス等)と比較してみると
訪問リハが休めない理由を理解するには、他の職場との比較が欠かせません。
▶① 病院(急性期・回復期)との比較
病院では、
- シフト制で代わりのスタッフがいる
- 多職種が近くにいる
- 休んでもカルテで情報共有される

そのため、急な休みが比較的取りやすい環境です。
一方、訪問は、
- 1人で1日のスケジュールを持っている
- 代行が責任重大
- 利用者宅ごとの細かい情報が共有しにくい
結果として、休むハードルが高くなります。
▶② 老健・デイサービスとの比較
老健やデイは「チームで利用者を見る」ため、
- 1人が休んでも全体でカバーできる
- 時間管理が規則的で予測しやすい
- 急な欠勤でも影響が少ない
訪問リハはこれと真逆で、“完全な個別対応”であることが休みにくさの根本です。
▶③ 訪問特有の「孤独感」が負担を増やす
訪問は常に1人で動くため、
- 相談相手がいない
- 全てを自分で判断する
- 責任が重く感じやすい
こうした精神的負担は、他のリハ職よりも辞めたい気持ちが強くなりやすい理由のひとつです。
あなたの頑張りが逆に職場を支えてしまっている現実
最も深刻で、そして多くのPTが気づいていないのが、「あなたが真面目に頑張るほど、職場があなたに依存してしまう」という現象です。
▶訪問リハに多い“優秀な人が損をする構造”
- 真面目な人ほど担当数が増える
- 休みを取りにくい人ほどさらに仕事を振られる
- 利用者満足度が高い人に頼りが集中する
- 管理者や事務が「この人なら大丈夫」と安心する
これはあなたが優秀だからこそ起きる現象で、頑張れば頑張るほど、「余裕が奪われる」構造が完成してしまいます。
▶あなたの努力が“当たり前”にされる危険
さらに、努力が当たり前視されるとこんなことが起きます。
- 残業・持ち帰り仕事が黙認される
- 「あの人はできるから」と業務量が増える
- 休むと逆に罪悪感を抱くようになる
これが積み重なると、あなたの頑張りが「負担」へと変わり、辞めたい気持ちが強くなるのです。
訪問リハビリで「休めない」「辞めたい」と感じるのは、 決してあなたの弱さや努力不足ではありません。

むしろ、訪問リハが抱える構造・環境・体制そのものが原因であり、あなたの責任では一切ありません。
あなたが悪いのではない。
あなたが頑張りすぎてしまうほど、職場があなたに依存してしまう構造が問題。
休みやすくする・辞めずに続けるための具体的な対策
ここまで「訪問リハビリが休めない・辞めたい」と感じる原因を解説しましたが、同時に理解してほしいのは、
“環境や工夫次第で、訪問リハを続けながら心身の負担を大幅に軽減できる”ということです。
もちろん、ブラック事業所にいる場合は転職が最優先ですが、環境改善で続けられるケースも多くあります。

ここでは、明日から使える具体策を「コミュニケーション」「代行体制」「転職」「セルフケア」の4つの軸で徹底解説します。
「訪問看護ステーションの人間関係を知りたい方はこちらの記事も必見です。」
上司・同僚とのコミュニケーションのコツ
訪問リハが休めない理由の多くは、「相談しづらい」「言い出せない」という心理的ハードルにあります。
そのため、まずはコミュニケーションを工夫するだけで 負担が大幅に軽減されることがあります。
▶① “早めに”相談するだけで受け止められやすくなる
訪問はスケジュール調整が必要なため、 前日や当日の休み申請は負担が大きいのが事実です。
逆に、
- 1〜2週間前
- 翌月シフト作成前
このタイミングで伝えると上司も調整しやすく、「嫌な顔をされない」可能性が一気に高くなります。
▶② 事務的に伝えてOK!説明は簡潔で大丈夫
多くのPTが「理由を詳しく言わないといけない」と考えがちですが、必要ありません。
例文:
【例1】「○日は有給を取得したいです。ご確認お願いします。」
【例2】「体調が不安定なので、早めに休暇調整をお願いしたいです。」
これだけで十分です。
▶③ “負担をかけて申し訳ない”を言いすぎない
真面目なPTほど謝りすぎますが、謝罪を繰り返すと「この人は我慢するタイプ」と認識されてしまいます。

意外かもしれませんが、淡々と伝える人のほうが休みやすい職場が多いです。
代行体制を整えるためにできること
訪問リハで休みにくい根本原因の1つは、「代行を頼みにくい・頼める人がいない」ことにあります。
しかし、あなたの工夫次第で代行のハードルを下げることができます。
▶① 利用者情報を“誰でも分かる形”にまとめる
代行がしにくい最大の理由は、「この利用者さんの状況が分からない」からです。
そのため、以下の情報を簡潔にまとめておくと代行が非常にスムーズになります。
- 基本動作(歩行・移乗・ADL)
- リスク(転倒・呼吸・疼痛など)
- 家族のスタンス(優しめ/厳しめ/要望強めなど)
- やってはいけない介入
- 本人の目標
上記を簡単に共有できるだけで、「代行しやすい利用者一覧」ができ、職場内の負担が減ります。
▶② 小さな引き継ぎを日常的に行う
訪問は1人で抱え込みがちですが、 ほんの少し共有するだけで負担が軽減されます。
例:
- 「○○さん、最近疲れやすいです」
- 「次回訪問で階段確認お願いします」
小さな共有を積み重ねると、いざ休むときのハードルが劇的に下がります。
休みやすい職場に転職する選択肢も検討する
環境改善でどうにもならない場合、転職は最も現実的で確実な解決策です。
特に、以下に当てはまるなら転職を検討すべきタイミングです。
▶① あなたが休むと事業所が回らない
これは完全に“職場の問題”です。
- リハが1〜2人しかいない
- 誰も代行できない仕組み
- 休むと管理者が怒る・ため息をつく
この環境ではあなたの心身が先に壊れます。
▶② 利用者の担当数が過剰(40名〜60名など)
担当数が多いほど休みづらくなり、毎日追われる感覚から抜け出せません。
担当25〜35名程度が一般的な適正ラインです。
▶③ 有給取得率が低い・休むと嫌味を言われる
これは完全にブラック傾向。
訪問リハの中には、
- 同行研修が長い
- 代行体制がしっかりしている
- リハが多く休みやすい
- 有給取得率が高い
というホワイト事業所も多く存在します。
“訪問はどこも同じ”と思う必要はありません。
心と体を守るセルフケアの具体例
訪問リハは体力・メンタルの消耗が激しく、本人が気づかないうちに限界に近づいていることがあります。

セルフケアは決して「甘え」ではなく、あなたのキャリアを守るために必要な技術です。
▶① 1日の中に“意図的な休憩”を挟む
訪問の合間に5分の休憩を取るだけで、疲労の蓄積が大幅に減ります。
▶② 感情を書き出す(モヤモヤを溜めない)
PTは優しい人が多く、感情を抑え込みがちです。紙に書き出すだけでも心の負担が軽くなります。
▶③ 同僚・他職種と月1で情報交換
訪問は孤独になりやすいため、意図的に誰かと話すだけでメンタルが安定します。
▶④「タスクを減らす」工夫をする
- 記録は音声入力を活用
- 訪問ルートを最適化
- 不必要な書類作業を見直す
1つ減らすだけでも負担は確実に減ります。
訪問リハはやりがいの大きな仕事ですが、 負担も大きく休みにくさが生まれやすいのが現実です。
しかし、
- 適切なコミュニケーション
- 代行体制の工夫
- 職場選びの見直し
- セルフケア
を行うだけで、「辞めたいほどつらい」状態から抜け出すことは十分に可能です。

あなたが今感じている苦しさは、 あなたの性格や努力不足が原因ではありません。
あなたには、もっと働きやすい環境を選ぶ権利があります。
「辞める」という選択肢を現実的に考える
訪問リハビリで働く多くのPT・OT・STが抱える悩み。

それが「休めない」「辞めたい」という強いストレスです。
あなたも、
- 「このまま続けたら体がもたない」
- 「心が限界かもしれない…」
- 「仕事のせいでプライベートが崩壊している」
と感じていませんか?
まず伝えたいのは、辞めたいと思うのは決しておかしいことではないということ。訪問リハは構造的に負担が大きく、あなたが悪いわけではありません。
そこでこの章では、「辞める」という選択肢を冷静に、現実的に検討するための視点をまとめました。
辞める=逃げではなく、あなたの人生を守るための大切な選択肢の一つです。
退職を決断する前に確認したいチェックリスト
辞めたい気持ちは強いものの、感情だけで判断するのは危険です。まずは以下のチェックリストで、状況を客観的に整理しましょう。
▶あなたの状況チェックリスト
- 1ヶ月以上「休みたいのに休めない」状況が続いている
- 上司に相談しても改善されなかった
- 担当利用者数が明らかに多すぎる(40〜60名以上)
- 代行体制が整っていない・誰も代わりに行けない
- 有給が取れず、申請すると嫌味を言われる
- 仕事のことを考えると胃が痛い・眠れない
- 毎朝、仕事に行くのがつらい・涙が出る
- 家庭やプライベートの時間がほぼない
- 訪問中に事故が起こるのではと常に不安
3つ以上当てはまる人は、「環境があなたに合っていない」可能性が高いです。
さらに5つ以上当てはまる場合、限界が近いサインと考えてよいでしょう。
「人間関係がストレスに感じる方には、こちらの記事も役立ちます。」
辞める前に知っておきたいリスクと準備
退職は大きな決断です。ただし、リスクを理解して事前準備さえしておけば、安心して次の一歩を踏み出せます。
▶① 収入が一時的に途切れる可能性
退職のタイミングによっては、翌月の給与が減ることがあります。
そのため、
- 最低2〜3ヶ月分の生活費を確保
- クレカの支払い日を把握
- 傷病手当金が使えるか確認
これらを事前に整えておくと安心です。
▶② 退職前の“引き継ぎストレス”への対策
訪問リハは担当制が多いため、引き継ぎでトラブルが起きやすい職種です。
- 情報を簡潔にまとめておく
- 引き継ぎの優先順位を決めておく
- 過剰な責任を背負わない(完璧でなくてよい)
特に「最後だから」と真面目にやりすぎると、あなたが余計に消耗します。
▶③ 次の職場が決まる前に辞めない
心身が限界の場合は例外ですが、可能なら“辞める前に転職先を決める”のが安全です。
理由は、
- 収入の空白期間がなくなる
- 精神的に余裕を持って選べる
- 焦って妥協するリスクがなくなる
訪問リハは需要が高いため、良い職場は必ず見つかります。
転職先の選び方とおすすめの職場環境
訪問リハが合わなかったからといって、“リハ職全体が向いていない”わけではありません。
あなたに合った環境を選べば、「休める」「続けられる」「心が軽くなる」働き方は実現できます。
▶① 休みやすさを最重要で選ぶ
求人を見るときは、以下を必ずチェックしてください。
- 有給取得率
- 代行体制・人数体制
- リハ職の人数(少人数は危険)
- 急な欠勤時の対応マニュアルの有無
- 管理者のタイプ(経験豊富・穏やか・現場理解あり)
特に以下の職場は休みやすい傾向があります。
- リハ職が多い訪問看護ステーション
- 大手法人の訪問リハ
- デイサービス(負担少なめ)
- 老健(チーム制・代行が効きやすい)
▶② その職場の“文化”を見る
求人票だけではわからないのが「職場の文化」。
例:
- スタッフが楽しそうに働いているか
- 管理者の話し方が柔らかいか
- 新人へのフォローが手厚いか
- 休むことが普通に受け入れられているか
職場見学や面接の雰囲気は非常に重要です。
訪問リハ以外のキャリアパスとその魅力
訪問リハが合わないからといって、あなたのキャリアは終わりではありません。
むしろ訪問の経験は、他の職場でも非常に高く評価されます。
▶① 病院(急性期・回復期)
チームでの支援が多く、休みやすい環境が整っている職場が多いです。「1人での訪問がつらい」人におすすめ。
▶② 老健・デイサービス
負担が少なく、規則的な働き方がしたい人に向いています。「メンタルを立て直したい」「時間に余裕がほしい」人に最適。
▶③ クリニック・外来リハ
専門性を高めたい人、運動療法が好きな人に人気。夜勤もなく生活リズムが作りやすいです。
▶④ 福祉用具・企業系(営業・インストラクター)
訪問で培ったアセスメント能力が活かされます。
▶⑤ フリーランス・パラレルワーク
働く時間を自由に決めたい人向け。ただし収入が不安定になる可能性もあるため慎重に検討が必要です。

訪問リハがつらくて辞めたい気持ちは、あなたの弱さではありません。
環境の問題であり、構造の問題であり、あなたの人生を守るために「辞める」という選択肢を持つのは自然なことです。
あなたはもっと休めて、もっと自分を大切にできる職場を選んでいい。
実際に休める・辞めた人たちの体験談から学ぶ
「今の職場では休めない…」
「もう辞めたいけど、辞めた先が不安」
そんな悩みを抱えるあなたにとって、実際に行動した人のリアルな体験談ほど参考になるものはありません。
この章では、
- 休める職場に転職して人生が変わったPT
- 思い切って辞めて新しい道を歩んでいる人
- 働きやすさを最優先に職場を選び直した人
など、“生きた情報”をまとめています。
休みやすい職場に転職した事例
まずは、訪問リハから「もっと休める職場」に転職して、働き方を大きく改善したPTの実例を紹介します。
▶事例①:1人職場→大手法人の訪問へ転職し、休みが月4日→月10日に
30代・男性PT(訪問→訪問)
前職はリハ職が自分1人。「休む=職場が止まる」という状況で、有給なんて夢のまた夢。
▼転職後の変化
- リハスタッフ10名以上の大型ステーション
- 代行体制がしっかりしていて罪悪感なし
- 毎月のように有給取得が可能に
- 精神的な負担が激減
本人のコメント:
「同じ訪問リハでも、職場が違うだけでこんなに働き方が変わるとは思わなかった。」
→訪問が合わないのではなく、職場の人数と体制が問題だったケースです。
▶事例②:訪問→老健へ転職し、時間に追われない生活を手に入れた
20代・女性PT(訪問→老健)
訪問の移動と担当数の多さで、毎日ヘトヘト。休みの日も「利用者のことで頭がいっぱい」。
▼転職後の変化
- チームで利用者を見るため負担が大幅に軽減
- 急な休みも交代しやすい環境
- 定時退社があたりまえに
- 心の負担が“0”に近づく
本人のコメント:
「仕事のことを考えずに夜眠れるようになった。それだけで転職して良かった。」
▶事例③:精神的に限界→病院に戻り、再びPTとしての自信を取り戻した
30代・男性PT(訪問→回復期)
クレーム対応、利用者宅での判断の連続、孤独感が積み重なって限界に。
▼転職後の変化
- チームで相談できる環境
- 上司・医師・他職種と気軽にディスカッション可能
- 専門性を深められる研修制度
コメント:
「訪問がダメだったんじゃなくて、1人で抱えすぎていただけだった。」
→“訪問疲れ”の人にとって回復期は最適な環境になりやすいです。
辞めて違う道に進んだ人のケース
訪問リハを辞めたPTの中には、リハ以外の道に進んで成功している人も多くいます。
▶事例①:福祉用具の営業へ転職し、収入アップ&休みが取りやすい働き方に
訪問リハと深い関係がある福祉用具の仕事は、PTの経験がフルに活かされます。
- 訪問先のアセスメント能力を高評価
- 土日休み&連休取得可能
- インセンティブで収入がUP
コメント:
「移動は多いけど訪問より気が楽。休みが普通に取れるのが何よりありがたい。」
▶事例②:デスクワーク中心の企業リハアドバイザーに転身
PTの知識を活かして企業の健康サポートを担当。
- 夜勤も移動もなし
- 在宅勤務OK
- 体力を使わない働き方ができる
コメント:
「“体力に頼らない働き方”ができている実感が、大きな安心感につながっている。」
▶事例③:パラレルワークで週3訪問+週2在宅ワークの働き方へ
訪問の良さを活かしつつ、週5フル勤務の負担を軽減したケース。
- 訪問は好き、でもフルタイムはしんどい
- 週3勤務で収入は最低限確保
- 空いた時間でWebライターや講師業
→やり方次第で、辞めずに続ける“折衷案”も可能です。
休みやすさ・働きやすさを重視した職場の探し方
最後に、「もう休めない職場はイヤ」「働きやすいところでリハを続けたい」 という人のために、職場選びのポイントをまとめます。
▶① リハ職の人数が多い職場を選ぶ
人数が多いほど、以下が実現します。
- 代行がしやすい
- 休むことに罪悪感が生まれない
- 情報共有がしやすい
特に大手法人の訪問ステーションはおすすめ。
▶② 管理者のタイプを最重視する
働きやすさの8割は上司で決まると言っても過言ではありません。
面接・見学で以下をチェック:
- 声かけが優しいか
- スタッフを大切にしているか
- 急な休みに理解があるか
- 離職率を隠さずに話すか
管理者の性格は、休みやすさに直結します。
▶③ “担当数”と“訪問件数”を必ず確認する
働きやすい訪問は、
- 担当:25〜35名
- 訪問:1日4〜5件
このラインを大きく超える場合、休みにくくなる傾向があります。
▶④ 有給取得率・代行制度を質問する
面接で聞くべき質問:
- 「急な休みのときはどう対応しているか?」
- 「リハ職同士で代行し合える仕組みはあるか?」
- 「有給取得率はどのくらいですか?」
この3つで“ホワイト度”はある程度判断できます。
訪問リハで苦しい思いをしているあなたに伝えたいのは、「休める働き方は必ずある」ということです。
休めない・辞めたいと悩むのは、あなたが弱いからではありません。ただ単に今の職場があなたに合っていないだけです。
この記事で紹介した体験談のように、環境を変えればQOLが驚くほど上がります。

そしてあなたも、「ちゃんと休める」「安心して働ける」職場を選ぶ権利があります。
「“休める職場に行きたい”と感じた方は、転職先選びのポイントをまとめた記事が参考になります。」
【ここでしか読めない】訪問リハビリの「裏側」|業界関係者が語る本音
「なんでこんなに休めないの?」
「訪問リハって、どうして辞めたいほどつらくなるの?」
この記事では、管理者・経営側・現場PT… 業界の“内側”にいる人たちから集めた、本音の声をまとめました。

休めない構造の根本原因と、あなたの働き方を本気で変えるためのヒントを解説していきます。
管理者が抱える悩みと休みを取りにくくする真因
訪問リハの管理者は、「休むなら早めに言ってほしい」「代行が難しい」 とよく言います。
でもその裏側には、あなたが知らない管理者の苦悩があります。
▶①「代行できる人材」がそもそも足りない
管理者がよく口にするのがこれです。
- 採用しても応募がこない
- 新卒PTは訪問を選びにくい
- 中堅PTは訪問に不安がある
つまり、多くのステーションは慢性的な人手不足で運営されています。
この状態だと、あなたが休むたびに管理者は、
- ケアマネへ連絡
- 利用者への説明
- スケジュールの再調整
- 代行スタッフ探し
と、膨大な仕事を抱えます。
結果として、休みに対して敏感になってしまうのです。
▶② 経営的に「休む=売上減」だから
訪問は、1件ごとに売上が決まるビジネスモデル。
そのため、「スタッフが休む=売上が減る」という現実があります。
管理者としては、
- 赤字になりたくない
- 上からのプレッシャーがある
- 稼働率を維持しないと評価が下がる
という葛藤を抱えているのです。
▶③ スタッフを守りたいが、守りきれない矛盾
本音を聞くと、多くの管理者はこう言います。
「スタッフには休んでほしい。でも現状では難しい…」
あなたのしんどさは、管理者のマネジメント不足だけが原因ではなく、業界構造そのものに問題があるのです。
経営側の視点から見る「休みやすい職場」の条件
訪問リハにおいて“休みやすい職場”は、偶然ではなく明確な条件があります。
業界の経営者が語る「休める職場の仕組み」を紹介します。
▶① 人数体制が厚い(リハ職5〜10名以上)
これは絶対条件です。
人数が多いほど、
- 代行がしやすい
- 急な休みのカバーが簡単
- 精神的負担が少ない
逆に、リハ職1〜3名の小規模ステーションは、休みにくさの温床になりがちです。
▶② 経営者が「スタッフを消耗品扱いしない」
ホワイト事業所の経営者は、必ずこう言います。
「スタッフが元気でいてこそ、事業は成り立つ」
そのため、
- 稼働率よりスタッフの心身を優先
- 無理な件数を詰め込まない
- 有給取得を当たり前に認める
という方針がはっきりしています。
▶③ 教育と情報共有の仕組みが整っている
休みやすい職場には、共通した特徴があります。
- 利用者情報の共有が簡単
- 記録が整理されていて代行しやすい
- 新人育成に余裕がある
つまり、「誰が休んでも回る」仕組みが整っているのです。
▶④ 管理者が“プレイヤー兼管理者”になっていない
管理者自身が訪問で手一杯だと、スタッフのフォローができません。
休みやすい職場は、
- 管理者が現場に出すぎない
- マネジメントに専念できる
- スタッフと話す時間がある
という特徴があります。
現場の声を変えるために必要な行動

「休めない」「辞めたい」と感じるのは、 あなた一人の問題ではありません。
しかし、現場の空気を変えるためにあなた自身ができる行動も存在します。
▶① 小さな“共有”を増やす
訪問リハは孤立しやすい働き方です。
ですが、1日1回の共有でも、職場全体の負担が軽くなり、休みやすい文化が育ちます。
- 利用者の状態変化を共有
- 困りごとを相談
- 代行しやすい記録の書き方を工夫

あなたの小さな行動が、職場を変える第一歩になります。
▶② 「無理なスケジュールにはNO」と言う勇気
訪問リハの世界は、真面目な人ほど損をする構造です。
だからこそ、
- 件数を詰め込まれたら「難しい」と伝える
- 担当数が多すぎたら相談する
- 明らかに無理な依頼は断る
こうした主張は、あなたを守る行為です。

むしろ「できないことはできない」と言える人のほうが、職場から大切にされます。
▶③ “休むのが当たり前”という空気を作る
休みにくい職場は、例外なく「遠慮の文化」があります。
逆に、休める職場は「休みは権利」という価値観が根付いています。
そのためには、
- 有給を堂々と申請する
- 体調不良のときは無理しない
- 他のスタッフが休む時も肯定的に受け止める

こうした小さな積み重ねが、休みやすい雰囲気を育てます。
▶④ 「休める職場」に転職するという最終手段も持つ
どれだけ頑張っても、環境そのものがブラックなら改善は不可能です。
あなたが自分を守るために、「ここはもう限界だ」と判断することも大切です。
訪問リハでも、休める職場は確実に存在します。
もし今の職場がどうにもならないなら、環境を変えることは“逃げ”ではなく“戦略”です。
訪問リハビリが休めない・辞めたいと感じる理由は、あなたの性格や能力ではなく、 業界構造・職場体制・管理者の負担が重なった結果です。
その裏側を知ることで、あなたの心はきっと軽くなります。

そして覚えていてほしいのは、あなたには、自分の人生を大切にできる職場を選ぶ権利があるということ。
「“割に合わない”と感じやすい理由を整理した記事はこちらです。」
まとめ|訪問リハビリで「休めない・辞めたい」と感じるあなたへ
訪問リハビリの裏側には、あなた一人ではどうにもできない構造的な問題が潜んでいます。
そのため、苦しさを抱えるのは当然のことであり、あなたが弱いわけでも、頑張りが足りないわけでもありません。
この記事で解説した“休めない理由”と“改善のヒント”をまとめると、以下のようになります。
▼この記事の重要ポイント
- 訪問リハが休みにくいのは、構造的な人手不足と担当制が原因
- 管理者側にも「代行がいない」「売上が下がる」などの苦悩がある
- 経営者の価値観で職場文化は大きく変わり、ホワイト職場は必ず存在する
- 人数体制が厚い職場ほど休みやすく、ストレスが少ない
- 小さな共有・コミュニケーションが“休める空気”を作る第一歩
- 無理なスケジュールには「NO」と言っていい(あなたの責任ではない)
- 休めない職場は、あなたを消耗品として扱っている可能性がある
- 訪問が合わないわけではなく、環境が合っていないケースが多い
- 休める訪問リハは「大手法人」「人数の多いステーション」に集中している
- 今の職場が改善しないなら転職も“正しい選択肢のひとつ”
- 訪問リハ以外にも、病院・老健・デイ・企業・福祉用具など道はたくさんある
- あなたには、もっと大切にされる環境で働く権利がある
訪問リハビリはやりがいが大きい一方で、 負担も大きく、孤独になりやすい働き方です。

だからこそ、一人で抱え込まず、環境に目を向けることが大切です。
今の苦しさは“あなたのせい”ではありません。 そして、あなたには必ず“もっと休める環境”があります。
次に進むかどうか悩んでいるあなたが、 この記事で少しでも気持ちが軽くなり、 自分を大切にする一歩を踏み出せることを願っています。