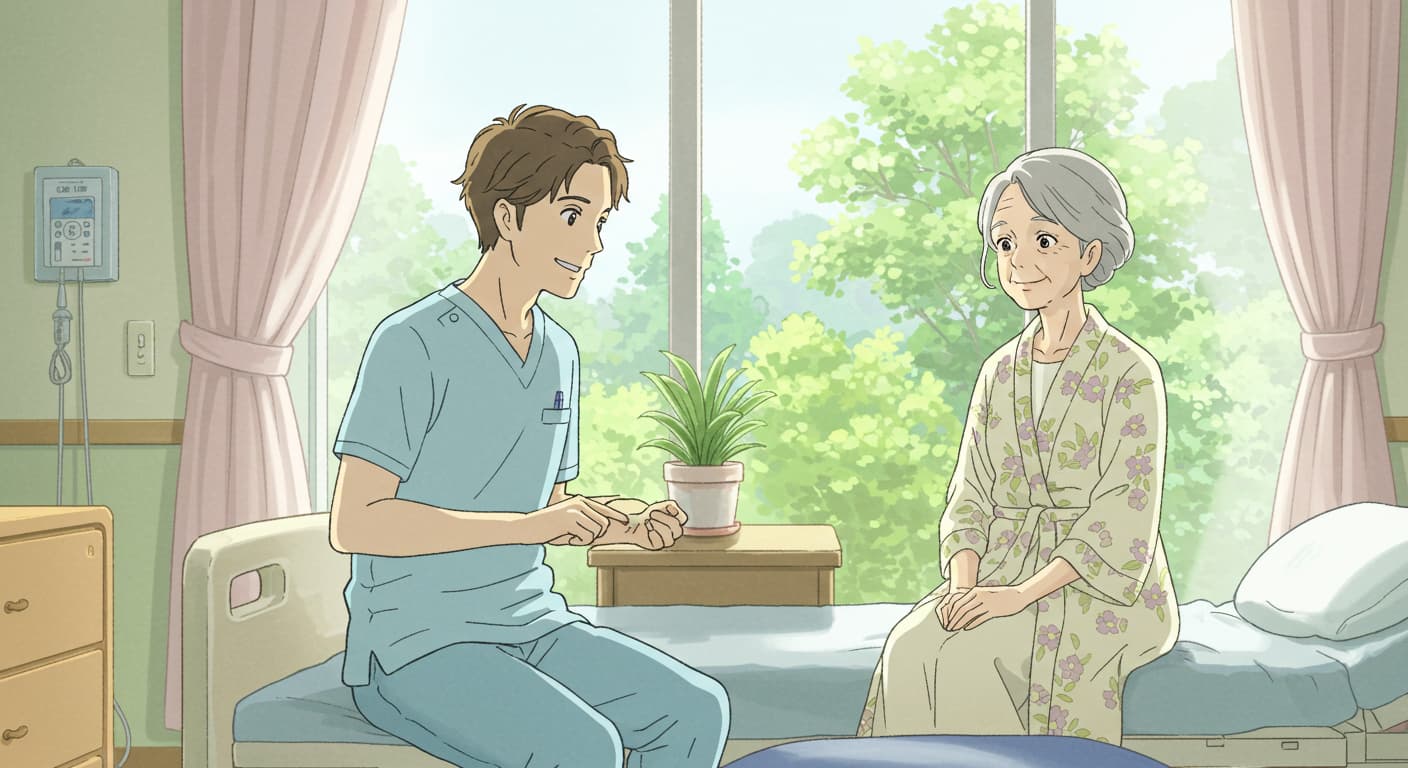「理学療法士なのに、人と話すのが苦手…自分は向いていないのかもしれない。」
そう感じて、ため息をついたことはありませんか?
患者さんとの会話が続かない。先輩にうまく相談できない。雑談が苦手で職場に居づらい――。
けれど、それは“あなたが劣っている”からではありません。
実は、コミュニケーションに悩む理学療法士はとても多く、
「明るく話せない自分」を責めるあまり、本来の優しさや観察力を発揮できていない人がたくさんいます。
ポイント
この記事では、そんなあなたが「無理に変わらなくても大丈夫」と心から思えるように、
コミュ障に悩む理学療法士の“リアルな現場の声”と“明日からできる小さな工夫”を、
専門家視点でわかりやすくお伝えします。

読後にはきっと、「自分らしく働くヒント」が見えてくるはずです。
Contents
理学療法士が「コミュ障」で悩むのは普通です
「患者さんとの会話がうまく続かない」「先輩や看護師と話すのが怖い」──
そんな悩みを抱える理学療法士は、実は決して少なくありません。
リハビリ職は“コミュニケーションが命”と言われる一方で、
毎日患者さん・家族・医師・看護師など多職種と関わるプレッシャーも大きく、
「自分はコミュ障だから向いてないのでは?」と悩む声が非常に多いのが現実です。
しかし、結論から言えば 「コミュ障に悩む理学療法士」は珍しくありません。
大切なのは「向いていない」と決めつけることではなく、
「どうすれば無理なく関われるか」を見つけることです。

ここでは、理学療法士が感じやすい“コミュ障の壁”の正体と、
現場で活かせる実践的なヒントをお伝えします。
理学療法士に求められるコミュニケーション力とは
理学療法士の仕事における「コミュニケーション力」は、
単に“話すのがうまい”という意味ではありません。
重要なのは、相手の状態を正しく理解し、安心感を与える力です。
たとえば――
- 患者との信頼関係構築(リハビリを継続するモチベーションに直結)
- チーム医療での情報共有(医師・看護師・OT・STとの連携)
- 家族への説明力(在宅復帰・介護方針の理解を得る)
つまり「会話の量」ではなく、
相手がどう受け取るか・どう安心できるかがポイントです。
実際、患者さんの多くは“明るく話すセラピスト”よりも
“静かでも丁寧に対応してくれる人”に信頼を寄せる傾向があります。

「話すのが苦手=理学療法士に向いていない」ではなく、
誠実な態度や観察力も立派なコミュ力なのです。
「コミュ障」と感じる理由と心理的背景
では、なぜ理学療法士は“コミュ障”に悩みやすいのでしょうか。
主な理由は以下の3つです。
① 学生時代から「技術中心」の教育環境
理学療法士養成課程では、解剖学・運動学など技術系科目が中心。
コミュニケーション技術は「現場で学ぶもの」とされがちです。
そのため、就職してから人間関係に直面し、戸惑うケースが多発します。
② 多職種連携のストレス
医師・看護師・介護士など、上下関係や専門領域の違いがある中で、
“自分の意見をどこまで言っていいのか”が分からず萎縮してしまう人も。
③ 患者対応の「感情労働」
リハビリでは、患者の感情や痛みに日々向き合います。
拒否・怒り・涙…といったリアクションを受けるうちに、
「どう接すればいいのか分からない」と不安が強くなるのです。
このように、“コミュ障”とは単なる性格ではなく、
職場環境と経験不足によって生じる一時的な適応反応であることが多いのです。
「“話し方が強い”“偉そう”と思われてしまう背景には、職場文化の影響もあります。【PTが偉そうと言われる理由】もぜひ参考に。」
実はコミュ力に悩む理学療法士は多い!データで見る現状
公益社団法人日本理学療法士協会の調査や、各種アンケート結果を見ると、
理学療法士のうち 約6割以上が「コミュニケーションに苦手意識がある」 と回答しています。
特に新人・2〜3年目のセラピストでは、
「患者との関係づくりが難しい」「先輩と話すのが怖い」という声が多く、
経験年数より“慣れと自信”の差が大きな要因になっています。
また、近年ではSNS上でも
「会話が苦手でも理学療法士を続けられる?」「患者さんと沈黙が怖い」
といった相談投稿が増えており、同じ悩みを持つ人が多数存在することがわかります。
つまり、“コミュ障に悩む理学療法士”は、
特殊でも恥ずかしいことでもなく、極めて一般的な悩みなのです。

むしろ、その悩みを自覚して改善に向き合おうとする姿勢こそ、
信頼される医療者への第一歩と言えるでしょう。
患者さんとのコミュニケーションが苦手なときの対処法
「話すのが苦手」「何を話せばいいのか分からない」「沈黙が怖い」──
そんな不安を抱える理学療法士は多いものです。
しかし、コミュニケーションは“話す技術”ではなく、信頼関係を築くプロセス。
苦手意識を減らすためには、「聴く」「理解する」「共感する」ことから始めましょう。

ここでは、臨床現場で実際に役立つ“対話の型”と“具体フレーズ”を紹介します。
どんな患者さんでも安心して関われるようになる「実践的コミュ力」を身につけましょう。
基本は「聴く」から始める:信頼を築くステップ
コミュニケーションに苦手意識がある理学療法士ほど、
「何か話さなきゃ」と焦って“沈黙”を埋めようとしがちです。
しかし、患者さんが本当に求めているのは「うまい会話」ではなく、
“自分の話を聴いてもらえている”という安心感です。
聴く力を高める3つのステップ
| ステップ | 内容 | 実践例 |
|---|---|---|
| ① 相手の話を遮らない | 沈黙を恐れず、相手が話し終えるまで待つ | 「そうなんですね」「もう少し詳しく聞かせてください」 |
| ② 共感を言葉にする | 相手の感情をくみ取って反応する | 「それは大変でしたね」「不安な気持ちになりますよね」 |
| ③ 非言語を意識する | 表情・うなずき・姿勢で安心感を与える | 優しくうなずく、目線を合わせる、穏やかに微笑む |
特に高齢者や長期入院患者は、
「聞いてもらえること」自体がリハビリ意欲を左右することもあります。

話すより、聴く。これが信頼関係づくりの第一歩です。
「新人のうちは“伝え方がわからない”“距離感が難しい”と感じやすいものです。【新人PTが抱える悩み】も共感できるはずです。」
失語症や構音障害の患者さんとの接し方
失語症・構音障害の患者さんとのやり取りでは、
「伝わらない」「聞き取れない」というもどかしさが双方に生まれます。
ここで焦ってしまうと、患者さんは「迷惑をかけている」と感じ、
リハビリへの意欲が低下してしまうことも。
対応のコツ
- ゆっくり・短い文で話す
→ 一文を10〜15文字以内に区切る(例:「今日は歩行の練習をしましょうね」) - 選択肢を提示する
→ 「痛いですか?」「うん」「ちょっと」「いいえ」など、Yes/Noで答えられる質問にする - 視覚情報を活用する
→ 写真・絵カード・ホワイトボードを活用して理解を助ける - 焦らず待つ
→ 言葉が出るまで10秒以上待つことも大切
「沈黙=失敗」ではありません。

相手が言葉を探している時間を尊重することが“最高のコミュ力”です。
発達障害・認知症患者さんへの対応の工夫
発達障害や認知症の患者さんの場合、
“言葉のキャッチボール”よりも環境と雰囲気づくりが重要です。
発達障害の方への対応
- 急な予定変更は避ける:見通しのあるスケジュールを提示
- 具体的な指示を出す:「もう少し頑張って」より「あと3回曲げましょう」
- 声のトーンを一定に保つ:大きすぎる声や急な変化は混乱を招きやすい
認知症患者さんへの対応
- 否定しない:「違います」ではなく「そうなんですね」と受け止める
- 過去の話題を活かす:昔の職業や家族の話を引き出すと安心感を得やすい
- 短く・ゆっくり・同じ言葉で繰り返す:理解力の低下を補う
難しい場面で使える具体的なフレーズ集
コミュニケーションに詰まったときは、
あらかじめ“使いやすい定型フレーズ”をいくつか持っておくと安心です。
【患者との会話が続かないとき】
- 「今日はどんな気分ですか?」
- 「昨日は眠れましたか?」
- 「最近、体の調子はどうですか?」
→ 開かれた質問(オープンクエスチョン)で相手が話しやすくなります。
【ネガティブな発言への対応】
- 「焦らなくて大丈夫ですよ」
- 「少しずつでOKです。無理は禁物です」
- 「前回よりも良くなってますね」
→ 否定せず、努力や変化を“見える化”する言葉を使う。
【沈黙が続くとき】
- 「ちょっと疲れちゃいましたね。少し休みましょう」
- 「今日は天気がいいですね」
→ 雑談も“心のリハビリ”。会話のクッションとして有効です。
理学療法士自身の「コミュ障」を克服するためのヒント
理学療法士として働いていると、「患者さんとの会話が苦手」「多職種カンファレンスで発言できない」「人と関わるのが疲れる」と感じる瞬間は誰にでもあります。
特に“コミュ障”を自覚している人は、「理学療法士に向いてないのでは」と落ち込んでしまいがちです。
しかし大切なのは、“コミュニケーションが苦手”という現実を否定することではなく、自分の特性を理解して、できる形で関わり方を見つけていくこと。

ここでは、「話すのが苦手でも現場で信頼を得られる理学療法士」になるための具体的なステップを紹介します。
自分の特性を理解する:自己分析の方法
まず最初にすべきは、「なぜ自分はコミュニケーションに苦手意識を持っているのか」を知ることです。
“コミュ障”という一言でまとめてしまうと、対処法も曖昧になります。
自己分析の3ステップ
| ステップ | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① 苦手な場面を洗い出す | どんな状況で緊張・萎縮するかを明確にする | 「患者さんに雑談を振る時」「先輩に相談するとき」など |
| ② 原因を整理する | 性格・経験・環境などに分けて考える | 「完璧主義」「否定された経験」「人が多い職場」など |
| ③ 得意な関わり方を見つける | 無理せず続けられるスタイルを探す | 「静かに話を聞く」「丁寧な言葉づかい」など |
特に理学療法士の場合、「自分の価値=コミュ力の高さ」ではないということを忘れないでください。
臨床では「相手を尊重する姿勢」や「観察力」「聴く力」こそが真のコミュニケーション能力です。

たとえば、無理に明るく振る舞うよりも、「静かだけど信頼できる先生」というポジションを築く方が、結果的に患者さんからの評価は高くなります。
小さな成功体験を積むトレーニング法
コミュニケーションは“スキル”です。
筋トレと同じで、少しずつ成功体験を重ねることで確実に上達していきます。
実践できるトレーニング法
- 「一言返す」練習から始める
→ 無理に会話を続けようとせず、まずは「おはようございます」「今日は天気いいですね」など、1往復の会話を日常に取り入れる。 - “聞き上手”トレーニング
→ 相手が話しているときに「へぇ」「なるほど」「そうなんですね」と相槌を意識的に打つ。
→ 5分間「聞く」に徹する練習をしてみる。 - 自己紹介の型をつくる
→ 初対面の場面では「出身地+趣味+仕事のやりがい」など、自分の中でテンプレを決めておくと安心。 - 雑談メモをつける
→ 患者さんの好きな話題(孫の話・趣味・天気・食べ物など)をカルテの隅にメモしておくと、会話が続けやすくなる。 - 1日1回「ありがとう」を言う
→ 感謝を伝える言葉は、最も簡単で最も信頼を生むコミュニケーション。
これらを毎日少しずつ実践することで、
「自分でも話せた」「患者さんが笑ってくれた」などの小さな成功体験が増え、
自然と苦手意識が薄れていきます。
どうしても苦しいときに頼れる支援先・相談窓口
コミュニケーションへの不安が強く、「職場に行くのがつらい」「誰にも相談できない」と感じたとき、
無理をして自分の中で抱え込むのは危険です。
そんな時は、専門のサポート機関やキャリア相談を活用しましょう。
主な相談先一覧
| 種類 | 内容 | 相談先例 |
|---|---|---|
| 職場内相談 | メンター・教育担当・管理職に相談し、業務負担や人間関係を調整 | 所属部署のリーダー、教育委員会など |
| 理学療法士協会系 | キャリアやメンタル支援制度を提供していることも | 日本理学療法士協会「キャリアサポート窓口」 |
| 医療従事者向けメンタル支援 | 職業ストレス・バーンアウト相談 | 「こころの耳(厚生労働省)」「産業保健総合支援センター」 |
| 転職支援サービス | 自分に合った職場環境を相談可能 | レバウェルリハビリ、マイナビコメディカルなど |
また、同じ悩みを持つ仲間の声を聞くだけでも、気持ちは軽くなります。
SNSやオンラインコミュニティ(例:理学療法士のキャリア系Xアカウントなど)では、
“コミュ障PT”を公言しながら活躍している人も多数います。
「苦手」は“弱点”ではなく、“工夫の種”。
克服しようとするプロセスそのものが、あなたの臨床力を確実に高めていきます。

このように、「理学療法士×コミュ障」は決してマイナスではありません。
むしろ、人の痛みや気持ちに敏感なあなたこそ、共感力に優れた医療者です。
焦らず、少しずつ“自分らしいコミュニケーションスタイル”を築いていきましょう。
「若手が多い職場ほど、経験や考え方の差から誤解が生まれやすい傾向があります。【PTの年齢層事情】もチェックしておきましょう。」
職場内のコミュニケーションを円滑にするには
理学療法士として働くうえで、患者対応だけでなく職場内コミュニケーションも避けて通れません。
しかし、「上司や先輩が怖くて話しかけづらい」「カンファレンスでうまく意見が言えない」「チームの輪に入れない」と感じている人も多いはず。
実は、“コミュ障”を自覚する理学療法士の多くが悩むのは対人スキルそのものではなく、「どう接すればうまくいくか分からない」という不安。

ここでは、現場でストレスをためずに働くための「話しかけ方・関わり方・トラブル対応」を、実践的に解説します。
上司や先輩に話しかけやすくするコツ
「忙しそうで声をかけにくい」「雑談が苦手で距離が縮まらない」──
こうした悩みを解消するには、“タイミング”と“きっかけづくり”がポイントです。
① 話しかけるタイミングを見極める
- 昼休み直前・夕方のカルテ整理中など、集中が切れやすい時間帯を狙う。
- 朝のバタバタした時間帯や会議直後は避けるのが鉄則。
- 「今お時間大丈夫ですか?」とワンクッション入れるだけで印象は格段に良くなります。
② 用件+感謝で話を切り出す
- 「昨日の〇〇の件、教えていただきたいことがありまして」
- 「お忙しいところすみません。ちょっとだけ確認したいことがあります」
→ 相手を立てながら本題に入ることで、スムーズに話しやすくなります。
③ 雑談の“型”を決めておく
苦手な人は、無理に盛り上げようとする必要はありません。
- 「この前〇〇の患者さん、すごく頑張ってましたね」
- 「〇〇先生のストレッチの教え方、分かりやすいですね」
といった仕事に関連した話題を中心に選ぶと、自然な会話が生まれやすいです。
チームワークを高める具体的な行動例
理学療法士の現場は、医師・看護師・作業療法士・言語聴覚士・介護職など、多職種との連携が不可欠です。
ここで重要なのは、「チームの一員として信頼される行動」を意識すること。
「看護師など他職種との関係性に悩むなら、【リハ職×看護師の人間関係】の記事も参考になります。」
① 報連相を「早く・簡潔に・丁寧に」
- 例:「〇〇さん、歩行時のふらつきが増えていたので、午後もう一度確認します」
- ポイント:主観よりも事実+今後の行動をセットで伝える。
② 感謝と挨拶を“ルーティン化”する
- 「今日もよろしくお願いします」「お先に失礼します」など、あいさつを自然に口に出す習慣を。
- 感謝を伝える「〇〇してもらって助かりました」も、小さな一言で印象が変わります。
③ 情報共有は「メモ・ホワイトボード」で見える化
- 口頭だけではなく、共有ノートや電子カルテに残すことでトラブルを防止。
- 「共有しておいた方がよさそう」と思ったら、必ず残すクセをつける。
④ チーム内での“立ち位置”を意識する
- 発言が苦手でも、「聞き役」「まとめ役」として貢献できる。
- 会議中に「なるほどですね」「整理すると〇〇ですね」と要約の一言を添えるだけで評価が上がる。
トラブルが起きたときの対処法
人間関係がある以上、誤解・衝突・気まずさは避けられません。
「もう話したくない」「居づらい」と感じたときこそ、冷静な“言葉の整理力”が必要です。
① 感情的にならず「事実」を切り分ける
- 「あの人が嫌い」ではなく、「〇〇の指示が分かりづらかった」「報告の行き違いがあった」と具体的な原因を言語化。
- 事実ベースで話せば、感情的な対立を避けられます。
② 早めに第三者を挟む
- 上司・主任・教育担当など、中立的な立場の人に相談。
- 「愚痴」ではなく「今後どうしたらよいか相談したい」というスタンスを取る。
③ 謝罪・修正はスピードが命
- たとえ自分に非がなくても、「誤解を招く表現をしてしまってすみません」と先手でフォローすることで関係修復が早まる。
④ 長期的に関係が悪化している場合は環境を変える
- どうしても改善が見込めない場合は、転職や部署異動を検討するのも選択肢のひとつ。
- 「人間関係が合わない=自分が悪い」ではありません。
コミュ障の人ほど、“我慢しすぎる傾向”があります。

本来の実力を発揮するためにも、自分を守る行動も立派なプロの選択です。
「コミュ障だから職場がしんどい」と思っている理学療法士こそ、
実は相手の気持ちを考えすぎるほど優しいタイプです。
だからこそ、“完璧な会話”を目指すより、
「伝わる仕組み」「安心できる距離感」を意識していけば、
必ずチームの中で信頼される存在になれます。
現役理学療法士の体験談:コミュ障からの脱却ストーリー
「患者さんとうまく話せない」「先輩に質問するのが怖い」「自分は理学療法士に向いていないのかも…」

新人時代、私(理学療法士歴10年)もそう感じていました。
周りの同期は明るくて会話が上手、自分だけが“壁”を感じていたのです。
しかし今では、患者さんや多職種から「話しやすい先生」と言ってもらえるようになりました。
ここでは、かつて“コミュ障理学療法士”だった私が、どうやって苦手を克服してきたのか――リアルな体験談としてお伝えします。
「人間関係に疲れたときは、【転職で環境を変える】という選択もあります。」
新人時代に苦労したエピソード
私は回復期病棟に配属された新人理学療法士でした。
1年目は「18単位をこなすこと」「ミスをしないこと」で頭がいっぱい。
患者さんに声をかけるときも、
「今から歩行訓練します」
「ではベッドに戻ります」
と、“業務報告のような会話”しかできませんでした。
患者さんが笑わない。沈黙が続く。
それが怖くて、ますます話しかけづらくなる悪循環。
さらに先輩に相談しようとしても、
「こんなことで聞いたら怒られそう」と思い込んでしまい、
結局、カルテ室で一人悩みを抱え込む日々でした。
そんな私を救ってくれたのは、ある60代の患者さんの一言でした。
「先生、無理にしゃべらなくていいよ。あなたの丁寧なリハビリが安心するから。」
その瞬間、「話せない=ダメではない」と気づきました。
“言葉の多さではなく、相手への誠実さが信頼を生む”という原点を教えてもらったのです。
先輩や患者さんとの関係改善のきっかけ
きっかけは、“話そう”から“聴こう”への意識転換でした。
① 聴く姿勢を変えた
以前は「何を話せばいいか」ばかり考えていました。
でも、「相手の言葉を最後まで聴く」ことを意識した途端、
患者さんがどんどん話してくれるようになりました。
たとえば、
「今日の調子どうですか?」の後に、
相手が答えた内容をオウム返し+共感するだけで会話が広がります。
患者:「今日はちょっと膝が痛くて…」
自分:「膝の痛みが出てるんですね。昨日より強いですか?」
“質問”ではなく“共感”で返す。
それだけで相手の心が開くことを実感しました。
② 先輩に「相談ではなく共有」を意識
「相談=迷惑をかける」と思っていた私でしたが、
“共有”という形に変えると、驚くほど反応が良くなりました。
「〇〇さんの歩行、少しふらつきがあるんですけど、〇〇な理由かもしれません」
→ “考えたうえで意見を求める”形にすると、上司も建設的に答えてくれます。

これにより、コミュニケーションが「上下関係」ではなく「チーム連携」に変わりました。
今だから言える、当時の自分へのアドバイス
新人時代の私に、今の自分が言えることがあるとすれば――それは、
「完璧に話そうとしなくていい」
ということです。
患者さんも先輩も、理学療法士に“トーク力”を求めているわけではありません。
誠実さ、観察力、丁寧な対応。

それが伝われば、十分コミュニケーションは成立します。
こんな考え方を持っていれば楽になる
| 不安な考え方 | 置き換える考え方 |
|---|---|
| 話が続かない=向いてない | 無理に続けなくていい。「聴く力」も立派なスキル |
| 先輩が怖い | 怒られても“自分を育ててくれる人”と捉える |
| 雑談が苦手 | 雑談=信頼を作る練習の場。1分で十分 |
また、“無理に自分を変えようとしない”ことも大切です。
私は「明るい人」になろうと頑張って失敗しました。
結局、“静かで落ち着いた理学療法士”という自分の強みに気づいたときから、職場での人間関係が一気に楽になりました。
いま、この記事を読んでいるあなたがもし「自分はコミュ障かもしれない」と感じているなら――

それは“自分の課題にちゃんと気づけている”という大きな成長の証です。
焦らず、一歩ずつ「聴く・共有する・自分らしく振る舞う」を積み重ねていけば、
必ず現場で信頼される理学療法士になれます。
あなたの“静かな誠実さ”は、必ず患者さんにもチームにも伝わっていきます。
理学療法士が「コミュ障」で悩むあなたへ伝えたいこと
理学療法士という職業は、人と関わることが多いため、「コミュニケーションが苦手=向いていないのでは」と感じやすい仕事です。
しかし実際には、“コミュ障”に悩む理学療法士ほど、相手を思いやる繊細さや誠実さを持っている人が多いのです。

ここでは、悩んでいるあなたに伝えたい“心構え”と“現場で使える小さな工夫”をまとめます。
無理に変わる必要はない
まず一番伝えたいのは、「無理に明るくなろうとしなくていい」ということです。
理学療法士として大切なのは、派手なコミュ力ではなく、信頼される安心感と誠実さです。
「会話が苦手だから」と引け目を感じる必要はありません。
大切なのは、あなたらしい関わり方を見つけること。
たとえばこんなスタイルでも十分です
- 口数は少なくても、「一言一言を丁寧に伝える」
- 雑談は苦手でも、「相手の話を最後まで聞く」
- 表情が硬くても、「落ち着いた声とペースで安心感を与える」
患者さんは、“自分をきちんと見てくれるセラピスト”を信頼します。
それは、必ずしも“話がうまい人”ではありません。
むしろ、静かで真面目なタイプの理学療法士の方が、
高齢患者やリハビリに不安を抱く人にとっては“安心できる存在”になることも多いのです。
小さな工夫で働きやすさは大きく変わる
「コミュ障だから仕方ない」――そう諦めるのは早いです。
ほんの少しの工夫で、職場での居心地も仕事のしやすさも劇的に変わります。
① 会話を“準備”しておく
- 出勤前に「今日話す一言」を決めておく(例:「昨日の運動の効果、どうでしたか?」)
- 話すことに困ったときは、「昨日より〇〇ですね」など観察ベースのコメントを使う
② “話す”より“共有する”を意識
先輩や上司には「相談」より「情報共有」の形で話しかけるとプレッシャーが減ります。
例:「〇〇さんの歩行が少し不安定だったので、次回見ていただけますか?」
③ 苦手な人とは「距離の保ち方」を学ぶ
すべての人と仲良くなる必要はありません。
業務で必要なやり取りを丁寧にこなすだけで十分です。
無理に合わせようとすると、ストレスで燃え尽きてしまいます。
④ 自分の得意分野で信頼を積む
コミュニケーション以外でも信頼は築けます。
- 技術面で成果を出す
- 患者対応で一貫した丁寧さを保つ
- 報連相や記録を正確に行う
そうした“目に見える誠実さ”が、周囲との関係を自然と良くしてくれます。
まとめ:理学療法士が「コミュ障」で悩むあなたへ伝えたいこと
理学療法士として働く上で、「コミュ障かもしれない」と悩む人は決して少なくありません。
しかし、コミュニケーションに苦手意識があるからといって、“向いていない”わけではありません。

大切なのは、自分の特性を理解し、無理のない形で信頼関係を築くことです。
以下に、今回の記事の重要ポイントを整理します。
1.理学療法士がコミュニケーションに悩むのは「普通」
- 「患者と話すのが苦手」「雑談が続かない」と感じる人は多い。
- 話し上手よりも、“聴き上手”の方が臨床では信頼されやすい。
- コミュ障の人ほど、相手を思いやる誠実さが強みになる。
2.無理に「明るく」なろうとしなくていい
- 無理なキャラ変更は長続きせず、ストレスになる。
- 落ち着いたトーンや丁寧な説明で“安心感”を与えることができる。
- 「沈黙が怖い」よりも、「沈黙を共有できる安心感」を意識しよう。
3.小さな工夫で職場の人間関係は変えられる
- 挨拶やお礼を“習慣化”するだけでも印象が良くなる。
- 雑談が苦手なら、仕事ベースの話題(患者・症例・研修など)で十分。
- 上司・先輩への相談は「質問」ではなく「共有」として伝えるとスムーズ。
- 会話に自信がなくても、報連相や記録の正確さで信頼を得られる。
4.苦手な人と無理に仲良くしなくてもいい
- 全員と仲良くなる必要はない。
- 距離を保ちながらも、業務上の関係を丁寧にこなせば問題ない。
- 無理に関係を作ろうとして疲弊するより、“誠実な対応”を徹底しよう。
5.コミュニケーション力=「伝える力」より「伝わる力」
- 上手に話すよりも、“相手がどう感じるか”を意識することが大切。
- 患者の表情・言葉・反応を観察して、共感の言葉を返す。
- 「うまく話せない」ではなく、「丁寧に伝えよう」と意識を変える。
6.自分を責めず、「自分らしさ」を伸ばす
- コミュ障を“欠点”ではなく、“個性”として捉える。
- 一人ひとりに合った関わり方ができることが、PTとしての価値。
- 自分のペースでいい。焦らず、少しずつ信頼を積み重ねていけばOK。