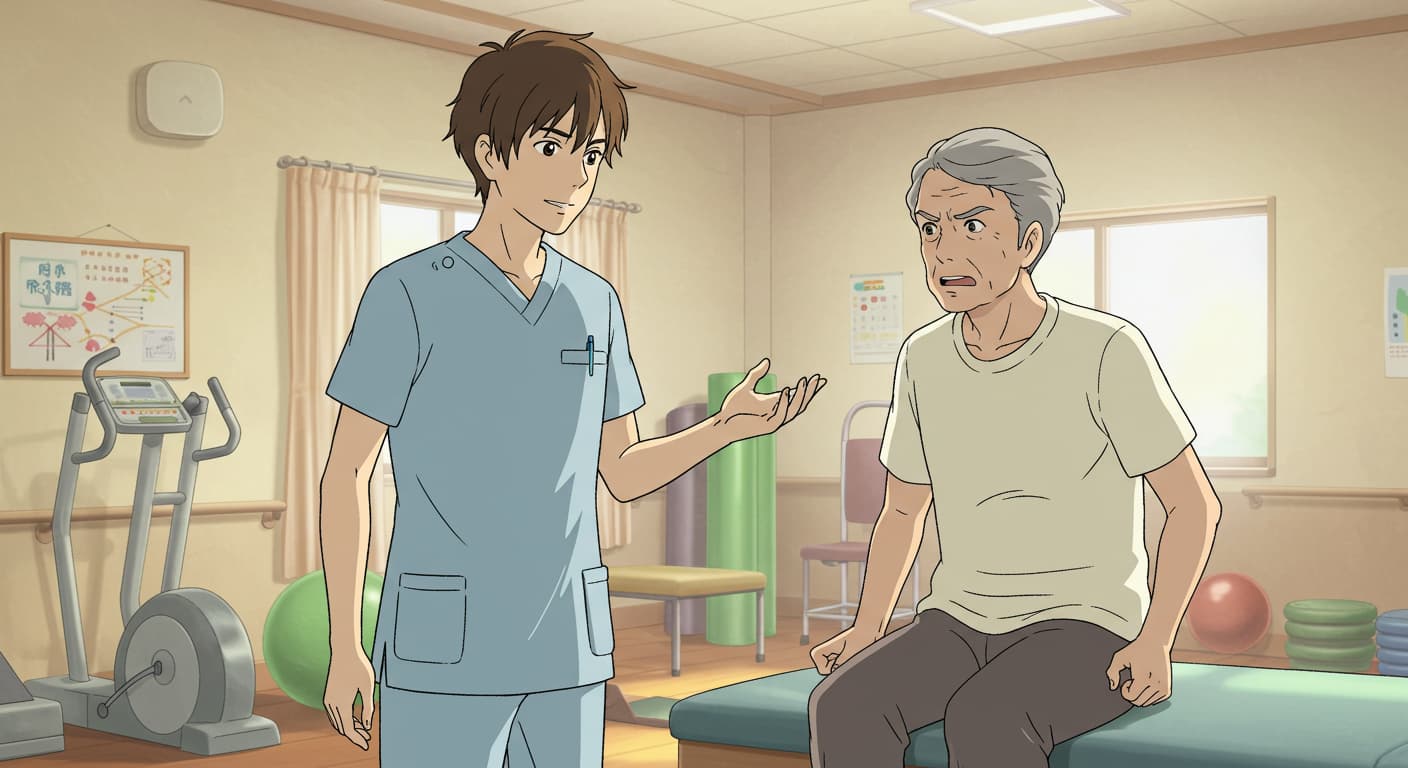患者さんから「担当を変えてほしい」と言われた瞬間、頭が真っ白になりませんでしたか?
「自分は理学療法士に向いていないのかもしれない」
「もうこの仕事を続ける自信がない」

そう感じているあなたに、まず伝えたいことがあります。
担当変更=あなたの価値が低い、という意味ではありません。
むしろこの出来事は、多くの理学療法士が一度は通る“成長の入り口”です。
ポイント
なぜ患者は担当変更を希望するのか。本当の理由は何なのか。そして、そこから何を学び、どう立て直せばいいのか。
その答えを、現場目線でわかりやすく解説していきます。
Contents
患者に「担当を変えてほしい」と言われるのは珍しくない?現状と実態
患者さんから突然、
「担当を変えてもらえますか?」
と言われたとき、多くの理学療法士は大きなショックを受けます。
「自分の何が悪かったんだろう…」
「もうPT向いてないのかも…」

こうした不安が一気に押し寄せるのは自然な反応です。
しかし結論から言うと、担当変更を希望されること自体は、決して珍しい出来事ではありません。
まずは現状と実態を正しく知ることで、
必要以上に自分を責めない視点を持ちましょう。
「担当制がきつくなる背景には、単位ノルマの存在が大きく影響しています」
理学療法士の約○割が経験する現象
正確な全国統計は存在しませんが、
複数の転職エージェントや現場アンケートでは、
「一度は患者から担当変更を希望された経験がある」
と答える理学療法士は6〜7割前後にのぼると言われています。
特に以下の環境では起こりやすい傾向があります。
- 回復期・療養病棟
- 高齢患者が多い施設
- 長期入院・長期通所
つまり、
担当変更=珍しいトラブルではなく、
臨床を続けていれば誰でも起こり得る出来事なのです。

新人・中堅・ベテラン関係なく発生します。
「言われた=自分だけがダメ」ではありません。
患者側が感じる不満のよくあるパターン
患者が抱く不満は、必ずしも「技術不足」とは限りません。
① 説明が少ない・分かりにくい
- 何の練習をしているのか分からない
- 良くなっている実感がない
② 話を聞いてもらえていない感覚
- 痛みの訴えを軽く流された気がする
- 雑に扱われていると感じる
③ 期待とのズレ
- もっとマッサージしてほしい
- もっと厳しくやってほしい
④ 相性の問題
- 話しやすい・話しにくい
- 性格が合わない
重要なのは、
不満=あなたの人格や能力を否定しているわけではない
という点です。

多くは「期待とのミスマッチ」です。
担当変更を希望する患者の心理的背景
患者さん側にも、さまざまな心理があります。
① 不安のはけ口を探している
病気や障害そのものへの不安が、
担当セラピストへの不満として表出するケースです。
② 誰かのせいにしたい
思うように回復しない苛立ちを、
無意識に担当者に向けてしまいます。
③ 「変えれば良くなるかも」という期待
担当を変えることで状況が好転すると信じています。
④ 家族からの影響
「この人より別の人がいいんじゃない?」
と家族に言われて希望するケースもあります。
つまり、
担当変更は「攻撃」ではなく「不安行動」
であることが多いのです。
患者に「変えてほしい」と言われると、どうしても自分を責めてしまいます。
しかし現実には、
✔ 多くのPTが経験している
✔ 技術以外の要因が大半
✔ 相性問題も普通に起こる
という事実があります。
まずは、
「よくある出来事のひとつ」として受け止めることが、
あなた自身を守る第一歩です。
なぜ担当を変えられたのか?よくある理由5選
患者さんから「担当を変えてほしい」と言われると、
ほとんどの理学療法士はこう考えます。
「自分の技術が足りないのでは?」
「何か大きなミスをしたのでは?」

しかし実際には、担当変更の理由はもっと複雑で多層的です。
ここでは、現場でよく見られる代表的な5つの理由を整理し、
「全部を自分の責任にしなくていい」根拠を示していきます。
「限られたリハビリ時間の中で結果を求められるのも、担当制がつらい理由です」
技術的な理由(手技や知識不足)
まず最初に思い浮かびやすいのが、
「技術が足りなかったのでは」という理由です。
確かに、以下のようなケースでは技術面が関係することがあります。
- 痛みがなかなか改善しない
- 変化が実感できない
- 説明が曖昧だった
ただし、ここで重要なのは、
患者が評価しているのは“臨床能力の正確さ”ではなく“体感”
という点です。
つまり、
- 理論的には適切な介入
- 教科書的には正解
であっても、
「良くなっている気がしない」
と感じれば、不満につながります。

さらに、患者は複数のセラピストを比較することがあります。
- 前の担当者はマッサージが多かった
- 別のPTは運動が多かった
この“好みの違い”が、
「今の担当は合わない」という評価になるケースも多いです。
つまり、
技術不足=担当変更とは限らない
ということです。
コミュニケーションの問題(態度や表現がきつい etc.)
担当変更の理由として、
実は技術以上に多いのがコミュニケーション要因です。
よくある例
- 説明が少ない
- 専門用語が多い
- 忙しそうで話しかけづらい
- 無表情に見える
本人に悪気はなくても、
患者側はこう受け取ることがあります。
「冷たい」
「話を聞いてくれない」
また、指導的な口調が、
「上から目線」
「きつい」
と受け取られることもあります。
ここで知っておいてほしいのは、
コミュニケーションのズレは“相性”の問題が大きい
ということです。
同じ話し方でも、
- 合う患者
- 合わない患者
が必ず存在します。

あなたの人間性が否定されたわけではありません。
性格や相性の問題(好みや価値観の不一致)
最もどうしようもない理由が、
相性です。
例えば、
- 雑談が好きな患者 × 寡黙なPT
- 厳しくしてほしい患者 × 優しいPT
- 理屈派の患者 × 感覚派のPT
どちらが正しい・間違いではありません。
ただ「合わない」だけです。
これは恋愛や人間関係と同じで、
努力しても埋まらない溝が存在します。
にもかかわらず、
「自分の努力不足だ」
「もっと頑張ればよかった」
と背負い込んでしまうPTはとても多いです。

相性が理由の場合、担当変更はむしろ合理的な判断です。
あなたの価値が下がったわけではありません。
患者の事情(同性を希望・家族の意向など)
患者さんの個人的事情による担当変更もよくあります。
よくあるケース
- 同性のセラピストがいい
- 年齢が近い人がいい
- 家族が「別の人がいい」と言った

この場合、あなたの対応とは無関係です。
それでも、現場では
「クレーム」
「問題があった」
のような扱いになることがあり、
PT側が必要以上に落ち込みます。
しかし実態は、
生活歴・価値観の違いによる選好
に過ぎません。
ここを混同しないことが重要です。
職場の都合(シフトや効率化)
患者発信に見えて、
実は職場都合であるケースもあります。
例
- 担当数の調整
- 新人教育目的
- 稼働率の調整
表向きは、
「患者さんが変えたいと言っている」
と伝えられても、
実際は上層部判断ということも少なくありません。
この場合、
あなたの評価とは無関係
です。
ここまでの5つをまとめると、
- 純粋な技術不足が原因のケースは一部
- 多くはコミュニケーション・相性・患者事情
- 中には職場都合もある
という構造です。
つまり、
担当を変えられた=あなたの価値が低い
ではありません。
むしろ、
臨床をしていれば誰でも一度は通る道
です。

この前提を知っているだけで、自責思考はかなり軽くなります。
担当変更を告げられた時のベストな対応法
患者さんから「担当を変えてほしい」と告げられた瞬間、
頭が真っ白になったり、胸がギュッと苦しくなったりするのは当然です。
多くの理学療法士がこの場面で、
- 動揺してうまく返事ができない
- 必要以上に謝ってしまう
- 自分を強く責めてしまう
といった反応を経験しています。
ここでは、感情に振り回されず、自分を守りながら対応するための現実的な方法を解説します。
「担当がうまくいかないと、自分が悪いと感じてしまう人も多いです」
ショックを受けても感情的にならない
まず大前提として、
ショックを受けること自体は正常
です。
問題になるのは、そのショックのまま
- 言い訳する
- 言い返す
- 落ち込みすぎる
といった行動を取ってしまうことです。
おすすめの初期リアクション
- 「そうなんですね」
- 「教えてくださってありがとうございます」
まずはこれだけで十分です。
無理にその場で解決しようとしなくてOKです。

感情の処理はあとでやるものと割り切りましょう。
まずは理由を冷静に聞く姿勢が大切
可能であれば、
「差し支えなければ、理由を教えていただけますか?」
と穏やかに確認します。
ここでのポイント
- 反論しない
- 正当化しない
- 遮らない
理由が分かれば、
- 改善できること
- どうしようもないこと(相性など)
を切り分けられます。
逆に、理由を聞かずに終わると、
「何が悪かったのか分からないまま悩み続ける」
状態になります。

自分を守る意味でも、可能な範囲で理由を把握することは大切です。
謝罪が必要かどうかの見極め方
多くのPTがやってしまうのが、
条件反射での過剰な謝罪
です。
謝罪が必要なケース
- 明らかな説明不足
- 不適切な言葉遣い
- 配慮に欠ける態度
謝罪が不要なケース
- 相性の問題
- 患者の好み
- 家族の意向
謝る場合も、
「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」
程度で十分です。
必要以上に
「全部私のせいです」
と言う必要はありません。

それは事実ではないことが多いからです。
患者が安心できる言葉のかけ方・態度
大切なのは、
患者の選択を尊重する姿勢
です。
使いやすいフレーズ
- 「より合う担当者が見つかるといいですね」
- 「引き継ぎはしっかり行います」
こうした言葉があるだけで、患者は
「揉めずに済んだ」
「嫌なことを言ってしまった」という罪悪感
を抱きにくくなります。

結果的に、トラブル化を防げます。
上司や同僚への報告と相談のポイント
担当変更があった場合、
一人で抱え込まないことが重要です。
報告内容の例
- 患者から担当変更の希望があった
- 理由(分かる範囲で)
- 自分なりの振り返り
ここで大切なのは、
自分を過度に責めるトーンで話さないこと
です。
「相性の問題もありそうです」
「患者の希望です」
と事実ベースで伝えましょう。
また、可能であれば
- 先輩の経験談
- 同じケースの対応例
を聞いてみてください。
多くの場合、
「私も昔あったよ」
という話が返ってきます。
担当変更を告げられたときに最も大切なのは、
✔ 感情的にならない
✔ 必要以上に背負わない
✔ 一人で抱え込まない
この3つです。
冷静に対応できた時点で、
あなたはすでにプロとして十分な対応をしています。
担当を変えられた後にやるべき3つのこと
患者さんから担当変更を告げられたあと、多くの理学療法士はこう感じます。
「もう患者対応が怖い」
「次に同じことが起きたらどうしよう」
この状態のまま放置すると、
- 自信を失う
- 患者との距離が縮まらなくなる
- 仕事そのものがしんどくなる
という悪循環に入ってしまいます。

大切なのは、「終わった出来事」を「次につながる材料」に変えることです。
ここでは、担当変更後にやるべき3つの行動を具体的に解説します。
「患者・家族とのコミュニケーション負担が大きくなるのも担当制の特徴です」
自分の課題を振り返り改善する
まず行いたいのは、
感情ではなく事実ベースでの振り返りです。
振り返りのポイント
- 説明は十分だったか
- 患者の話を最後まで聞いていたか
- 忙しさが態度に出ていなかったか
ここで重要なのは、
「全部自分が悪い前提」で考えないこと
です。
あくまで、
- 改善できそうな点があれば拾う
- 相性や患者事情だった可能性は切り離す
というスタンスが大切です。
よくある改善ポイント
- 介入の目的を最初に説明する
- セッションの最後に「今日のまとめ」を伝える
- 痛み・不安を一言拾う
大きな変化は不要です。

小さな1つの行動修正で十分です。
「自分には改善できる部分があった」と思えるだけで、
無力感はかなり軽減します。
信頼を取り戻すためにできる努力
「もう信用されないのでは…」
と感じる人も多いですが、
1人の患者との出来事=職場全体での評価
ではありません。
むしろ、ここからの姿勢が大切です。
意識したい行動
- 挨拶を丁寧にする
- 患者の名前を呼ぶ
- 報連相をいつもより意識する
特別なスキルアップよりも、
基本動作の質が信頼につながります。
また、先輩や同僚に
「〇〇の対応で何か気になる点あれば教えてください」
と聞いてみるのも有効です。
多くの場合、
「特に問題ないと思うよ」
と言われます。

この一言だけでも、気持ちはかなり楽になります。
心のケア(メンタルを保つための考え方)
担当変更後に一番ダメージを受けるのは、
実は技術面よりメンタルです。
ここを放置すると、
転職を考えるほど追い込まれることもあります。
持っておきたい考え方
- 臨床をしていれば誰でも一度は経験する
- 相性問題は努力で解決できない
- 1件で自分の価値は決まらない
特に大切なのは、
「100人中1人合わない人がいるのは普通」
という視点です。
全員に好かれるPTは存在しません。
また、こんな問いかけも有効です。
「もし後輩が同じことを言われたら、何て声をかけるか?」
おそらく、
「気にしなくていいよ」
「誰でもあるよ」
と言うはずです。

その言葉を、自分自身にも向けてあげてください。
担当を変えられた後に大切なのは、
- 必要な振り返りだけする
- 基本行動を丁寧にする
- 自分を過剰に責めない
この3つです。
この経験は、
あなたをダメにする出来事ではなく、
臨床家として一段成長するきっかけになります。
担当変更を防ぐためにできる5つの予防策
患者さんから「担当を変えてほしい」と言われる経験は、
どれだけ気をつけていてもゼロにはできません。
しかし一方で、起こる確率を下げることは十分可能です。
ここでは、現場で実践しやすく、
かつ「明日から意識できるレベル」の予防策を5つ紹介します。
「もう二度と同じ思いをしたくない…」

そう感じている方は、ぜひ1つずつ取り入れてみてください。
「担当制が合わない場合、職場を変えるという選択も現実的です」
患者に寄り添うコミュニケーションを磨く
担当変更の原因で最も多いのは、
技術よりもコミュニケーションです。
難しいスキルは必要ありません。
意識するだけで変わるポイント
- 患者の話を最後まで遮らない
- 「そうなんですね」と一度受け止める
- 感情に名前をつける
例
「痛いです」
→「痛みが続いていて不安ですよね」
この一言があるだけで、
患者は「分かってもらえた」と感じます。

問題解決より先に、共感を置くことが大切です。
共感 → 説明 → 介入
この順番を意識するだけで、
不満はかなり減ります。
リハビリ計画を患者と共有する工夫
患者が不満を感じやすい理由の一つが、
「何をしているのか分からない」
状態です。
おすすめの習慣
- 開始時に今日の目的を伝える
- 終了時に成果を一言まとめる
例
開始時:
「今日は歩くときのふらつきを減らす練習をします」
終了時:
「さっきより足が前に出やすくなりましたね」
これだけで、患者は
「意味のある時間だった」
と感じやすくなります。
変化が小さい日でも、
「今日は評価の日です」
「今日は体調確認メインです」
と伝えるだけでOKです。

沈黙のまま進めることが、一番不安を生みます。
表情・態度・言葉遣いに注意する
自分では普通のつもりでも、
- 無表情
- 早口
- 事務的
に見えていることがあります。
最低限意識したい3点
- 入室時に一度アイコンタクト
- 語尾を柔らかくする
- 退出時に一言声かけ
例
×「立ちます」
○「立ちますね」
たった「ね」をつけるだけで、
印象は大きく変わります。
また、忙しいときほど、
ゆっくり話す
を意識してください。
早口=冷たい
という印象を持たれやすいからです。
相性の見極めと他スタッフとの連携
どんなに気をつけても、
相性が合わないケースはあります。
重要なのは、
悪化する前に察知すること
です。
サイン
- 返事がそっけない
- 目を合わせない
- 訴えが増える
こうした変化を感じたら、
「最近リハビリどうですか?」
と軽く聞いてみましょう。
それでも改善しない場合は、
- 先輩に同席してもらう
- 他PTの意見を聞く
など、早めに連携します。

「自分で抱え込まない」ことが、結果的に担当変更を防ぎます。
定期的に自己評価とフィードバックを受ける
成長しているPTほど、
「自分はどう見られているか」
を気にしています。
おすすめ
- 月1回、先輩に相談
- 「改善点ありますか?」と聞く
ここで大事なのは、
評価を取りに行く姿勢
です。
自分から聞く人は、
「成長意欲がある人」として見られます。
また、フィードバックがあれば、
担当変更が起こる前に修正できます。
ここまでの5つをまとめると、
- 共感ベースで関わる
- リハの目的を共有する
- 印象管理を意識する
- 相性問題は早めに連携
- 第三者の目を取り入れる
これらはすべて、
技術レベルに関係なく実践できることです。
完璧を目指す必要はありません。

1つでも意識すれば、担当変更のリスクは確実に下がります。
そして何より、
あなたが悪者にならない働き方
を作ることが目的です。
【専門家視点】担当変更は必ずしも「悪いこと」ではない理由
患者さんから「担当を変えてほしい」と言われたとき、多くの理学療法士がまず感じるのは、
「自分はダメなPTなのでは…」
「もう信頼を失ったのでは…」
という強い自己否定です。
しかし、専門家の視点で見ると、
担当変更は必ずしもネガティブな出来事ではありません。
むしろ、
- 患者にとっての最適化
- あなた自身の成長機会
- 組織全体の調整
という前向きな意味を持つことも多いのです。
ここでは「担当変更=失敗」という思い込みを壊し、
視点を切り替えるための考え方をお伝えします。
患者がよりよいリハビリを受けるための選択
まず大前提として、
患者が担当変更を希望する最大の目的は「回復すること」
です。
決して、
「あなたを傷つけたい」
「あなたを評価して落としたい」
わけではありません。
患者視点で考えると
- 話しやすい人がいい
- 説明の仕方が合う人がいい
- 安心できる人がいい
という、極めてシンプルな欲求です。
これはレストランで、
「この店員さん苦手だから別の人にしてほしい」
と言う感覚と近いものです。

能力の否定というより、相性の問題であるケースが大半です。
専門家視点の本音
もし患者があなたと合わず、
別のPTとなら前向きにリハビリに取り組めるなら、
それは「良い担当変更」です。
患者の意欲が上がる → 実施量が増える → 予後が良くなる
という好循環が生まれます。
つまり担当変更は、
患者のアウトカムを最大化するための調整
とも言えます。
「自分が切られた」と捉えるのではなく、
「患者にとって最適な選択がされた」
と考えてみてください。
新しい学びや成長のチャンスになる
担当変更は、
心理的にはかなりキツい出来事です。
ですが、同時に
強制的なフィードバック
でもあります。
成長につながるポイント
- 説明の仕方は分かりやすかったか
- 共感が足りなかったか
- 距離感が近すぎた/遠すぎたか
こうした振り返りは、
順調なときにはなかなかしません。

人は基本的に、失敗したときにしか本気で考えないからです。
臨床家としての現実
ベテランPTでも、
若手でも、
担当変更を一度も経験していない人はほぼ存在しません。
経験値の高いPTほど、
「ああ、あの頃はこういう理由で変えられたな」
というエピソードを複数持っています。
それは、
失敗 → 修正 → 定着
を繰り返してきた証拠です。
今回の経験は、

あなたのPTキャリアの中で、確実に「糧」になります。
組織全体の効率化や最適化の一環
現場では、
担当変更が個人の問題ではないケースも多々あります。
よくある背景
- 患者層の偏り
- スタッフの得意分野
- シフト・人員配置の都合
- クレーム予防
例えば、
認知症対応が得意なPT
整形疾患が得意なPT
など、
暗黙の役割分担が存在します。
患者側の希望をきっかけに、
「この人の方が合いそうだな」
と管理者が判断するケースもあります。
管理者の視点
管理者が重視しているのは、

誰が傷つくかではなく、現場が回るかどうかです。
・クレームが減る
・スタッフのストレスが減る
・患者満足度が上がる
これらを総合的に見て、
担当変更が選択されます。
つまり、
構造上の調整
である場合も多いのです。
「担当変更=評価」ではない
多くのPTが勘違いしがちですが、
担当変更=能力評価
ではありません。
もし本当に能力不足であれば、
- 指導が入る
- 面談がある
- 教育プランが組まれる
など、
別の形でフィードバックが行われます。
担当変更だけで終わる場合、

多くは相性か調整です。
転職を考えている人へ伝えたいこと
もしあなたが今、
「変えてほしいと言われた自分は、どこへ行っても通用しないのでは」
と感じているなら、
それは事実ではありません。
職場が変われば、
- 患者層
- 求められる役割
- 文化
は大きく変わります。
今の職場で合わなかっただけで、
別の環境では評価されるPT
になるケースは非常に多いです。
まとめとして伝えたいこと
- 担当変更は患者最適化の結果
- あなたの人格や価値を否定していない
- 成長材料として使える
- 組織的な調整の場合も多い
担当を変えられた経験は、
「キャリアの汚点」ではなく、
臨床家として成熟していく過程の1ページ
です。
「担当制が原因で限界を感じたら、一度立ち止まることも必要です」
まとめ
患者さんから「担当を変えてほしい」と言われると、
多くの理学療法士は「自分はダメなPTなのではないか」「評価が下がったのではないか」と強いショックを受けます。
しかし専門家の視点で見ると、担当変更は必ずしもネガティブな出来事ではありません。
患者・理学療法士本人・組織の三者それぞれにとって、前向きな意味を持つケースも多く存在します。
- 担当変更の最大の目的は、患者がより良いリハビリを受けるための調整である
- 多くの場合、能力の否定ではなく相性の問題である
- 患者の意欲が上がることで、リハビリ効果が高まる可能性がある
- 担当変更は臨床家として成長するためのフィードバックになる
- ベテランPTでも担当変更を経験している人は珍しくない
- 失敗経験は「修正→改善→定着」のサイクルを回す材料になる
- 現場では個人評価ではなく、人員配置や役割分担の調整として行われることも多い
- 担当変更だけで「能力不足」と判断されることは基本的にない
- 本当に問題があれば、指導・面談・教育など別の形でフィードバックがある
- 今の職場で合わなくても、環境が変われば評価されるケースは多い
担当を変えられた経験は、あなたの価値を否定するものではありません。

むしろ、臨床家として視野を広げ、引き出しを増やすための通過点です。
「自分は向いていない」と決めつけるのではなく、
「何を学べるか」「次にどう活かすか」という視点で捉えることが、
今後のキャリアを大きく左右します。
この経験を、より良い理学療法士になるための材料として活かしていきましょう。