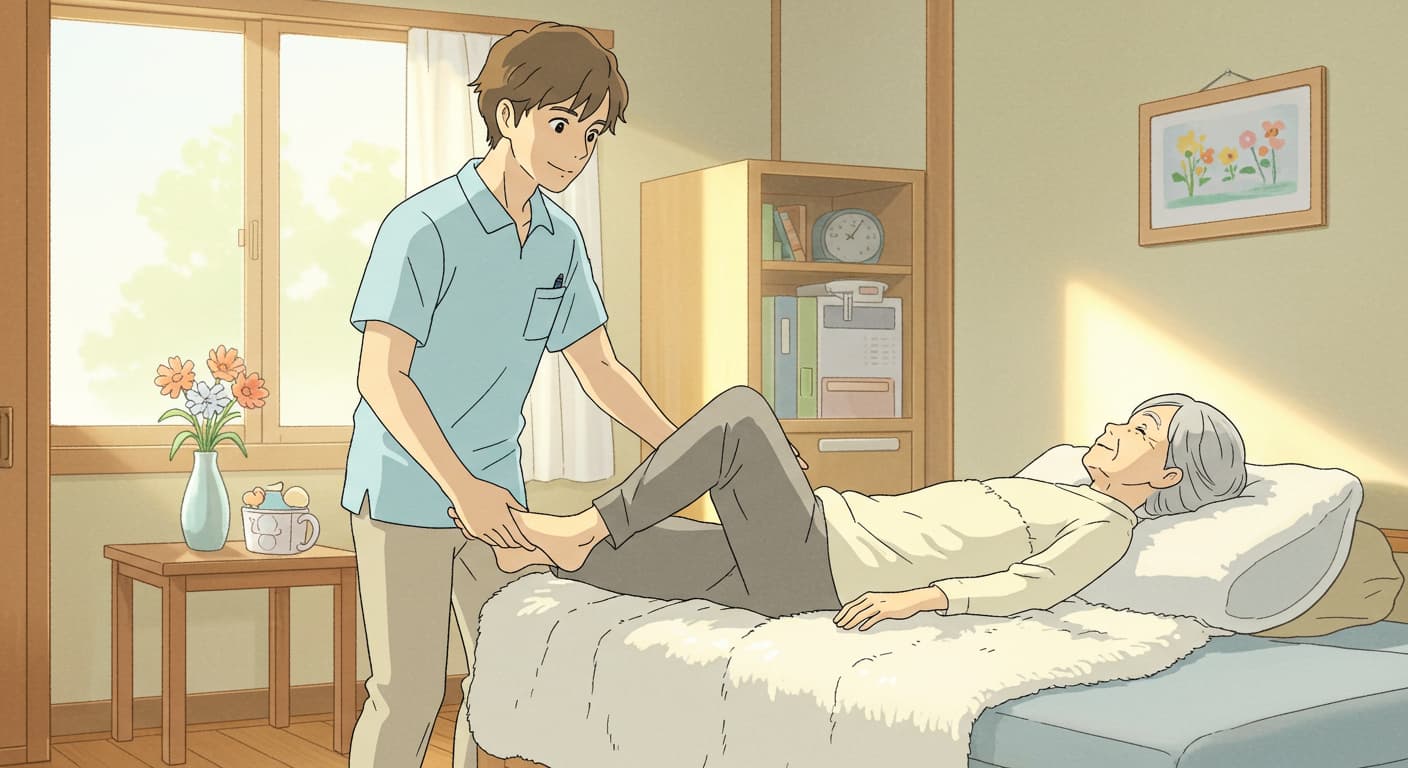「訪問リハビリって将来性があるって聞くけど…本当のところどうなの?」
多くのPTが気になっていながら、誰もはっきり語ろうとしない“業界の裏側”。
給料は高いのに離職率が高いと言われる理由。成功する事業所と、すぐ崩れる事業所の決定的な違い。そして現場で本当に評価されるPTは、どんなスキルを持っているのか——。
これらは、求人票や公式サイトには絶対に書かれていない“リアル”です。
ポイント
もしあなたが、「このまま病院で働き続けて大丈夫だろうか…」「訪問に興味はあるけど失敗したくない」そんな不安を抱えているなら、この記事はまさにあなたのための内容です。

ここでしか読めない訪問リハビリの本音と未来予測。
続きを読むことで、あなたのキャリアの迷いが一気に晴れます。
Contents
訪問リハビリの現状と需要の背景
「訪問リハビリは将来性があるのか?」
「この先、病院から訪問へキャリアの軸を移しても大丈夫?」
実際、訪問リハは数ある働き方の中でも、将来性・安定性・需要の伸び率が抜群に高い領域です。
しかし、世の中に出ている情報は「高齢化が進むから需要が増える」という表面的なものばかりで、“なぜ訪問リハがこれほどまでに求められているのか”まで深掘りされた記事はほとんどありません。
この記事では、国の方針・社会構造・市場拡大のデータをもとに、訪問リハの将来性を徹底解説。

「この先、訪問リハにキャリアチェンジしても大丈夫か?」という疑問に、本気でお答えします。
「訪問リハの給料や単位の仕組みについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。」
高齢化社会と訪問リハビリの役割
まず大前提として、訪問リハの需要が伸び続けている最大の理由は、日本が世界でも例を見ないスピードで高齢化しているからです。
▶日本は世界一の高齢化社会へ
- 2025年:団塊の世代が全員75歳以上へ
- 2040年:高齢化率は約35%へ
- 2050年:国民の3人に1人が後期高齢者になる予測
これらの変化は、生活機能が低下した高齢者が増えることを意味します。
その結果、「病院で治す」から「自宅で支える」へ医療・介護の軸が大きくシフトしました。

ここで必要になるのが、在宅で専門的な介入ができる訪問リハビリ職です。
▶訪問リハの役割は「生活の再構築」
病院でのリハビリはあくまで医療モデルですが、訪問リハは生活モデルです。
- 家の中で転倒しないような動線づくり
- 生活の自立度を最大化する環境調整
- 家族への介助方法の指導
- 福祉用具・住環境の最適化
本人の生活がそのままリハビリの場になるため、病院では出来ない領域をカバーできるのが訪問リハの強みです。
訪問リハビリが選ばれる理由(利用者目線・国の方針)
訪問リハが急速に普及しているのは、高齢化だけが理由ではありません。利用者・家族・国(行政)の三者が「訪問リハを必要としている」という珍しい構図があるからです。
▶① 利用者・家族にとってのメリット
- 病院に通う負担がゼロ(送迎の必要なし)
- 生活に合わせた実践的なリハビリが受けられる
- 家族へのケア方法をその場で指導してもらえる
- 病院よりも密度の高いマンツーマンの介入
つまり、訪問リハは利用者満足度が高いサービスなのです。
▶② 国の政策が「在宅医療」を後押ししている
国は以下の理由から、訪問リハを強く推進しています。
- 病院や施設に高齢者を収容する時代は限界
- 在宅医療のほうが医療費を抑えられる
- 住み慣れた家で最期まで生活するという国の理念
厚生労働省の資料でも、「今後は在宅医療中心の体制へ」と明言されています。
実際、訪問看護ステーション・訪問リハの配置基準緩和や加算の見直しが進んでおり、需要が伸びるのは国が仕組みとして誘導していると言っても過言ではありません。
▶③ 施設リハでカバーできない領域を補完している
施設(デイケア・老健・通所リハ)は 「通える人」しか利用できません。
一方で訪問リハは、
- 寝たきりの方
- 重度の障害がある方
- 退院直後の不安定な方
こうした“通えない層”を支えることができます。

だからこそ、訪問リハは社会に不可欠な存在なのです。
現在の市場規模と成長率のデータ
訪問リハの「将来性」を客観的に知るには、市場規模と成長率のデータを理解する必要があります。
▶訪問看護・訪問リハ市場は右肩上がり
- 訪問看護ステーション数:10年前の約2倍に増加
- 訪問リハ利用者数:年々増加し続けている
- 在宅医療市場の規模:2030年にかけて拡大予測
このデータが示しているのは、「需要は確実に増え、供給が不足している」ということ。
▶理学療法士は“訪問に移るだけで”市場価値が上がる
病院だけにキャリアを置くPTは飽和状態ですが、 訪問リハ領域は明らかに人材不足です。
そのため、訪問経験があるPTは、
- 採用されやすい
- 収入が高くなりやすい
- 将来のキャリアの幅が広がる
という利点があります。
▶今後も給料が下がりにくい構造
訪問は医療モデルよりも利益率が高いため、「需要↑」「人材↓」→ 給料は高止まりしやすいという市場原理が働きます。

訪問リハは、現在も将来も安定して成長し続ける領域です。
病院や施設のキャリアに不安を感じているPTにとって、“最も将来性のある働き方の1つ”と言えます。
訪問リハビリの将来性を左右する要因
「訪問リハビリは本当に将来性があるの?」
「制度・人手不足・テクノロジーの変化に影響されないの?」

実際、訪問リハの将来性は“高齢化による需要”だけでは語り尽くせません。
訪問リハの未来を左右する要因は、制度・採用市場・テクノロジーという3つの大きな軸で決まります。
この記事では、これらの変化が訪問リハにどんな影響を与えるのか、PTのキャリアに直結する視点で深掘りしていきます。
「“訪問リハは休みにくい”と言われる理由はこちらの記事で詳しく紹介しています。」
介護保険・医療保険制度の動向
訪問リハビリの将来を考えるうえで最も重要なのが、介護保険と医療保険の制度改定です。
制度によって報酬(=収益)が決まるため、 訪問リハの働きやすさ・給与水準にも直接影響します。
▶① 国は「在宅医療・在宅介護」へ全力でシフトしている
厚労省は以下の方針を明確に掲げています。
- 病床削減(病院を縮小し、在宅へ誘導)
- 地域包括ケアシステムの強化
- 「可能な限り住み慣れた地域で生活」政策の推進
この流れは今後も変わらず、むしろ加速することが確実です。
結果として、訪問リハは今後も国の後押しを受け続ける領域と言えます。
▶② リハビリ難民の増加が訪問リハの追い風に
急性期・回復期では在院日数の短縮が進んでおり、
- 十分なリハビリを受けられないまま退院する高齢者
- 通所サービスに通えない利用者
こうした「リハビリ難民」が急増しています。
訪問リハがカバーすべき対象者が増えるため、制度への依存度はむしろ高まっていくと予想できます。
▶③ 報酬減?それとも維持?→訪問リハは安定しやすい
制度改定で報酬が上下することはありますが、訪問リハは次の理由で下がりにくい傾向があります。
- 訪問リハ対象者は重度者が多い=必要性が高い
- 在宅医療の中核を担うサービスのひとつ
- 医療費削減(入院回避)につながる
したがって、制度の方向性からすると訪問リハは中長期的に安定した収益構造が維持される可能性が高いと言えます。
人手不足と採用市場の現状
訪問リハビリの将来性を語るうえで欠かせないのが、採用市場の深刻な人手不足です。
▶① 訪問リハは「慢性的な人材不足」
訪問リハは以下の理由でPTの確保が難しい市場です。
- 病院と比べて“一人で判断”する場面が多く、敬遠されがち
- 運転が必要なことを嫌がるPTが一定数いる
- 在宅領域は経験のハードルが高いと思われている
その結果、訪問リハは供給<需要の状態がずっと続いているため、転職市場では「売り手市場」が長期化しています。
▶② 今後10年、さらに採用難が加速
高齢化が進む一方で、PTの訪問領域への流入はまだ不足しています。
つまり、
訪問ができるPTは市場価値が今後も上がる
という構造が変わらないのです。
▶③ 給与が高止まりする理由は“人手不足”
訪問リハの給与が高いのは報酬単価の高さだけではなく、人材不足で採用が難しい → 給与を上げざるを得ないという背景もあります。
訪問リハの給与水準は今後もしばらくは高止まり、 むしろ地域によっては上昇の可能性すらあります。
テクノロジーの進化が与える影響(AIやロボットの導入)
最後に、多くのPTが気になっているテーマ:「AIに仕事を奪われるのか?」
訪問リハは、テクノロジーの導入で大きく変化する分野です。 しかし、その変化は脅威ではなくむしろ“追い風”になる可能性があります。
▶① AI・ICTは「作業負担の軽減」に役立つ
- 電子カルテの自動入力
- 音声入力による記録の効率化
- 訪問ルートの自動最適化
- 申し送り・情報共有のDX化
訪問リハでは移動が多く書類が負担になりがちですが、 AIの導入で作業時間の短縮と生産性向上が期待できます。
▶② ロボットリハの導入は「訪問リハの補完」
ロボットアシストや歩行補助デバイスが増えていますが、 これは訪問リハの仕事を奪うものではありません。
むしろ、
- 自宅での訓練の幅を広げる
- 家族の介助負担を軽減する
- PTの専門性をより活かせる
訪問リハを強化するツールとして活用される可能性が高いです。
▶③ AIが代替できない“訪問ならではの価値”
訪問リハは単なる機能訓練ではなく、生活動作・環境・家族全部を含めた総合的支援です。
AIやロボットは身体機能の支援はできても、
- 家族間の関係性を調整する
- 利用者の生活背景を理解する
- 家の中の動線を見て生活を再構築する
- 本人の心理・不安を汲み取る
といった“人間的支援”はできません。
つまり、訪問リハの仕事はAIによって縮小するのではなく、より高度な専門性が求められる職域へ進化すると考えられます。

訪問リハビリの将来性は、制度・採用市場・テクノロジーの3軸で見ても、 非常に強く、安定しています。
病院のキャリアに行き詰まりを感じているPTにとって、訪問は“未来が開ける働き方”と言えるでしょう。
訪問リハビリは本当に安定した職業なのか?
「訪問リハビリって将来性あるの?」
「病院のリハは飽和してるし、訪問は安定して働ける?」
「年収は?キャリアは?リアルな声が知りたい!」
結論からいうと、訪問リハビリは医療・介護の中で最も将来性が高く、かつ安定しやすい職種です。
その理由は、単に「高齢化だから」ではありません。
訪問リハは、
- 年収が伸びやすい構造
- キャリアパスの自由度が高い
- 病院では得られない専門性が身につく
- 人手不足で採用市場が超売り手市場
- 在宅医療という国の重要施策の中心である
という複数の要因が集まっているため、PTにとって非常に魅力的なフィールドになっています。

ここでは、“収入・キャリアパス・市場価値・現場のリアル” を徹底的に解説します。
訪問リハビリ職の年収とキャリアパス
訪問リハの年収は、病院・施設と比較しても最も高い水準に位置します。
▶訪問リハの平均年収
| 働き方 | 平均月収 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 病院PT(急性期〜回復期) | 22〜27万円 | 350〜420万円 |
| 施設PT(老健・デイケア) | 23〜28万円 | 360〜430万円 |
| 訪問リハ(正社員) | 30〜40万円 | 450〜550万円 |
| 訪問リハ(管理者) | 40〜55万円 | 550〜700万円 |
訪問リハは、
- 訪問件数に応じたインセンティブ
- 管理者手当(3〜7万円以上)
- 売上に応じた歩合
など、収入アップの仕組みが豊富です。
▶訪問リハのキャリアパスは「選択肢の多さ」が魅力
病院のキャリアは「主任 → 主査 → リハ長」など少ないですが、訪問リハは違います。
訪問リハで積めるキャリアの種類
- 訪問リハスタッフ(正社員)
- 管理者・管理者候補
- リハ責任者
- エリアマネージャー
- 訪問看護ステーションの立ち上げメンバー
- 業務委託・フリーランス訪問PT
- 自費リハビリ(開業・委託)
訪問リハで経験を積むことで、将来の働き方の選択肢が大幅に広がるのが最大の魅力です。
他のリハビリ職(病院・施設)との比較
訪問リハの将来性を理解するには、病院・施設との比較が欠かせません。
▶① 病院PTとの比較
病院は安定しているように見えて、実は収益構造が厳しい職場です。
- 診療報酬の点数が頭打ち
- 在院日数短縮でリハ単位を積みにくい
- 人件費が上がりにくい仕組み
- 昇給は年2,000〜3,000円のケース多数
対して訪問リハは、
- 1件あたりの収益が高い
- 病棟より利益率が高い
- インセンティブがつきやすい
同じPTでも給与構造そのものが違うのです。
▶② 施設PTとの比較
施設(デイ・老健)は利用者が多く、役割自体は重要ですが、
- 加算による収益上限が低い
- 機能訓練指導員の参入で飽和しやすい
- PTの専門性が必ずしも活かせるとは限らない
これに対し訪問リハでは、
- 在宅での専門性が最大限に活かせる
- PTの代替が効きにくい領域(専門性が高い)
- 「生活に直接影響する介入」ができるため価値が高い

市場価値の観点でも、訪問リハはPTがもっとも稼ぎやすい分野と言えます。
「老健リハとの違いを比較したい方はこちらの記事もおすすめです。」
現場で働く人たちのリアルな声(インタビュー・口コミ)
最後に、訪問リハで働くPTたちの“本音”を紹介します。
▶訪問リハ歴3年(30代・男性)
「病院では給料が頭打ちでしたが、訪問に来てから毎月の手取りが7〜10万円上がりました。1人で判断するのは最初怖かったけど、慣れると自由度が高くて働きやすいです。」
▶訪問リハ歴1年(20代・女性)
「病院での人間関係がストレスでしたが、訪問は人間関係の疲れがほぼゼロ。移動時間がリフレッシュになるので意外と快適です。」
▶訪問リハ歴8年(40代・管理者)
「訪問のいいところは、努力した分だけ収入に反映されること。管理者になると年収600〜700万も現実的で、キャリアとしても魅力が大きいです。」
▶訪問に不安があったPTの声
「最初は『自分にできるかな?』と不安でしたが、 同行研修がしっかりしていて安心してスタートできました。病院では経験できない“生活を変える仕事”ができるのが大きなやりがいです。」
訪問リハビリは、年収・将来性・キャリアの幅・専門性のすべてがそろった、PTの中でも最も安定した職業のひとつです。

病院で将来に不安を感じているPTにとって、訪問リハは間違いなく強力なキャリアの選択肢になります。
【独自視点】訪問リハビリの未来予測シナリオ
「訪問リハビリの将来性って本当に大丈夫なの?」
「この先も需要が続くのか、転職して後悔しないか知りたい…」

“訪問リハの未来”について、多くは漠然とした内容しか書いていません。
しかし、理学療法士としてキャリアの分岐点に立つあなたに必要なのは、「データ・政策・現場の変化を踏まえたリアルな未来シナリオ」です。
ここでは、最新動向をもとに、訪問リハビリの未来を3年後 → 5年後 → 地域別 → コロナ後の構造変化という独自の視点で深掘りします。
「訪問リハの給料が生活にどう影響するかは、手取りについてまとめたこちらの記事が参考になります。」
3年後・5年後の需要予測(データ+専門家コメント)
訪問リハビリの需要は、今後確実に“増え続ける”と予測されています。 その根拠は、高齢化だけではありません。
▶最新データに基づく需要予測
- 2025年:75歳以上人口が急増(団塊の世代が後期高齢者へ)
- 2030年:高齢人口がピークに近づく
- 2040年:高齢化率35% → 生活期・在宅の需要が最大化
特に訪問リハは、通所が難しい高齢者を支えるため、今後5〜10年は確実に需要が伸びる領域です。
▶専門家コメント(在宅医療領域の管理者の見解)
ある訪問看護ステーション管理者は次のように語っています。
「5年以内に訪問リハの需要はさらに拡大します。 理由は“病院が受け皿になれない高齢者”が増え続けるからです。 訪問リハに参入するPTがまだ少なく、供給が追いついていません。」
このように、“供給不足×需要増加”という構造により、 訪問リハは今後数年で市場価値がさらに高くなると予測できます。
▶訪問リハの未来シナリオ(独自分析)
3年後:訪問看護ステーションの増加が継続 ・訪問リハの需要が供給を上回る ・給与水準は現状維持〜微増
5年後:専門性の高い訪問PTの価値が上昇 ・管理者の必要数が急増 → 年収600万円台が一般化 ・在宅医療のDX化が進み、働きやすさが向上

今から訪問リハを経験しておくことは、未来のキャリアの安定性を高める“最適な投資”と言えるでしょう。
都市部と地方で異なる将来性
訪問リハの将来性は、地域によって大きく異なるという点も重要です。
▶都市部(東京・大阪・福岡など)の特徴
- 訪問看護ステーションの数が多い → 選択肢が豊富
- 事業所間の競争が激しい → 給与水準が高くなりやすい
- PTの確保が難しく、売り手市場が続く
- 在宅医療モデルが成熟しているため安定しやすい
結論:都市部は今後も高給与の傾向が続きやすい。
▶地方都市・郊外の特徴
- ステーション数が少ないため、PTの奪い合いが起きにくい
- 人口減少により、将来の利用者数が減る可能性も
- その一方で、訪問ができるPTが非常に少ないため価値が高い
地方は人口問題に左右されますが、 訪問ができるPTの価値は都市部以上に高いケースも多いのが現実です。
▶総合結論
都市部 → 給与・働きやすさが安定
地方 → 市場価値が高く、待遇アップの余地大
どちらにしても、PTが訪問スキルを持つメリットは大きく、地域差があっても“訪問リハは将来性が高い”という結論は変わりません。
コロナ禍を経た訪問リハビリの変化
訪問リハはコロナ禍を境に、大きく進化しました。 これは他のリハ職にはない特徴であり、将来性の高さを裏付ける重要ポイントです。
▶①「通所ができない人」を支える役割が拡大
コロナで通所サービスを休止・縮小した結果、
- 外出できない高齢者が増えた
- リハビリを受けられない“空白期間”が発生

そこで需要が急増したのが訪問リハビリです。
これは一時的なものではなく、「通えない人を支える」という訪問リハの役割が社会に定着した瞬間でした。
▶② 在宅医療の重要性がさらに認識された
病院に行くことがリスクになったことで、
- 在宅医療の価値が爆発的に上昇
- 国の在宅推進が加速
- 訪問系サービスが医療介護の主流へ
コロナ禍は“訪問リハの価値を社会全体が再認識する転換点”となりました。
▶③ ICTの導入が進み、働き方が改善
訪問リハはICT化の恩恵を最も受ける分野です。
- オンラインカンファレンスの普及
- 電子カルテ・音声入力の導入
- 訪問ルートの自動最適化
この結果、以前より働きやすさ・生産性が大きく向上しました。
訪問リハビリの未来は、データ・現場の声・政策・地域差・コロナ後の変化すべてを踏まえても、「大きく成長し続ける可能性の高い領域」です。
病院の先行きに不安を感じているPTにとって、訪問リハは将来性・働きやすさ・市場価値のすべてが揃った最有力の選択肢といえるでしょう。
訪問リハビリで活躍するために今からできること
「将来性はあると分かった。でも、実際に訪問リハで活躍できるのか不安…」
「今のうちに何を準備すれば、訪問でも通用するPTになれる?」

そんな不安を抱く理学療法士は多いですが、安心してください。
訪問リハは正しい準備をしておけば必ず活躍できる職場です。
ここでは、「訪問リハで価値を発揮するための具体的な準備」をスキル・職場選び・マインドセットという3つの軸で徹底解説します。
スキルアップに必要な資格や知識
訪問リハで求められるスキルは、病院と似ているようで少し違います。特に重要なのは、生活期・在宅特有の知識と判断力です。
▶① 訪問リハで最も重要なのは「リスク管理スキル」
訪問は医師が常駐していないため、 PT自身が“現場で判断”する場面が多いのが特徴です。
以下の知識は訪問で必須レベルです。
- バイタルの見方(呼吸数・SpO2・心拍)
- 急変リスクの察知(脱水・感染・心不全・誤嚥)
- 服薬の影響理解
- 慢性疾患(COPD・心疾患・糖尿病)の基礎知識
病院経験がそのまま活かせますが、“生活環境×既往歴”の視点を持てるPTは訪問で重宝されます。
▶② 生活期リハの専門知識
訪問は「生活に合わせた機能向上」が目的です。
- 福祉用具(歩行器・ベッド・ポータブルトイレ)
- 住環境整備(段差・手すり・動線)
- 家族指導(介助方法・負担軽減)
できるPTほど、利用者の生活が劇的に改善します。
▶③ 取得すると強い資格
訪問で活きる資格は以下です。
- 呼吸療法認定士(COPD・心不全ケースで有利)
- 地域ケア会議参加資格(自治体研修)
- 住環境コーディネーター
資格がなくても働けますが、管理者候補を目指すPTは持っておくと強い武器になります。
需要が高いエリアや職場の選び方
訪問リハで成功するかは、「職場選び」が8割です。
▶① 需要が高いエリアの特徴
- 高齢化率が30%以上の地域
- 在宅医療の推進が進んでいる自治体
- 病院が少ない/通所サービスが不足している地域
特に以下の地域は訪問の需要が高く、求人も多い傾向があります。
- 東京・神奈川・大阪・福岡(都市部:高収入)
- 東北・九州・北陸の地方都市(訪問PTが不足:市場価値が高い)

都市部は選択肢が多く働きやすい、地方は希少性が高く待遇が上がりやすいという特徴があります。
▶② 優良な訪問ステーションの特徴
以下に当てはまる職場は「良い事業所」です。
- 管理者が訪問経験豊富
- 教育体制が整っている(同行期間が長い)
- 看護とリハの連携がスムーズ
- ICT化が進んでいる(電子カルテ・音声入力)
- 移動ルートを効率化している
逆に、以下に当てはまる職場は要注意です。
- 訪問経験のない管理者
- 同行研修が2〜3回で終わる
- 1日の訪問件数が6〜7件と多い
- 人の出入りが激しい(離職率が高い)
職場次第で、成長スピードも年収も働きやすさも大きく変わります。
業界の変化に対応するためのマインドセット
訪問リハで長く活躍するために最も大事なのは、「マインドセット」=仕事への姿勢です。
▶① “一人で判断する力”を育てる意識
訪問は病院のようにすぐに相談できる環境ではありません。
そのため、
- 観察力
- 決断力
- リスク管理
を高める意識を持つことが重要です。
▶② 多職種連携を面倒と思わないこと
訪問リハはケアマネ・看護・医師・家族など、 関わる職種が非常に多いです。
コミュニケーションを円滑に取れるPTは、 訪問で圧倒的に価値を発揮できます。
「訪問看護ステーションでの看護師との関係性を知りたい方はこちらも参考になります。」
▶③ “生活を良くする”という視点を持つ
訪問リハの中心は「ADL」「IADL」「生活環境」です。病院のように「機能回復」だけではなく、生活のストーリーを組み立てる視点が重要です。
▶④ 変化をチャンスと捉える
在宅医療は成長中の市場であり、制度も働き方も進化しています。
変化を恐れるのではなく、「変化に乗る=キャリアアップのチャンス」と捉えられるPTは訪問で必ず成功します。
訪問リハビリは、将来性・市場価値・年収・働きやすさのすべてが揃った分野です。
そして、正しい準備をすれば誰でも活躍できる可能性があります。

今のうちにスキル・職場選び・マインドを整えて、“将来に強いPT”を目指しましょう。
【ここでしか読めない】訪問リハビリ業界の裏側と本音
「訪問リハビリは将来性があると聞くけど…現場の本音はどうなの?」
「離職率が高いって本当?やっていける自信がない…」
こうした不安を抱えて「訪問リハビリの将来性」を気にするPTは多いですが、
ネット上の情報は“きれいごと”が多く、現場の実態に触れる記事はほとんどありません。
そこで本記事では、業界内部の実情・成功する事業所の条件・PTに求められる本当のスキルまで、他の記事では触れない「リアル」を徹底的に解説します。

現場を深く理解することで、「後悔しない訪問リハ転職」ができるようになります。
なぜ離職率が高いと言われるのか?
訪問リハは「離職率が高い」と言われがちですが、 その背景には“訪問ならではの構造的な理由”があります。
▶① 一人で判断する負荷が大きい
訪問は病院のように近くに医師や先輩がいません。 そのため、PT自身が状況判断しなければならない場面が多くなります。
- 急変リスクの判断
- 医療的な変化の察知
- 家族の不安への対応
特に若手は“相談しづらさ”に不安を感じ、離れることがあります。
▶② 教育体制の差が大きい
訪問リハの離職率は「職場による差が極端」です。
- 同行研修が丁寧に行われる職場 → 離職率が低い
- 2〜3回の同行後すぐ単独訪問 → 不安が大きく辞めやすい
つまり、離職率の高さは “訪問が問題”なのではなく、“教育体制が弱い事業所”の問題であることが多いのです。
▶③ 訪問件数のノルマが重い職場がある
訪問リハの給与が高い理由は「1件ごとの収益が高い」から。 その一方で、悪質な事業所はPTに過剰な件数を求めることがあります。
- 1日6〜7件(移動しながらはキツい)
- 書類業務も自宅で行う必要がある
- 休憩が取れない
こうした“ブラック訪問”に入ってしまったPTが離職しているだけであり、 優良事業所では離職率はむしろ低い傾向があります。
成功している事業所に共通する特徴
離職率が低く、PTが伸び続ける事業所には明確な共通点があります。
▶① 教育体制が整っている(同行期間が長い)
優良事業所では、以下が徹底されています。
- 最低1〜2か月の同行あり
- ケースごとに振り返りの時間を確保
- 多職種連携の方法を実地で指導
教育が手厚ければ、訪問が未経験でも問題なくスタートできます。
▶② 看護とリハの連携が強い
成功しているステーションの特徴は、「看護 × リハ」の連携がスムーズであること。
- 看護師が利用者の情報を常に共有
- 医師への連絡体制が明確
- チームとして動けるため安心感がある
PTが安心して働ける環境が整っているため、長く続けやすいのです。
▶③ ICT化が進んでおり業務効率が高い
成功している事業所は“ITによる効率化”が当たり前です。
- 電子カルテ+音声入力
- 訪問ルートの自動最適化
- スマホで記録完結
これにより、移動や記録の負担が大幅に軽減され、PTが「利用者支援」に集中できる環境が整います。
現場で求められている「本当のスキル」
訪問リハビリで活躍できるPTは、 病院経験の長さや技術力“だけ”で決まりません。
▶① コミュニケーション能力(家族・多職種)
訪問は、利用者本人だけではなく家族やケアマネとの関わりが重要です。
「相手の不安を消す」「必要な情報を分かりやすく伝える」

これができるPTは利用者・家族から高い信頼を得られます。
▶② リスク管理スキル
訪問は常に「安全第一」。
- 呼吸状態の変化
- 心不全の悪化兆候
- 脱水・感染・疼痛
こうした兆候を素早く察知できるPTは、 どの事業所からも求められます。
▶③ 環境調整・生活支援スキル
訪問のリハビリ価値は「生活を変えられるか」。
具体的には、
- 福祉用具の選定
- 動線の改善
- 家族の介助負担の軽減
- 転倒しにくい環境作り
このスキルがあるPTは、利用者から最も感謝される“生活期のプロ”です。
▶④ 判断力・決断力
訪問は「迷ったら相談」ではなく、「迷ったら観察して判断」が必要な場面に出会います。
この力があるPTは訪問で圧倒的に強く、 管理者候補としても評価されやすいです。
訪問リハビリは将来性のある仕事ですが、 実際の現場には良い面・厳しい面の両方があります。
しかし、裏側の構造を理解し、
- 優良事業所を選ぶ力
- 現場で求められるスキル
- 適切なマインド
を身につければ、

「訪問リハでキャリアも収入も安定させる」ことは十分可能です。
訪問リハの“本音”を知った上で動くことで、 将来の不安を消し、より良いキャリア選択ができるようになるでしょう。
「訪問リハへの転職を考えている方にはこちらの記事も役立ちます。」
まとめ|訪問リハビリの将来性と裏側を正しく理解してキャリアを伸ばそう
訪問リハビリは、将来性・需要・市場価値すべてが高い領域ですが、「どの職場で働くか」「どんなスキルを身につけるか」によって PT人生が大きく変わるフィールドでもあります。
良い職場を選べば年収・働きやすさ・専門性のすべてを手に入れられますが、 悪い職場を選ぶと離職率が高い理由に直面する可能性もあります。
最後に、この記事で解説した重要ポイントをまとめます。
▶重要ポイント
- 訪問リハは「在宅医療の中心」であり、今後も需要は確実に伸びる。
- 離職率が高く見える理由は「訪問の問題」ではなく「教育不足の事業所」にある。
- 成功している事業所は、同行研修が長く、看護との連携が強く、ICT化が進んでいる。
- 訪問リハではコミュニケーション能力・リスク管理・生活環境調整スキルが最重要。
- 訪問PTは“生活を変えるリハ”が求められ、病院では得られない専門性が身につく。
- 悪質な事業所は「過剰な訪問件数」「記録の持ち帰り」などブラック要素がある。
- 優良事業所を選ぶことで、年収・働きやすさ・キャリアのすべてが安定する。
- 判断力・観察力・多職種連携のスキルを磨くことで、管理者候補として評価されやすい。
- 訪問は“スキルが給与に直結する”ため、努力が認められやすい働き方である。
- 現場の本音を知ることで、自分に合う職場を見極められ、失敗のリスクを避けられる。

訪問リハは“将来性が高い”だけでなく、PTとしての可能性を最大化できる働き方です。
不安を感じるのは当然ですが、 裏側の構造・本音・求められるスキルを理解すれば、 あなたにとって訪問リハは大きなチャンスのあるキャリアの選択肢になるはずです。