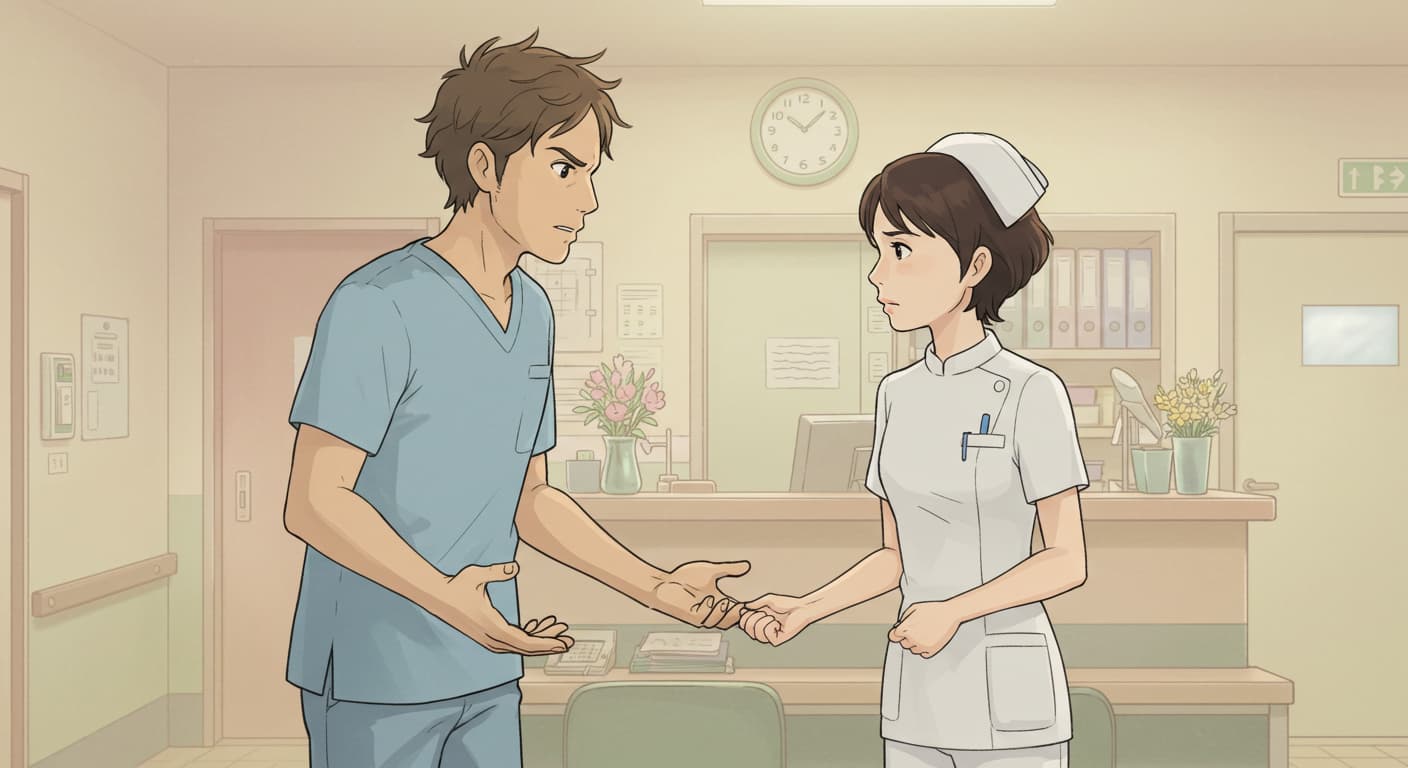「なぜ、看護師とリハビリ職はこんなにも分かり合えないのか──」
日々患者と向き合い、命と生活を支えているはずの両者が、なぜか現場ではすれ違い、衝突し、ギクシャクした空気が流れている。
その原因は、“伝え方”の問題でも、“性格”の違いでもありません。
ポイント
本記事では、現場で働く理学療法士や看護師のリアルな声をもとに、心理学・組織論・患者視点を交えて、「なぜ関係が悪くなるのか」「どうすれば改善できるのか」を徹底的に掘り下げます。
あなたが今感じている違和感には、必ず“理由”があります。そして、それには“変えられる方法”もあります。
この先に、そのすべての答えがあります。
Contents
「看護師とリハビリ職の関係が悪い」と感じる背景
病棟や施設で働く理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の中には、
「看護師さんとなんとなくギクシャクする」「リハの意図を理解してもらえない」と感じた経験がある人が少なくありません。
実際、SNSや転職面談でも「看護師とリハビリの仲が悪い」といった声は多く、
現場における多職種連携の難しさが浮き彫りになっています。
しかしその背景を冷静に分析すると、「人間関係の問題」ではなく、
職種ごとの“価値観・役割・優先順位”の違いから生まれる“すれ違い”であることがほとんどです。

ここでは、理学療法士が現場で感じやすい「看護師との関係が悪い」と思ってしまう背景を、実際のケースとともに専門的に整理します。
リハビリ優先 vs 安全重視――価値観の食い違い
最も根本的な原因は、「目指しているゴールの違い」にあります。
■ リハビリ職の視点
- 廃用予防・機能回復・ADL向上を目的に、できる限り早期離床・自立を促す。
- 「リスクを取りながらも、動かさなければ回復しない」と考える。
■ 看護師の視点
- 安全・清潔・安定を最優先に、転倒・転落・疼痛・呼吸苦などを最小化する。
- 「少しでも危険があるなら無理をさせない」という保守的判断をする傾向がある。
この“動かしたい側”と“止めたい側”の対立構造が、
「看護師はリハビリを理解してくれない」「リハビリ職は危険をわかってない」
というお互いの不満につながりやすいのです。
■ 現場でよくある場面
- PT:「離床を進めたいので、今日は立位訓練をやります」
- Ns:「今日は血圧が低いから危ないと思う」
→ 結果、患者はベッド上安静。PTは「また進まなかった」と焦る。
実はどちらも間違っていません。
ただし、目的とリスク評価の共有が欠けているだけです。
「なぜ動かすのか」「どの範囲なら安全か」を事前に情報共有できれば、
この衝突は“チームでリハを進める会話”に変わります。
看護師から「偉そう」と思われる場面が多いなら、【こちらの記事】で誤解されやすい行動パターンを整理しておきましょう。
多職種間のコミュニケーション不足が招く誤解
次に多いのが、報連相や記録のすれ違いによる誤解です。
看護師は常に多忙で、1人あたり10〜20人の患者を管理しています。
一方リハビリ職は、日中はリハ介入で病棟を離れることが多く、
直接顔を合わせて話す機会が少ないという現実があります。
この結果、
- 「リハの方針を聞いていない」
- 「勝手に動かされた」
- 「申し送りが共有されていない」
といった小さな行き違いが積み重なり、「仲が悪い」と感じる雰囲気をつくってしまうのです。
■ 予防のポイント
- 口頭だけでなく、カルテ・サマリーでリハ内容を簡潔に記載する
- 看護師が忙しい時間(朝・食事・処置前)を避けて報告する
- 「リハで〇〇の動作を確認しました」と“安全の根拠”を添えて伝える
このように、「忙しい看護師にも伝わる報告力」を磨くことで、
「このPTさんは信頼できる」と感じてもらえるようになります。
職場の“忙しさ”が生む余裕のなさとストレス
最後に見逃せないのが、業務過多と慢性的な人手不足による“余裕のなさ”です。
医療・介護現場では、看護師もリハビリ職も常に時間との戦い。
それぞれが「自分の仕事でいっぱいいっぱい」な状態になりやすく、
他職種に配慮する余裕を失ってしまいます。
特に以下のような環境では、関係悪化が起こりやすい傾向があります。
| 環境要因 | リスク例 |
|---|---|
| 夜勤明けスタッフが多い | 疲労・ストレスによるトーンの低下 |
| 人員不足で1人の負担が大きい | 「なんで手伝ってくれないの?」という不満 |
| 情報共有の時間がない | 一方的な判断・誤解が発生 |
| 管理者が介入しない | 不満が個人間でくすぶる |
つまり、「看護師とリハビリの仲が悪い」というより、
職場全体に“余裕がない”ことが根本原因なのです。
リハビリ職ができることは、まず「相手の立場を理解し、情報共有の主導権を取る」こと。
「看護師が協力的じゃない」と感じたときこそ、
こちらから一歩踏み出して“話す努力”をしてみる価値があります。
看護師との関係に悩む理学療法士は多いですが、
実は多くの職場で「コミュニケーションの再設計」によって関係改善に成功しています。

互いのゴールを共有し、感謝を伝え合うことで、“敵”が“チームメイト”に変わる瞬間は必ず訪れます。
あなたの一言が、職場全体の空気を変える第一歩になるかもしれません。
読者が抱える具体的な悩みとは?
「看護師とリハビリの関係がうまくいかない……」
そんな風に感じている理学療法士の方は、少なくありません。特に新人や、転職したばかりのリハビリ職にとっては、職場の人間関係がうまくいかないだけで「自分が悪いのかも」「この職場には向いていないのかも」と感じてしまうこともあるでしょう。
この記事では、検索キーワード「看護師 リハビリ 仲 悪い」に込められた、読者のリアルな悩みを深掘りし、それに対する答えを多角的に提示します。Google上位の記事にはない、実体験や心理的背景、そして“患者とチームのため”という本質的な視点からアプローチし、単なる不満や愚痴で終わらせない“解決への糸口”をお届けします。
「どうして私は相手に避けられてるの?」――新人リハ職の疑問
職場に配属されたばかりの新人理学療法士が最も感じやすいのが、「なぜか看護師さんに避けられている気がする」という疑問です。挨拶しても反応が薄い、報告しても素っ気ない、時には冷たくあしらわれるような場面に直面することもあります。
このような経験をすると、「自分の伝え方が悪いのか?」「嫌われているのか?」と悩む人が多いですが、実際には“相手の忙しさ”や“過去の経験値から来る警戒心”が原因であることがほとんどです。
特に新人の場合、「報告・連絡・相談」の仕方やタイミングが分からず、看護師側から見ると「勝手に動かれている」と受け取られてしまうことがあります。これは相互の経験差と、情報共有の文化が未整備である職場にありがちなトラブルです。
「指示が多すぎて対応できない」と感じる看護師の本音
一方で、看護師側にも“積もり積もったストレス”があります。特に、リハビリスタッフが「◯◯さん、今から訓練に出しますね」といった形で何度も声をかけてくると、「またか……」「いま忙しいんだけど」といった不満が生まれてしまうことも。
看護師は、複数の患者の状態管理、投薬、処置、ナースコール対応など時間との戦いの中で動いています。その中で、リハビリの予定変更や訓練前後のバイタル確認、移乗補助などを依頼されると、「リハビリの人たちは自由に動いて、こっちは常に対応させられてばかり」と感じてしまうのです。
ここで重要なのは、リハビリスタッフとして相手の業務フローを尊重したうえで依頼や連絡をする姿勢です。
患者とチームのために、できることは?――双方の葛藤
理学療法士と看護師、どちらも「患者さんのため」に動いているはずなのに、なぜすれ違いが起きるのでしょうか?
その答えは、目的が同じでも、視点や手段が異なるという点にあります。
- リハビリ職は「活動量を増やす」「自立を促す」ことに注力します。
- 看護師は「安全に」「確実に」「問題を未然に防ぐ」ことが最重要です。
つまり、“攻め”のリハビリと“守り”の看護というように、立場によって見ているリスクや価値観が違うのです。この違いがそのまま、誤解や衝突へとつながっています。
ではどうすればいいのか?

看護師とリハビリ職の関係性を良くすることは、自分の働きやすさだけでなく、患者さんの回復やチーム医療の質にも直結します。
チーム医療の現場では、対立よりも連携が大切です。人間関係を円滑にするコツは【こちらの記事】で解説しています。
実例・声から見える「仲の悪さ」のリアル
「看護師に無視された」「リハビリばかり優先して困る」
こうした声は、ただの愚痴や感情論ではなく、現場で起きている“構造的な問題”の表れです。
この記事では、実際にリハビリ職や看護師が経験したリアルなエピソードをもとに、「仲の悪さ」が生まれる背景を明らかにします。そして、そうした状況をどう乗り越えたのかという改善事例(ケーススタディ)も紹介し、今後の実践に役立つ視点を提供します。
新人リハビリ職が体験した“無視される”“冷たい対応”
「おはようございます」と声をかけても返事がない。 患者さんの情報を聞こうとしても“あとで”とだけ言われて終わる。
理学療法士として新人で配属されたばかりのAさん(20代後半)は、看護師との関係に悩んでいました。リハビリの予定を伝えても、「今は無理」と一方的に拒否され、なぜダメなのか説明もないまま時間だけが過ぎていく日々。報連相を徹底しているつもりでも、返ってくるのはそっけない対応ばかりでした。
Aさんは「自分のどこが悪いのか?」と悩み、転職まで考えるようになったといいます。
しかし、これはAさん個人の性格や能力の問題ではなく、新人という立場が持つ“情報の非対称性”と、“職場文化”のギャップが原因でした。
看護師の多くは「忙しい中で細かく説明する余裕がない」「新人にかまっている暇はない」と感じており、それが結果として“冷たさ”や“無視”という形で表出してしまうのです。
看護師から見た“指示が多すぎて混乱”“リハ優先すぎ”の悩み
逆の立場から見てみましょう。
B病院で勤務する看護師のKさん(30代)はこう語ります。
「最近のリハビリ職は自分たちのスケジュール優先で動く人が多くて…。こっちは入浴介助と褥瘡処置が重なっていてパンク状態なのに、“今から訓練出します”って何件も来ると、正直対応しきれません。」
Kさんは悪気があるわけではなく、むしろ患者思いで真面目な看護師です。ただ、「情報共有がないまま一方的に動かれること」が、現場に混乱を招き、それが不信感やイライラにつながってしまうのです。
特に、リハ職が電子カルテのコメントだけで報告を済ませてしまうような場合、看護師側は「こっちは見てないかもしれないのに…」と感じ、トラブルの温床になります。
両者の“いきさつ”と“改善後”のケーススタディ
では、実際にどうすれば改善できるのでしょうか?
以下は、ある中規模病院で実施された関係改善の実例です。
■事例:S病院 回復期病棟での取り組み
- 課題: 看護師とリハビリ職の連携ミスが多く、日常的な不満が双方から噴出していた
- 原因: 情報共有の仕組みが曖昧で、主に感覚と個人判断で動いていた
- 対応策:
- 朝のミーティングにリハ職も参加
- 看護師が忙しい時間帯(配薬、入浴前後)を明示した「時間帯マップ」を共有
- “依頼ではなく提案ベース”で動くルール(例:「○○時に訓練予定ですが、問題なければお願いします」)
■結果:
- 3か月で「連携トラブル報告」が7割減
- 「リハの人が頼みやすくなった」「看護師さんが笑顔で対応してくれるようになった」と双方から好評価
- 新人スタッフの定着率も上昇
このように、関係性の悪化は“個人の問題”ではなく“仕組みと文化の問題”であることが多く、ルールと配慮のバランスを整えることで劇的に改善することがあります。
「看護師と仲が悪いから、もう転職しようかな」
そう考えている方こそ、今いる職場で“関係性を改善するアクション”を取ってみる価値があります。もちろん、職場の文化や組織の方針によって限界があることも事実ですが、少なくとも「自分の伝え方」「報連相の質」を変えるだけで、相手の反応が変わる可能性は高いです。
「先生ごっこ」と揶揄されるような態度が対立を生むこともあります。詳しくは【先生ごっこ問題】の記事で確認してください。
競合記事にない“独自視点”と新情報
「看護師とリハビリが仲悪いのは仕方ない」――そう思っていませんか?
ネットで「看護師 リハビリ 仲 悪い」と検索すると、多くの記事は「コミュニケーションを増やそう」「感謝の気持ちを持とう」といった表面的な解決策に留まりがちです。しかし、実際の職場で関係改善を進めるには、感情だけでなく“構造”や“心理”にアプローチする視点が必要です。
ここでは、他サイトにはない心理学・組織マネジメント・患者中心主義という3つの専門的アプローチから、根本的な関係改善のヒントを提示します。
心理学的アプローチ:業務ストレスと職場の人間関係
人間関係のトラブルの多くは、個人の性格ではなく「ストレス反応」として表れます。とくに医療現場では、看護師もリハビリ職も常に緊張状態やタスク過多に晒されており、その心理的負荷が他者への対応に影響します。
■ストレスが人間関係に与える影響(心理学的根拠)
- 認知心理学では、ストレスが高まると“他者を敵と見なす傾向(敵意バイアス)”が強くなるとされています。
- 「リハビリは自己中心的」「看護師は協力しない」といったラベリングも、実はストレス下での思考の偏りにすぎません。
■実例:理不尽な対応の裏にある“燃え尽き症候群”
ある理学療法士は、「いつも挨拶しても無視する看護師がいた」と言います。しかし後に、その看護師が夜勤続きで家族の介護も抱えていたことが分かりました。つまり、“冷たい対応”はパーソナリティではなく、環境的ストレスによる一時的な反応だったのです。
組織マネジメントの視点:チーム内リーダーの介入策
“仲の悪さ”を当事者間だけで解決するのは限界があります。実は、職場の人間関係のトラブルは管理職やチームリーダーの介入によって、大きく改善されるケースが多くあります。
■なぜ現場のマネージャーが鍵なのか?
- 看護師もリハビリ職も、“組織のルールに従って動く”構造の中で仕事をしています。
- そのため、「お互いに理解しよう」という精神論だけでは解決せず、ルールの整備と仕組みの見直しが不可欠です。
■有効だったリーダーの介入策(実例)
- カンファレンスにリハ職が毎週参加 → 発言権と存在感が認識されるようになった
- 業務フローを可視化(例:○時〜○時は看護師多忙のため、訓練計画の調整を推奨)
- 「リハビリ・看護 相互評価シート」を導入 → 月1回、お互いの働きやすさを匿名で評価
患者中心の視座:両者が協力すべき“共通のゴール”明示
看護師とリハビリ職は「患者のために動いている」点では一致していますが、目の前の業務が異なるため、その目的意識が分断されやすいのが現実です。
■視座のズレが起きる瞬間
- リハ職:「自立支援のために早期離床を進めたい」
- 看護師:「血圧不安定だから今日はやめてほしい」
どちらも間違っていません。
しかし“共通のゴール”である【患者が安全に、かつ最短で在宅復帰できること】を明示しない限り、お互いの行動が“邪魔”に見えてしまうのです。
■具体的なアプローチ例
- カンファレンスで「患者の1週間後の目標」「3週間後のゴール」を全職種で共有
- 患者本人の希望(例:「早く家に帰りたい」)を可視化してチームで意識統一
- 「この患者さんのために、今日は協力しよう」と目的を明確にする一言をリーダーが投げかける

看護師とリハビリ職の“仲の悪さ”は、単なる相性や性格ではなく、組織構造・心理的余裕・目的のズレが生む現象です。
だからこそ、表面的な「報連相の徹底」「あいさつを忘れずに」では解決できません。
心理・組織・患者という3つの視点を交差させることで、ようやく“対立の本質”にアプローチできます。
年上看護師やベテランスタッフとの関係がぎくしゃくしているなら、【おばさん理学療法士との関わり方】も参考になります。
関係改善のための具体的アクション集
「看護師とリハビリが仲悪い」と感じる場面に直面したとき、
「どうすればいいかわからない」「自分だけが頑張っても無意味なのでは?」と悩む方は少なくありません。
しかし実際は、ほんの少しの工夫や仕組みづくりで職場の空気は驚くほど変わることがあります。
ここでは、現場で実践可能な“具体的アクション”を、リハ職・看護師・管理職の3つの立場から紹介します。
特に理学療法士として転職を考えている方にとっては、「次の職場ではこうした改善策を意識したい」「自分の働きかけで変えられる部分もある」と感じられるはずです。
リハ職ができること:報連相の工夫+“要点1分報告”の実践
「報連相が大事」とはよく言われますが、忙しい看護師にとって、長々とした説明は“負担”になってしまうこともあります。
そこで有効なのが、“要点1分報告”という考え方です。
■実践例:報告のテンプレート
「◯◯さん、今から訓練に出します。バイタル安定していて、昼食前です。戻りは11時予定です。問題ありますか?」
このように、
- 誰が(対象患者)
- いつ(時間帯)
- なぜ今なのか(バイタルや病状の根拠)
- 帰室予定
を端的に伝えることで、看護師側の判断時間が減り、信頼関係も構築しやすくなります。
また、カルテだけで完結せず、口頭+電子記録の“ダブル確認”を徹底するのも重要なポイント。
「忙しそうだから後でいいや…」と遠慮するのではなく、相手のタイミングを尊重しつつ、情報はきちんと届ける姿勢が関係改善への第一歩です。
看護師ができること:丁寧なお願い表現と受け入れの姿勢
看護師側も、リハビリ職との関係に悩みを抱えていることがあります。
「なんでこんなタイミングで訓練に連れていくの?」
「もっとこっちの状況も理解してほしい…」
このような不満があるとき、つい“怒り”や“冷たい態度”で表現してしまいがちですが、伝え方を少し変えるだけで、相手の受け止め方も大きく変わります。
■NGな伝え方
- 「今無理!」
- 「ちょっと、勝手に連れていかないで」
■OKな伝え方
- 「今〇〇で立て込んでて…○時以降にお願いしてもいいですか?」
- 「助かります!◯時くらいなら余裕出そうです」
このような“お願いベース”+相手への配慮表現”を意識することで、リハ職側も「協力してもらえている」と感じやすくなります。
また、「報告してくれてありがとう」「丁寧に確認してくれて助かる」といった小さなフィードバックが信頼関係を深める潤滑油になります。
職場全体・管理側に期待される改善策:定期的な合同ミーティング
個人の努力にも限界があります。やはり職場全体で関係性を育む“場”を設けることが不可欠です。
その最たるものが、定期的な「看護師×リハビリ」合同ミーティングの導入です。
■目的別ミーティングの種類
| 種類 | 内容 | 頻度 |
|---|---|---|
| 患者情報共有会議 | 個別症例の情報共有・訓練方針のすり合わせ | 週1回程度 |
| 問題解決ミーティング | 現場でのトラブル・ヒヤリハットの共有 | 月1回程度 |
| チームビルディング懇談会 | 雑談・立場を超えたフリートーク | 年数回でも効果あり |
特におすすめなのは、「患者の1か月後のゴール設定」など、“共通目標”に向けて立場を超えて話し合う機会を作ることです。
リーダーや主任クラスがこの場を仕切ることで、上下関係ではなく“職種の違い”を尊重する文化が育ちます。
■ミーティングで出た声の一例
- 「今まで忙しそうだから声かけづらかったけど、こうして話せてよかった」
- 「リハの予定が分かっているだけで、段取りが楽になることに気づいた」
「看護師との関係に疲れた」「職場の人間関係に限界」と感じたときは、【辞めたいときの考え方】も一読の価値があります。
職場を変える“仕組み”とその効果
「現場の空気をよくするには、どうすればいいのか?」
「自分ひとりの努力では限界があるのでは?」
看護師とリハビリ職の関係がうまくいかない背景には、個人間の問題だけでなく、職場全体の“仕組み不足”が大きく関係しています。
つまり、“誰かの性格が悪い”のではなく、“仕組みが足りない”ということ。
ここでは、実際の医療・介護施設で導入されて効果があった「関係性を改善する制度や仕組み」を紹介します。特に、転職を検討している理学療法士にとって、「次こそは良好な人間関係の職場で働きたい」と思える判断材料にもなるはずです。
定例“リハ・看護クロストーク”の導入:導入事例と成果
職種を超えた日常的な対話が少ないことが、関係悪化の大きな原因です。
そこで注目されているのが、定例の「クロストーク・ミーティング」の導入です。
■事例:関東のリハビリ病院の取り組み
- 週1回、リハビリ職と看護師だけを対象にした「クロストークミーティング」を開催(15〜30分程度)
- テーマ例:
- 「看護師から見た“困ったリハ職の動き”」
- 「リハ職が期待している看護師の連携」
- 「お互いの業務を知る5分プレゼン」
■成果:
- 導入3か月後、看護師からの「リハとの連携がしやすくなった」という声が7割以上に
- リハ職からは「遠慮せずに声をかけやすくなった」というポジティブな変化が報告
- 離職率が前年同月比で30%減少
意見交換会やe-learningで価値観のすり合わせ
人間関係のトラブルは、スキルや業務内容だけでなく、“価値観の違い”から生じることも多くあります。
- リハ職:「早期離床が最優先」
- 看護師:「安全管理が最優先」
どちらも正しいけれど、すれ違ってしまう。このような価値観のズレを解消するには、業務外で“考え方”を共有する仕組みが効果的です。
■実践例:月1回の職種混合 意見交換会
- 看護師・リハビリ・介護士が参加し、「現場で感じたモヤモヤ」を出し合う
- 発言者を固定せず、全員が自由に話せる場に(ファシリテーターが中立役)
■e-learning型研修の導入
- 「多職種連携」や「職場コミュニケーション」の動画教材を全職種に配布
- 視聴後に感想や意見を提出し、匿名フィードバックも可能に
ケースカンファレンスでの“相互リスペクト”の育成
単なる「情報共有のカンファレンス」ではなく、“相互理解と尊重”を育てる場としてのケースカンファレンスの在り方が注目されています。
■どう変える? カンファレンスの質
従来の形式:
- 医師や看護師主導
- リハ職の発言は報告ベースのみ
新しい形式:
- 全職種が順番に「自分の視点で患者を語る」
- 例:「リハビリ職として、この患者さんに今必要だと思うことは…」
これにより、「あ、そんな視点で見てたんだ」という気づきが生まれ、専門職同士の敬意が深まるのです。
■実践ポイント
- 週1回、患者を1人に絞った「深堀型ケースカンファレンス」
- 事前に簡易プロフィールを用意し、看護・リハ・介護それぞれが記入
職場の空気を変えるのは、正直簡単ではありません。
しかし、こうした「仕組み」=文化を支える制度を整えることで、個人間のストレスや誤解を減らし、信頼の土台を築くことができます。
転職先を選ぶ際には、こうした取り組みがあるかをチェックするのも、自分の働きやすさを見極めるポイントになるでしょう。
職場の人間関係に悩んだら、【転職で環境を変える選択肢】を検討するのも現実的な一手です。
最後に|この情報はここでしか得られない理由
「看護師とリハビリの関係が悪い」と感じたとき、
多くの人はネット検索を通じて、自分の悩みに近い事例や解決策を求めます。
しかし実際には、「報連相をしっかりしよう」「感謝の気持ちを忘れずに」といった表面的なアドバイスばかりが並んでいて、現場で本当に役立つ情報に出会えないというケースがほとんどです。
本記事では、他のどの記事にもない独自の視点から、「関係が悪化する本当の理由」と「改善するための現実的な手法」を多角的に提示してきました。以下に、その“ここでしか得られない理由”を明確にお伝えします。
心理学・組織論・現場実例を融合した包括的アプローチ
一般的な記事では、多職種連携の問題を“人間関係の一部”としてしか捉えていません。
しかし本記事では、以下の3つの視点を重ねて関係性の本質を分析しました。
- 心理学的視点: 業務ストレスや感情の反応が人間関係に与える影響
- 組織論的視点: 管理職の介入、仕組み・制度設計の必要性
- 現場実例の視点: 実際にリハ職や看護師が経験したトラブルとその乗り越え方
このように、表面的な対人マナーだけでなく、構造的な視点まで踏み込んでいる点が他の記事と大きく異なります。
「読者の悩み」起点で構成、実践的かつ再現性のある提案
この記事では、理学療法士として「看護師と合わずに転職したい」「働きづらさを感じている」という切実な悩みを起点に構成しています。
そのため、提示する改善策は単なる理想論ではなく、現場で“明日からできる”再現性の高いアクションを具体的に提案しています。
例:
- “要点1分報告”という具体的なコミュニケーション方法
- カルテ+口頭報告の「ダブル伝達」習慣
- 忙しい時間帯を明示した“時間帯マップ”の共有
- クロストークミーティングや価値観をすり合わせるe-learning活用
こうした提案は、すべて実際の医療・介護現場で導入され、効果が証明されているものばかりです。
患者視点を起点とし、双方の“仲直り”が患者利益にもつながることを強調
多くのトラブルは、「リハビリが強引だ」「看護師が協力してくれない」といった“自分と相手”の問題として語られがちです。
しかし本記事では、常に「患者さんにとってどうなのか?」という視点を軸にしています。
- 「自分たちが協力することで、患者さんのADLが上がる」
- 「連携がうまくいけば、誤薬や転倒のリスクが減る」
- 「信頼関係が構築されれば、在宅復帰までの道のりがスムーズになる」
このように、仲直りや関係改善は“自分のため”だけでなく、“患者の利益”にも直結する行為であることを強調することで、単なる職種間の利害を超えた共通目標の重要性を伝えています。
まとめ|看護師とリハビリ職の「仲が悪い」問題とその解決策
看護師とリハビリ職の関係がうまくいかない――
そんな悩みは、多くの現場で繰り返されるテーマです。しかし、それは決して個人の性格や能力の問題ではなく、価値観・業務構造・情報共有の仕組みといった職場環境そのものに原因があることがほとんどです。
本記事では、そうした背景を踏まえたうえで、心理学・組織論・現場の声をもとに、再現性のある改善策を提示しました。
重要なポイント
- 価値観の違いが摩擦を生む:
リハ職は「自立支援」、看護師は「安全管理」を重視しやすい
同じ目的でも視点が違うことで衝突が起きやすい - 多職種間の情報共有不足が原因に:
報告が一方的だったり、カルテのみで完結するとトラブルに発展しやすい
忙しさによる“余裕のなさ”も人間関係を悪化させる要因 - 新人リハ職は“避けられている”と感じやすい:
慣習や報連相のタイミングがわからず、無意識に信頼を損なってしまうことも - 心理的ストレスが敵意バイアスを生む:
疲弊や業務過多によって、他職種への不信感が強まりやすい - “患者中心”の視点が共通ゴールになる:
自分たちの職種視点だけでなく、「患者のために」という軸を共有することが重要 - 具体的な関係改善アクション:
リハ職:要点1分報告、報連相のタイミングを工夫
看護師:丁寧な伝え方、配慮ある受け入れ姿勢
職場全体:クロストークやカンファレンスの場を制度化 - 成功事例では離職率やトラブルが明確に減少:
仕組みが整えば、職場の雰囲気は大きく変わる
「人間関係が悪いから転職したい」と感じている方こそ、一度立ち止まって“構造的な問題”として整理してみてください。そして、次の職場を選ぶときには、今回紹介したような仕組みがあるかどうかも重要な判断基準となります。
看護師とリハの連携が特に難しいのが訪問現場。詳しくは【訪問リハの実情】をチェックしてみてください。