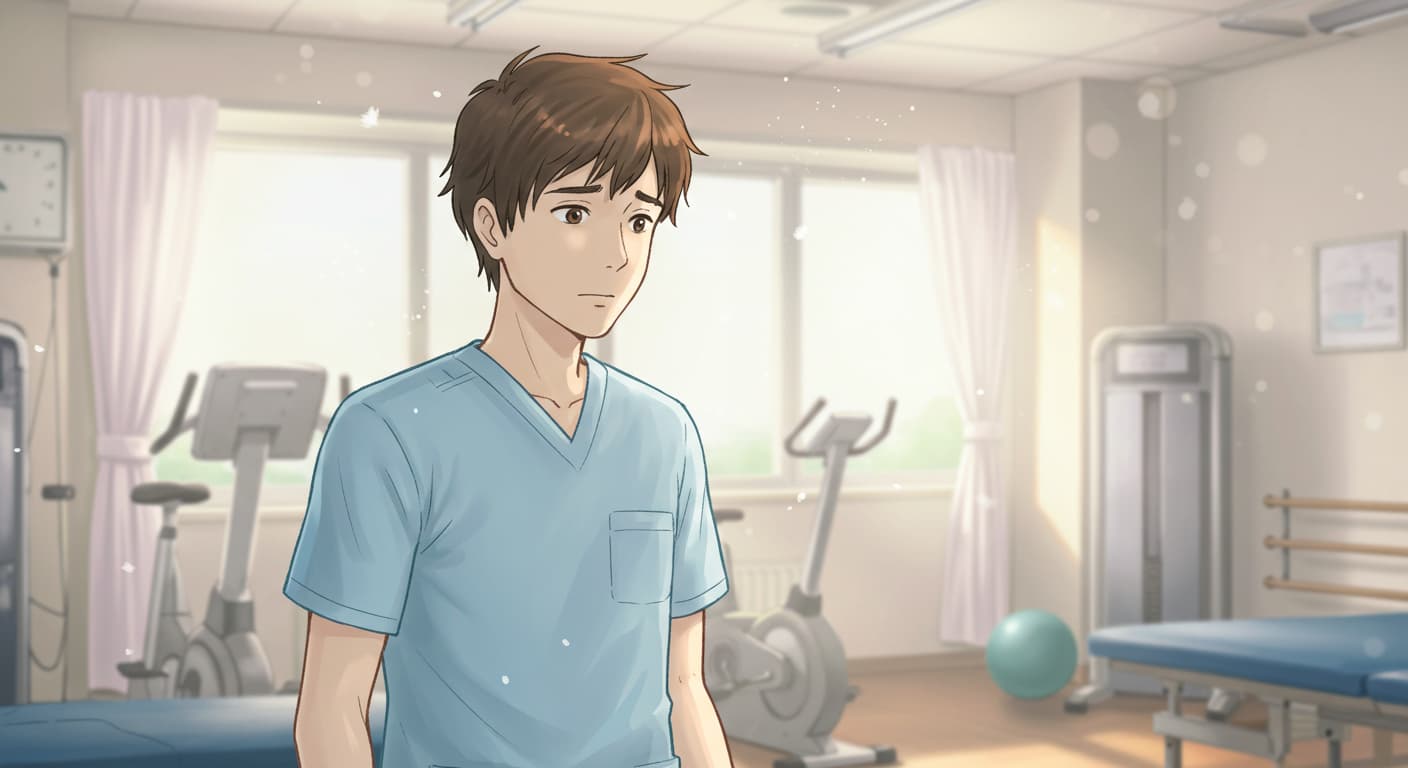「自分は、リハビリの仕事ができないのかもしれない」
そんな言葉が、頭から離れなくなっていませんか。
技術も学んできた。患者さんにも真剣に向き合っている。
それでもうまくいかず、周りと比べて落ち込む日々が続く――。

この違和感は、決してあなただけのものではありません。
実は多くの理学療法士が、「できない」と感じた瞬間をきっかけに、キャリアそのものに疑問を持ち始めています。
ポイント
この記事では、「どうすればできるようになるか」だけでなく、なぜそう感じてしまうのか、そしてその感覚をどう活かすべきかまで、他記事では語られない視点で深掘りします。
読み進めるうちに、
「自分がダメなのではなかった」そう思えるヒントが、きっと見つかるはずです。
Contents
「リハビリの仕事ができない」と感じるのはなぜ?【悩みの背景を理解する】
「自分はリハビリの仕事ができないのではないか」
そんな不安や自己否定の気持ちから、
「リハビリの仕事ができない」と感じて、このページにたどり着いたのではないでしょうか。

この悩みは、決して一部の人だけのものではありません。
特に、理学療法士として数年働いた後や、転職を考え始めたタイミングで強く感じやすい傾向があります。
ここではまず、「なぜリハビリの仕事ができないと感じてしまうのか」を、
心理面・環境面・評価の視点から整理し、その悩みの正体を言語化していきます。
よくある悩みのパターンと心理的要因
「リハビリの仕事ができない」と感じる人の多くは、次のような悩みを抱えています。
- 評価やプログラム立案に自信が持てない
- 患者さんの回復を実感できず、手応えがない
- 先輩や同僚と比べて劣っている気がする
- 説明やコミュニケーションがうまくいかない
これらに共通しているのは、
「結果が見えにくい仕事特性」と「自分への期待の高さ」です。
リハビリは、短期間で明確な成果が出にくく、患者さんの状態・環境・意欲にも大きく左右されます。
それにもかかわらず、
「もっと良くできるはず」
「自分の関わり方が悪いのでは」
と、責任をすべて自分に向けてしまうPTほど、「できない」という感覚を強めてしまいます。

特に真面目で向上心のある人ほど、自己評価が厳しくなりやすいのが、この悩みの特徴です。
「仕事ができないと感じる新人理学療法士は、実はかなり多いです」
周囲の期待と現実のギャップが生まれる理由
「リハビリの仕事ができない」と感じる背景には、周囲の期待と現実のギャップも大きく影響しています。
例えば、
- 新人時代に「即戦力」を求められる
- 忙しい職場で十分な指導を受けられない
- 成果よりも単位数・回転率を重視される
こうした環境では、
「考える余裕がない」
「振り返る時間がない」
まま現場に立ち続けることになります。
その結果、
- 成長している実感が持てない
- 「こなしているだけ」だと感じる
という状態に陥りやすくなります。
本来は環境や教育体制の問題であるにもかかわらず、
それを「自分ができないからだ」と捉えてしまうPTは非常に多いです。
もしあなたが、
「頑張っているのに評価されない」
「自分なりに工夫しているのに報われない」
と感じているなら、

それは能力不足ではなく、環境とのミスマッチの可能性も十分にあります。
「できない」と感じるのは成長のサイン? — 正しい自己評価の視点
ここで、最も大切な視点をお伝えします。
「リハビリの仕事ができない」と感じること自体が、必ずしも悪いことではありません。
むしろ、
・自分の課題に気づけている
・現状に疑問を持てている
という点では、成長の初期段階にいるサインとも言えます。
本当に危険なのは、
「何も考えずにルーティンをこなしている状態」
「できていないことにすら気づかない状態」
です。
一方で、
- 毎日振り返って悩んでいる
- 「もっと良くなりたい」と考えている
人は、自己評価が一時的に下がりやすい傾向があります。
この時期に大切なのは、
- できない点だけを見るのではなく
- 「できるようになったこと」も意識的に拾う
という視点です。
もし今、
「この仕事向いてないのかも」
「転職した方がいいのか迷っている」
と感じているなら、
まずは自分が本当にできていないのか、それとも評価軸がズレているのかを、
一度立ち止まって考えてみてください。
「リハビリの仕事ができない」と感じる悩みは、あなたが真剣にこの仕事と向き合ってきた証拠でもあります。

この感覚をどう扱うかで、これからのキャリアの方向性は大きく変わっていきます。
「リハビリの仕事ができない」と検索する人の具体的な悩みとは
「リハビリの仕事ができない」と感じて悩む人の多くは、
単に「仕事がつらい」というレベルではなく、
このまま続けていいのか、転職すべきかという岐路に立っているケースがほとんどです。
特に理学療法士として数年働いた後や、環境の変化(異動・転職・担当患者の変化)があったタイミングで、
こうした悩みは一気に表面化します。
ここでは、「リハビリの仕事ができない」と感じる人が抱えやすい悩みを、
現場で実際によくある4つのパターンに分けて整理します。

「これは自分のことだ」と感じる項目があれば、
それはあなたが怠けているのではなく、明確な理由がある悩みです。
技術が追いつかない・ミスが多い
最も多い悩みが、「自分は技術的にできていないのではないか」という不安です。
- 評価の組み立てが遅い
- プログラムがワンパターンになる
- 先輩に修正されることが多い
- 小さなミスが続いて自信を失う
こうした状態が続くと、
「自分はセンスがないのでは」
「他の人はもっとできているのに」
と、能力そのものを否定してしまいがちです。
しかし実際には、
忙しすぎて振り返る時間がない体系的に学び直す機会がない
といった環境要因が原因であることも非常に多いです。
「できない」のではなく、
「整理する時間と支援が足りていない」だけ、というケースは珍しくありません。
患者さんとのコミュニケーションが難しい
次に多いのが、患者さんとの関わりに自信が持てないという悩みです。
- 説明しても納得してもらえない
- 反応が薄く、手応えがない
- クレームや不満が怖い
- 距離感が分からない

リハビリは「技術職」であると同時に、対人援助職です。
そのため、
「技術は合っているのに、評価されない」
「一生懸命やっているのに伝わらない」
というズレが生まれやすい仕事でもあります。
特に真面目な人ほど、
「患者さんを満足させられない=仕事ができない」
と結びつけてしまい、自己否定を強めてしまいます。
しかし、コミュニケーション能力は経験・場数・環境による影響が非常に大きいスキルです。
一時的につまずいているだけで、仕事全体を否定する必要はありません。
「技術よりも、コミュニケーション面でつまずいているケースもあります」
職場の人間関係に馴染めない
「リハビリの仕事ができない」と感じる背景には、実は“仕事そのもの”ではなく、人間関係が影響していることも多くあります。
- 質問しづらい雰囲気
- ミスを責められる文化
- 先輩や上司との相性が悪い
- 比較や陰口が多い職場
こうした環境では、
「失敗できない」
「常に評価されている気がする」
という緊張状態が続き、本来の力を発揮しづらくなります。
結果として、
「自分はリハビリの仕事に向いていないのでは」
という結論にすり替わってしまうのです。
ですがこれは、
能力の問題ではなく、職場との相性の問題であるケースも少なくありません。
体力的・メンタル的に限界を感じる
最後に見逃せないのが、心身の限界からくる「できない感覚」です。
- 残業や単位数が多すぎる
- 休みが取れない
- 常に疲れている
- 朝、職場に行くのがつらい
この状態では、
どれだけ能力があっても、「うまくできない」と感じるのは当然です。
特に、
「前はもっとできていた気がする」
と感じている場合、それはスキル低下ではなく、
疲労やストレスによるパフォーマンス低下の可能性が高いです。
この段階まで我慢してしまうと、
- 自己否定が強くなる
- 転職=逃げだと感じてしまう
という思考に陥りがちです。
「リハビリの仕事ができない」と感じる悩みは、

一つひとつ分解して考えることで、初めて対処の方向性が見えてきます。
次のステップでは、「どう向き合えばいいのか」「転職を考えるべきラインはどこか」
といった具体的な判断軸を整理していくことが重要です。
仕事ができないと感じたときに試したい具体的な対策
「自分はリハビリの仕事ができないのかもしれない」
そう感じたとき、多くの人は気合や根性で何とかしようとします。
しかし実際には、やり方を変えるだけで状況が大きく改善するケースがほとんどです。
ここでは、「リハビリの仕事できない」と悩む理学療法士が、
今日から現実的に試せる対策を、
技術・コミュニケーション・振り返り・相談環境の4つの視点から解説します。

すべてを一度にやる必要はありません。
「これならできそう」と感じたものからで十分です。
技術・知識を身につけるための学習法
「技術が追いつかない」「知識不足を感じる」
そう思ったときにやりがちな失敗が、いきなり勉強量を増やすことです。
論文を読もうとしたり、分厚い参考書を開いたりして、
結局続かず自己嫌悪に陥る…という経験はありませんか?
ポイントは、“今の臨床に直結する学び”だけに絞ることです。
- 今日担当している患者さんの疾患だけを調べる
- 評価で迷ったポイントを1つだけ整理する
- プログラムの根拠を1行で説明できるようにする

「広く学ぶ」よりも、「狭く・深く・すぐ使う」ことを意識してください。
この積み重ねが、
「なんとなく不安」だった状態を、「理由が分かる」「説明できる」状態へ変えてくれます。
「勉強しても成長を実感できないと悩む人も少なくありません」
コミュニケーションを改善するコツ
リハビリの仕事ができないと感じる原因は、技術よりもコミュニケーションのつまずきであることも少なくありません。
特に多いのが、
- 説明が専門的すぎる
- 相手の理解度を確認していない
- 「正しいこと」を伝えることに必死
というパターンです。
改善のコツはシンプルで、「説明する」より「確認する」ことです。
例えば、
- 「ここまでで分かりにくいところはありますか?」
- 「今の説明、どう感じましたか?」
- 「ご本人としては、何が一番困っていますか?」
こうした一言を添えるだけで、
一方通行のリハビリから、双方向の関わりに変わります。
「うまく話せない」のではなく、

相手の反応を拾う余裕がなかっただけというケースは非常に多いです。
ミスや失敗を活かす「記録と振り返り」の習慣
「仕事ができない」と感じる人ほど、ミスや失敗を強く引きずる傾向があります。
ですが、ミスそのものより問題なのは、
「失敗が整理されず、次に活かされないこと」
です。

おすすめなのは、感情を書かない振り返りです。
- 何が起きたか(事実)
- なぜそうなったか(要因)
- 次に変える行動(1つだけ)
これを、メモやスマホ、ノートに簡単に残すだけでOKです。
「自分はダメだ」「向いていない」といった評価は一切不要です。
失敗=データ
として扱えるようになると、
「できない」という感覚は、「改善ポイントが見えた」に変わっていきます。
相談できる環境を作る・メンターを見つける
最後に、最も重要な対策です。
「リハビリの仕事ができない」と感じているとき、一人で抱え込むほど状況は悪化します。
大切なのは、
「完璧な指導者」を探すことではなく、
「話せる相手」を持つこと
です。
- 職場の先輩
- 以前の同僚
- 外部の勉強会やコミュニティ
どこでも構いません。
「こんなことで相談していいのかな」と思う内容ほど、話してみると整理されるものです。
もし、
「今の職場では相談できる人がいない」
「聞くと迷惑そうにされる」
と感じているなら、それは能力の問題ではなく、環境の問題かもしれません。
仕事ができないと感じたときは、
自分を変える努力と同時に、環境を見直す視点も忘れないでください。
「リハビリの仕事ができない」と悩む経験は、あなたが真剣にこの仕事に向き合っている証拠です。

正しい対策を取れば、その悩みは必ず次のステップにつながります。
どうしても辛いときは環境を変える選択もあり
「もう色々試したけれど、やっぱりリハビリの仕事ができない気がする」
「努力しても苦しさが減らない」
そんな状態まで追い込まれているなら、“環境を変える”という選択肢を真剣に考えてもいい段階かもしれません。
「環境を変える=逃げ」と感じる理学療法士は非常に多いですが、

実際には能力ではなく、場所との相性が合っていないだけというケースが大半です。
ここでは、「リハビリの仕事できない」と感じて限界に近づいたときに、
自分を守りながらキャリアを前に進めるための現実的な選択肢を整理します。
「実は、職場を変えただけで評価が一変する人も多いです」
異動や部署変更で活躍できる場を探す
まず検討してほしいのが、「職場を辞める」前に「部署を変える」という選択です。
同じ理学療法士でも、
- 急性期・回復期・維持期
- 外来・病棟・訪問
- 運動器・脳血管・内部障害
など、求められるスキルやテンポは大きく異なります。
例えば、
- スピード感が合わず急性期で消耗している人
- 人との距離感が難しく外来で疲弊している人
が、回復期や訪問に異動した途端、
「あれ?意外とできるかも」と感じることは珍しくありません。
もし今の職場に異動制度があるなら、
「今の部署が合っていない可能性」
を前提に、一度相談してみる価値は十分あります。

「リハビリの仕事ができない」のではなく、“今のフィールドが合っていない”だけかもしれません。
他の施設や職種への転職で活躍できる可能性
異動が難しい場合や、組織全体の雰囲気そのものが合わない場合は、転職を視野に入れることも自然な流れです。
理学療法士が働く施設は、
- 病院
- クリニック
- 介護施設
- 訪問リハビリ
など多岐にわたります。
特に、
- 教育体制が整っていない
- 人間関係のストレスが大きい
- 単位数や回転率が異常に高い
といった環境では、

どれだけ優秀な人でも「できない」と感じやすくなります。
実際、転職後に
「同じ仕事なのに、こんなに楽なのか」
「前より自信を持って関われる」
と感じる理学療法士は少なくありません。
ここで重要なのは、
“前の職場でうまくいかなかった=自分の価値が低い”
と結びつけないことです。
環境が変われば、
評価軸・求められる役割・サポート体制も変わります。
「リハビリの仕事できない」と感じた経験は、転職先を見極めるための重要なヒントにもなります。
リハビリの仕事を活かしたキャリアの広げ方
最後に、
「現場の理学療法士として働くこと」だけが、リハビリのキャリアではない、という視点もお伝えします。
リハビリの仕事で培った経験は、
- 身体・運動の知識
- 対人支援スキル
- 説明力・観察力
といった形で、他の分野でも十分に活かせます。
例えば、
- 医療・介護系の一般企業
- フィットネス・予防分野
- 教育・研修・サポート職
- ライター・発信・コンテンツ制作
など、「リハビリの仕事を離れる=ゼロからやり直し」ではありません。
むしろ、
「現場で苦しんだからこそ分かる視点」
が、価値になる場面も多くあります。
もし今あなたが、
「もう限界かもしれない」
「この仕事を続けるのが怖い」
と感じているなら、
それは弱さではなく、自分を守るための正常なサインです。

環境を変えることは、逃げでも失敗でもありません。
「リハビリの仕事ができない」と感じた経験は、あなたに合った場所・働き方を見つけるための通過点です。
自分を責めすぎず、
“どこなら力を発揮できるか”という視点で、次の一歩を考えてみてください。
競合記事にない独自視点:キャリア戦略として「できない」を考える
「リハビリの仕事ができない」と感じたとき、多くの人はできるようになる方法だけを探します。
もちろん努力や改善は大切ですが、それだけではこのキーワードの根本的な不安は解消されません。
なぜなら、「リハビリの仕事できない」と感じる人の多くは、
すでに十分頑張ってきたうえで、
キャリアとしてこの仕事を続けるべきかどうかを悩んでいるからです。

ここでは、「できない」という感覚をキャリア戦略として捉え直す視点を提示します。
なぜ「できる人材」ばかりを目指す必要はないのか
医療・リハビリ業界では、
- 評価が早い人
- 知識量が多い人
- 手技がうまい人
が「できる理学療法士」として語られがちです。
しかし現実には、全員が同じ方向で「できる人」になる必要はありません。
リハビリの仕事は、
- スピードが求められる現場
- じっくり関係構築が必要な現場
- 身体より説明力が重要な場面
など、求められる資質が場面ごとに大きく異なります。
それにもかかわらず、
「周りと同じようにできない=向いていない」
と結論づけてしまう人は非常に多いです。
ですが実際は、
「この環境では評価されにくい強み」を持っているだけ
というケースも少なくありません。
「できない」と感じる瞬間は、

自分と環境のズレを教えてくれる重要なサインでもあります。
自分の強みと適性を見つけるためのワーク
ここで一度、
「できないこと」ではなく、“相対的にマシだったこと”に目を向けてみてください。
簡単な振り返りワーク
- これまでの業務で「比較的苦痛が少なかった場面」は?
- 患者さんや同僚から感謝された経験は?
- 逆に、強いストレスを感じた業務は何か?

ポイントは、「得意」ではなく「消耗しにくい」を基準にすることです。
例えば、
- 手技は苦手だが、説明は苦ではない
- 急性期は無理だが、生活期なら落ち着いて関われる
- 臨床は辛いが、後輩指導は嫌いではない
こうした傾向は、
今後のキャリア設計に直結する重要なヒントになります。
「リハビリの仕事ができない」と感じた経験がある人ほど、実は自己理解の材料を多く持っています。
「できない」経験を武器にする転職面接での伝え方
転職を考えたとき、多くの理学療法士が不安に思うのが、
「できなかった経験をどう説明すればいいのか」
という点です。
結論から言うと、
「できなかった事実」そのものは問題になりません。
評価されるのは、
- なぜそう感じたのかを言語化できているか
- そこから何を学んだのか
- 次はどう活かそうとしているか
です。
例えば、
「前職ではスピードと回転率が重視される環境で、
自分は一人ひとりと向き合う関わりに強みがあると気づきました」
という伝え方は、自己理解が深い人材として評価されます。
「リハビリの仕事できない」と感じた経験を、
・反省で終わらせるか
・戦略に変えるか
で、その後のキャリアは大きく変わります。
この悩みを持ってここまで読み進めたあなたは、
すでに感覚ではなく、思考でキャリアを考え始めている段階です。

「できない」という感覚は、あなたを否定するものではありません。
“どこで・どう働くか”を見直すための、最も正直なサイン
として、一度真正面から向き合ってみてください。
それは必ず、次の一手につながります。
「周囲との関係性のズレが、『できない』と感じる原因になることもあります」
まとめ
「リハビリの仕事ができない」と感じて悩む人の多くは、
単にスキル不足を嘆いているのではなく、
この仕事をこのまま続けていいのか、キャリアとして正解なのかを真剣に悩んでいます。
この記事でお伝えしてきた内容を、
後悔しない判断をするための重要ポイントに絞って整理します。
- 「リハビリの仕事ができない」と感じるのは珍しいことではない
多くの理学療法士が、数年目・環境変化・疲労の蓄積をきっかけに同じ悩みを経験している。 - 原因は能力不足ではなく「環境・評価軸・相性」であることが多い
忙しさ、人間関係、教育体制、求められる役割が合っていないだけの場合も多い。 - 「できない」と感じること自体は成長のサインでもある
課題に気づけている=思考停止していない証拠。最も危険なのは何も考えなくなること。 - 対策は「努力量を増やす」より「やり方を変える」こと
臨床に直結した学習、振り返りの習慣、双方向のコミュニケーションで改善余地は大きい。 - 一人で抱え込まないことが最重要
相談相手やメンターがいない環境では、誰でも「できない」と感じやすくなる。 - 限界を感じたら、環境を変える選択は正しい
異動・転職は逃げではなく、自分の力を発揮できる場所を探す戦略。 - 「できない」経験はキャリアの弱点ではなく材料になる
自己理解が深まり、次の職場選びや面接での説得力につながる。 - 目指すべきは「何でもできるPT」ではない
自分が消耗しにくく、価値を出せるフィールドを選ぶことが長く働く鍵。
「リハビリの仕事ができない」と感じた経験は、あなたがこの仕事と真剣に向き合ってきた証拠です。
自分を責めるためではなく、
これからの働き方・生き方を見直すためのサインとして、この悩みを使ってください。

正しい視点で考えれば、この違和感は必ず次のキャリアにつながります。