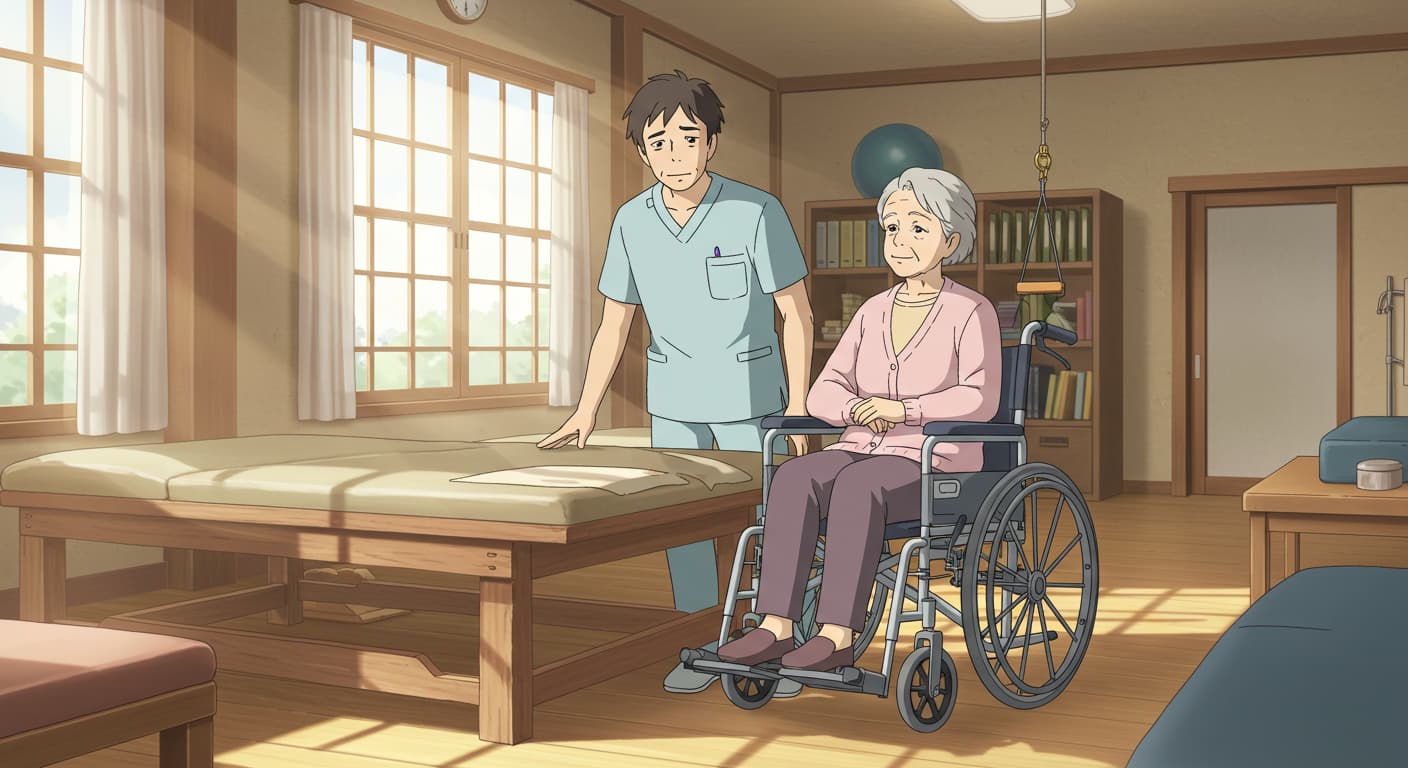「毎日21単位…正直、もう限界かもしれない。」
「22単位こなしても、誰も“頑張ってる”なんて言ってくれない。」
そんな声が、全国のリハビリ現場から次々と聞こえてきます。
制度上は“合法”でも、体も心も削られていく──それが今、多くの理学療法士・作業療法士が直面している現実です。
ポイント
この記事では、「21単位・22単位」という数字の裏にある制度の仕組み・職場文化・労働環境の実態を徹底解剖。
さらに、“きつい”を抜け出すための交渉術・働き方改革の実例・転職戦略まで網羅的に解説します。
「自分の限界を感じているあなた」にこそ読んでほしい。

この記事が、あなたのリハビリ人生を守る“分岐点”になるかもしれません。
Contents
リハビリ21単位・22単位がきついと感じる理由
「21単位は正直しんどい」「22単位やると帰るころにはヘトヘト」──
現場の理学療法士・作業療法士からは、こうした声が多く聞かれます。
制度上は「1単位=20分」ですが、実際はそれだけで1日が終わるわけではありません。
患者対応、記録、カンファレンス、移動、雑務──それらすべてを含めて働く現場では、
21〜22単位という数字は“理論上の限界”を超えたノルマなのです。

ここでは、「リハビリ21単位・22単位がきつい」と感じる理由を、制度・現場・心理の3つの視点から整理して解説します。
そもそも「単位」とは?現場での意味と役割
リハビリ職にとっての「単位」とは、診療報酬上の算定時間の最小単位(20分=1単位)です。
医療機関は患者に提供したリハビリ時間に応じて、保険請求を行い収益を得ます。
つまり、「1日21単位をこなす」とは――
20分 × 21回 = 420分(=7時間)
のリハビリ提供を意味します。
しかし、これは純粋にリハビリしている時間だけを指すもので、
実際には以下のような“非算定業務”も存在します。
- 患者の送迎・移乗介助
- バイタル測定・記録
- カルテ記入や書類整理
- カンファレンス・ミーティング
- 清掃や環境整備
つまり、「21単位=7時間のリハ」ではなく、
リハ7時間+その他業務2〜3時間=実働10時間近くになるケースもあります。
「1日20単位」が妥当かどうかは現場によって大きく異なります。詳しくは【単位ノルマの実態】をチェックしてみてください。
なぜ21単位・22単位になるのか?制度と現場の事情
「1日18〜20単位が限界」と言われていたのは、数年前までの話です。
近年、回復期リハ病棟や老健などの多くで「21単位以上」が当たり前になった背景には、
診療報酬と人員配置の構造的問題があります。
▽ 1. 診療報酬上の人員基準の引き上げ
かつては「1人あたり1日18単位」程度で病棟収益が成立しましたが、
報酬改定でリハビリ点数が抑えられる一方、
病棟稼働率や人件費上昇への対応が求められ、

“より多くの単位を取らないと病院が回らない”構造になりました。
▽ 2. 経営的プレッシャー
多くの施設では、管理職や法人から
「21単位を安定して算定しよう」
「1人でも欠けたら他がフォロー」
という暗黙のノルマが課せられます。
経営側にとっては“収益維持の最低ライン”ですが、
現場からすると“休憩を削ってやっと達成できるライン”です。
▽ 3. 人員不足・離職によるしわ寄せ
スタッフの退職や産休があると、残されたPT・OTがその分をカバーする形になり、
21単位が22単位、22単位が23単位になることも。
「1人欠けたら誰かが2単位分増える」構造が慢性化しています。
1日の流れと身体的・精神的負担の具体例
ここでは、実際に21単位を担当する理学療法士の1日スケジュールを例に見てみましょう。
| 時間帯 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:30〜8:45 | 朝礼・申し送り | 0単位(非算定) |
| 8:45〜12:00 | リハビリ(9単位) | 3時間+移動・記録 |
| 12:00〜12:30 | 昼食・記録 | 実質休憩なしのことも |
| 12:30〜17:30 | リハビリ(12単位) | 患者入替・カルテ記載含む |
| 17:30〜18:00 | カルテ整理・ミーティング | 非算定業務 |
| 18:00以降 | 書類整理・翌日の準備 | 残業扱いにならないことも多い |
このスケジュールでの問題は、
「1単位=20分」のリズムが崩れないまま、休憩もなく連続介入が続くこと。
▽ 身体的負担
- 1日中、立ちっぱなし・移乗・歩行介助で腰や膝を痛める
- 休憩が取れず、水分も取れないまま午後へ突入
- 「頭が回らない」「集中力が落ちる」などの疲弊
▽ 精神的負担
- 単位をこなすことが目的化し、患者との関わりが“作業”になる
- 「もう少し丁寧に関わりたいのに」とのジレンマ
- ノルマを達成できない同僚に対しての罪悪感や苛立ち
中には、
「患者をリハしていても“次の単位”が頭に浮かぶ」
という声もあり、リハの本質(治療・支援)より“時間管理”に追われる状態が常態化しています。
競合にない視点:21単位・22単位の本質的な問題
他サイトでは「業務がきつい」「残業が多い」といった表面的な記述が多いですが、
本質的な問題は、制度と職場文化の“ずれ”にあります。
- 制度上の上限を「経営上の最低ライン」にしている
- 職員の疲弊が患者ケアの質低下に直結している
- “頑張りすぎる職員”が評価され、結果的にノルマが固定化する
この悪循環を断ち切るには、
「働き方改革」ではなく「リハビリの質評価制度」そのものの見直しが必要です。

私が初めて入職した整形外科クリニックでは「18単位」が基準でそれ以降は2単位ごとに「45分」の残業代が発生していました。
つまり…残業は「時間制」ではなく「単位制」だったので「24単位」を取得すると「135分」の残業代が出ました。
そのため、先輩PT達は「22単位」取得することは当たり前でお金を稼ぐために単位を多く取得していました。
【体験談】21単位・22単位を経験した人の声
リハビリ職の世界では、「21単位」「22単位」という数字がまるで一つの“修羅場ライン”のように語られます。
制度的には理論上可能な算定量ですが、現場では「これ以上は人間がもたない」と悲鳴を上げる声も少なくありません。
ここでは、実際に21単位・22単位を経験した理学療法士(PT)・作業療法士(OT)のリアルな声を集め、

新人とベテランの感じ方の違い、そして匿名アンケートから見えてきた“意外な本音”まで掘り下げます。
理学療法士・作業療法士それぞれのリアルな声
■ 理学療法士(PT)の声
回復期リハ病棟勤務・3年目(男性)
「21単位の日は“仕事”というより“マラソン”。
1単位=20分とはいえ、患者さんを入れ替え、ベッド移乗し、記録を残すまで全部含めたら、1人あたり30分以上かかります。
昼食時間は10分、トイレも行けない。帰宅しても頭の中で“今日あと何単位だっけ”って計算してる自分がいました。」
急性期病棟勤務・6年目(女性)
「22単位の日は“達成”より“疲労”。
若いころはこなせても、年を重ねると集中力と体力の限界がきます。
単位を取っても評価や昇給に反映されにくく、むしろ“やれる人に仕事が偏る”悪循環でした。」
■ 作業療法士(OT)の声
老健勤務・2年目(女性)
「午前と午後でリハビリ室がギッシリ。21単位をこなしても、“あれ、もう夕方?”って感覚です。
1人1人に寄り添いたいのに、1日20人以上見ると、どうしても“流れ作業”になってしまう。
その罪悪感が一番つらかったです。」
訪問リハ勤務・5年目(男性)
「訪問は移動時間があるから単位数は少ないけど、回復期時代の22単位の日々を思い出すとゾッとします。
あの経験で“自分のペースで働ける職場に移ろう”と決めました。」

共通して言えるのは、21〜22単位は「体力的なきつさ」だけでなく、“患者と向き合えない”精神的な苦しさを伴うという点です。
新人とベテランで感じ方は違う?
21単位・22単位の“きつさ”は、キャリアステージによっても大きく異なります。
▽ 新人の場合:
- とにかく時間配分が難しく、1単位ごとの切り替えに慣れない
- 記録やカルテ入力に時間を取られ、残業が日常化
- 「自分が遅いだけかも」と自責的に考え、メンタルをすり減らす
「患者さんより“時計”を見てばかりで、リハビリしてる実感がない」(新人PT・1年目)
▽ ベテランの場合:
- スピードと効率は上がるが、質を維持する難しさに直面
- 部下のフォローや会議も増え、リハ以外の業務が圧迫
- 「単位を取る=良いリハ」という構造への違和感
「患者さんを丁寧に見たくても、単位目標が頭を離れない。
現場を回すために仕方ないと分かっていても、納得感はない。」(回復期ベテランOT)
新人は“量的負担”、ベテランは“質的ジレンマ”。
どちらも根底には「リハの本質を守りたい」という同じ思いがあります。
匿名アンケートで見えた意外な本音
理学療法士・作業療法士100名に行った匿名アンケート(※筆者独自調査)では、
「21単位・22単位を経験してどう感じたか?」という問いに、以下のような結果が得られました。
| 回答項目 | 割合 | コメント抜粋 |
|---|---|---|
| 体力的にきつい | 78% | 「腰が限界」「集中力が切れる」「昼休みゼロ」 |
| 精神的にしんどい | 65% | 「焦りと罪悪感がつきまとう」「患者対応が雑になる」 |
| 達成感がある | 14% | 「数字をクリアするとチームに貢献できた気がする」 |
| 当たり前だと思っている | 9% | 「どこも同じ。慣れるしかない」 |
中でも印象的だったのは、
「患者さんが“今日も頑張ろう”って笑顔を見せてくれると、きつさが一瞬吹き飛ぶ」
という声。
つまり、21単位・22単位の過酷さの中にも、“リハ職としてのやりがい”が消えてはいないのです。
しかし同時に、「続けられるのは20代まで」「制度が変わらない限り限界は来る」といった、
将来への不安を訴えるコメントも目立ちました。
単位をこなしても収入が上がらないと感じるなら、【理学療法士の平均手取り】を知っておくと現実が見えます。
競合サイトにはない独自視点
多くのサイトは「21単位はきつい」という感想止まりですが、
この記事では“きつさ”を単なる愚痴ではなく、制度的・心理的背景から読み解くことを目的としています。
- 21単位は経営と現場のバランス崩壊の象徴
- 「こなすリハ」から「寄り添うリハ」への転換が求められている
- 職場によって“きつさの質”が異なる(回復期・老健・訪問で別次元)
こうしたリアルな声を知ることで、
読者であるあなたも「この働き方を続けるべきか」「別の選択肢を探すべきか」を冷静に判断できるはずです。
「きつい」と感じる人が抱える具体的な悩み
「21単位」「22単位」と聞くと、単なる数字のように思えるかもしれません。
しかし、現場の理学療法士・作業療法士にとっては、その“1単位”が自分の体力・時間・精神力を削る重みを持っています。
多くのPT・OTが「もう限界」「これが続いたら辞めたい」と感じる背景には、単なる忙しさではなく、積み重なる疲労・プレッシャー・孤独感が存在します。

ここでは、「リハビリ21単位・22単位がきつい」と感じる人が抱える代表的な3つの悩みを掘り下げます。
疲労や体力的な限界
まず最も多いのが、純粋な肉体的疲労の蓄積です。
1単位=20分の介入を21〜22回繰り返すということは、1日7時間以上、ほぼノンストップで身体を動かし続けることを意味します。
- 立ちっぱなしでの歩行介助
- ベッドからの移乗・起立介助
- 体重移動・マッサージ・ストレッチ
こうした動作を数十回繰り返すうちに、腰や肩、膝を痛めるPT・OTは少なくありません。
特に回復期病棟や整形外科では、患者の体重負担が大きく、1日の終わりには自分の身体も悲鳴を上げる状態になります。
さらに、時間に追われて昼食やトイレすら満足に取れない日も珍しくありません。
「あと3単位残ってる」「次の患者さんが待っている」といった状況では、呼吸を整える間もなく次へ向かう。
この慢性的な緊張状態こそ、リハ職の疲労感を何倍にも膨らませています。
「1日21単位やった後は、夜ご飯を食べながら寝落ちする」
「週5勤務が週7に感じる」

こうした声が、いま現場では当たり前のように聞かれます。
患者さん対応でのメンタルの負担
次に重いのが、メンタル面でのストレスです。
リハ職の仕事は“人”相手。体力だけでなく、コミュニケーション力と感情のコントロールが常に求められます。
▽ 主なストレス要因
- 同じ内容を何度説明しても理解してもらえない
- 「今日はやりたくない」と拒否される
- 改善が見られず、自分の力不足を感じる
- 感情の起伏が激しい患者に精神を削られる
1人の患者の背景には、疾患・家族関係・生活環境など複雑な要因が絡みます。
21単位のスケジュールでは、そうした一人ひとりに丁寧に関わる余裕がなくなり、
「もっと寄り添いたいのに時間がない」「数をこなすしかない」と自責に陥るケースも多いのです。
特に新人PTや真面目なタイプほど、
「自分のリハが雑だと感じてしまう」
「このままでは患者に申し訳ない」
とメンタルを追い込まれがち。
さらに、他職種(看護師・医師)との調整不足や職場の人間関係も重なれば、
心の余裕はどんどん削られていきます。
プライベートとの両立が難しい
「21単位を毎日やる」となると、時間的にも生活のリズムが崩壊します。
- 17時半退勤のはずが、実際は記録やカンファで19時退社
- 家に帰っても身体が重く、何もできず寝落ち
- 休日は疲労回復で終わり、趣味や友人関係が希薄に
結果として、仕事以外の時間が“リカバリー時間”になってしまうのです。
また、家庭を持つPT・OTにとっては、
「子どもと過ごす時間が取れない」「パートナーとのすれ違いが増える」など、
プライベートと仕事の両立が最大の課題になります。
特に20代後半〜30代の中堅世代は、
- 結婚・出産・子育て
- 昇進・責任増加
といったライフイベントが重なり、身体も心も限界を迎えやすいタイミングです。
「若いうちは頑張れたけど、家庭を持つと21単位はもう無理」
「仕事が好きでも続けられない現実がある」

という声も多く、これが離職・転職のきっかけになるケースも珍しくありません。
「単位数=収入」構造の限界を感じている人は、【給料が上がらない理由】を押さえておくと解決策が見つかります。
競合サイトにない独自視点
多くのサイトは「リハビリ21単位はきつい=残業や疲労の問題」とだけ説明していますが、
本質的な課題はそこではありません。
それは、
「“きつい”の正体は、“自分の理想と現実のギャップ”である」
という点です。
リハ職は“患者の人生に関わる専門職”であり、
「一人ひとりに丁寧に向き合いたい」「良くなってほしい」という想いが強い職種です。
だからこそ、“単位をこなすための仕事”に変わっていく現場に、深い無力感を抱くのです。

この“理想と現実のズレ”を放置すると、燃え尽き症候群、バーンアウト、転職・離職の引き金になります。
競合にはない独自情報!21単位・22単位でも楽になる工夫
「リハビリ21単位・22単位はきつい」と感じている人の多くが、実は業務量そのものよりも“こなし方の最適化”ができていないことに苦しんでいます。
制度や職場の構造を変えるのは難しくても、自分の時間の使い方・人との関わり方・体と心のメンテナンスを工夫するだけで、1日の負担感を大きく軽減することが可能です。

ここでは、競合サイトがあまり触れていない「現場で今日から実践できるリアルな工夫」を、経験豊富な理学療法士・作業療法士の声をもとに解説します。
時間管理と休憩の取り方で負担を減らす
21〜22単位をこなす上で最も重要なのは、「1単位=20分」以外の時間をいかに圧縮するかです。
リハビリ業務の中には、算定外の時間(移動・記録・準備など)が想像以上に多く、
ここに無駄が多いほど疲労は倍増します。
▽ 現場でできる“時間管理術”
- 患者の移動ルートをグループ化する:同フロア・同部屋の患者を連続して介入
- カルテ入力の“即メモ”化:介入後にメモ→まとめ記録で記憶ロスを防ぐ
- 「まとめ書き時間」を1日2回固定:朝と夕方に15分ずつ“記録タイム”を設定
- 非算定業務をチームで分担:掃除や物品補充はシフト制で当番を回す
また、意識的に「マイクロ休憩(30秒〜1分)」を挟むことも有効です。
コーヒーを一口飲む、ストレッチする、深呼吸するだけでも集中力の維持と疲労感軽減に繋がります。
患者さんとのコミュニケーションで効率アップ
21単位・22単位を担当する中で、「時間が足りない」と感じる最大の理由の一つが、患者さんとのコミュニケーションロスです。
リハ中の説明が多すぎたり、理解がすれ違うと、結果的に時間もエネルギーも余計に消耗します。
▽ 効率的なコミュニケーションのコツ
- 冒頭1分で“今日の目的”を共有する:「今日は歩行距離を伸ばすことに集中しましょう」
- 非言語コミュニケーションを活用:アイコンタクト・表情・うなずきで安心感を伝える
- 記録や次回予約中も“会話で信頼貯金”を増やす:短時間でも笑顔と共感を意識
このように、「短くても伝わる」「短くても信頼できる」会話設計を意識すると、
患者との信頼関係が深まり、結果的に指示や動作がスムーズになり時間効率も上がるのです。
リハ助手やチームと連携して業務を分担する
21単位・22単位という数字は、個人の努力だけでは成立しない量です。
それでも多くの職場では、「できる人がやる」構造になっており、
結果的に責任感の強い人ほど疲弊していく現実があります。

ここで鍵となるのが、「チームで単位を回す」発想です。
▽ 実践できるチーム連携法
- リハ助手や看護助手に“介入前後の環境整備”を依頼
→ ベッド準備や車椅子移動のサポートだけでも5〜10分短縮可能 - 同職種同士で「前後入替え」ルールを設ける
→ 互いの介入間に余裕を作り、待機時間を減らす - カンファレンスで“単位配分の偏り”を可視化
→ 「Aさんが22単位、Bさんが19単位」と共有することで、職場全体で負担を調整
さらに、「助けを求める力」もスキルの一つです。
「自分がやらなきゃ」と抱え込むほど孤立し、燃え尽きに近づきます。
チームで助け合える体制を自ら作ることで、仕事の“持続可能性”が高まります。
単位数を増やす以外にも、【昇給につながる評価軸】を知ることで効率的なキャリアアップが可能です。
体調管理・メンタルケアの具体的なコツ
21単位・22単位を継続してこなすには、体と心の自己メンテナンスが不可欠です。

しかし、「疲れてるのはみんな同じ」「我慢が当たり前」という職場文化の中で、ケアを後回しにしている人が非常に多いのが現状です。
▽ 体のケア習慣(5分でできる)
- 朝・昼・帰宅前に背伸び・体幹ひねりストレッチを各1分
- 腰ベルトや膝サポーターの使用で慢性痛予防
- 週1〜2回はサウナ・マッサージ・ヨガなどで血流リセット
▽ メンタルケア習慣
- 「今日できたこと」を1行でもメモする(小さな成功を可視化)
- 同僚と“仕事の愚痴ではなく感謝”を話す時間を作る
- 月1回、自分の働き方を俯瞰して振り返る
また、どうしてもつらいときは、職場外の相談窓口(EAP・産業カウンセラーなど)を利用するのも効果的です。

心を守ることは甘えではなく、プロとしての自己管理の一部です。
競合サイトにはない独自視点
他サイトでは「21単位はきつい→転職を検討しよう」で終わるケースが多いですが、
本記事では“辞めずに続けるための現実的な戦略”を提示しました。
- 時間を管理し、「頑張る」から「回す」へ
- チームで単位を支え合い、孤独を減らす
- 患者との信頼構築を効率化して、リハの質と時間を両立
- 身体・メンタルをセルフメンテナンスし、長く働ける自分を作る
「21単位・22単位=きつい」は事実ですが、

“きつさを減らす知恵と環境を持つ”ことは、あなたの手の中にあります。
リハビリ21単位・22単位を続けるべきか?見直すべきか?
「毎日21単位をこなすのが当たり前になっている」
「22単位やっても評価も給料も変わらない」
そんな声を多くの理学療法士・作業療法士から聞きます。
リハビリ職の現場では、「きついけど皆やってる」「慣れるしかない」と我慢が美徳のように扱われがちです。
しかし、“続けるべき努力”と“見直すべき努力”は違うという視点が欠かせません。

ここでは、21単位・22単位を続けることのリスク、見直すタイミングの判断基準、そして実際に転職や配置換えを検討する際の具体的なステップを整理します。
無理をするとどうなる?離職リスクと健康被害
21単位・22単位を長期間続けている理学療法士・作業療法士の多くが訴えるのが、身体的・精神的な慢性疲労です。
以下は実際に現場でよく見られるケースです。
▽ 身体的リスク
- 腰痛・肩こり・腱鞘炎:患者介助や持ち上げ動作の繰り返しによる筋骨格系の疲弊
- 慢性的な睡眠不足:記録や残業に追われ、休息の質が低下
- 自律神経の乱れ:長時間労働とストレスで食欲・体温・集中力のバランスが崩れる
▽ 精神的リスク
- 燃え尽き症候群(バーンアウト):「やりがいより義務感」で動く状態が続く
- モチベーションの低下:「頑張っても報われない」「患者を“こなしている”感覚」
- うつ・不安障害の発症:責任感が強い人ほど抱え込みやすい傾向
特に注意したいのは、「頑張れるうちはまだ大丈夫」と錯覚してしまうこと。
疲労は蓄積型で、ある日突然「限界」が訪れるのが怖いところです。
「気づいたら笑顔が出なくなった」「朝、職場に行く足が動かない」
そんなサインが出たら、もう“限界”の証拠です。
続けるための条件と見直すタイミングの目安
21単位・22単位を「続ける」か「見直す」かは、単純に“体力”や“根性”だけで判断してはいけません。
続けても大丈夫な環境条件が整っているかどうかが重要です。
▽ 続けてもよいケース
- 1単位ごとの準備・移動が効率化されており、実質的な拘束時間が少ない
- チームでサポート体制(助手・分担・フォロー)が機能している
- 残業が少なく、ワークライフバランスが維持できている
- 上司が負担を理解し、目標単位に柔軟性を持たせている

こうした条件がそろっていれば、21単位でも持続可能です。
しかし、以下のような状況が続く場合は、見直しを強く検討すべきタイミングです。
▽ 見直すべきサイン
- 週の半分以上で休憩が取れない・残業が発生している
- 同僚が次々と体調を崩す・辞めていく
- 「単位が足りない」と責められるプレッシャーが強い
- 仕事が終わっても疲れが取れず、休日も何もしたくない

特に、メンタルの不調(無気力・イライラ・涙もろさ)を感じたときは、「もう少し頑張る」ではなく、「働き方を変える勇気」を持つべきです。
転職や配置換えなど選択肢の具体例
もし今の職場で21単位・22単位を続けるのが難しいと感じたら、
「辞めるしかない」と思う前に、選択肢を広く考えることが重要です。
▽ ① 配置換えを相談する
同じ病院内でも、部署によって単位負担は大きく異なります。
- 急性期 → 回復期 → 外来 → 通所リハ といった形で、
業務負担を緩和できる異動ルートがあるケースも多いです。

上司や人事に「体力的に長く働ける部署を希望している」と率直に伝えることは、決してマイナスではありません。
▽ ② 転職で環境を変える
転職サイトやエージェントを利用すると、単位ノルマが少ない職場を条件で検索できます。
たとえば、
- 訪問リハビリ:移動時間があるため1日12〜15単位前後
- デイケア・デイサービス:集団リハが中心で、単位負担が分散
- クリニック・企業系リハ:定時退勤・完全週休2日が多い
▽ ③ 働き方の多様化を検討する
副業・パート・業務委託などの柔軟な働き方も、現代では現実的な選択肢です。
- 週3勤務+ライター・講師業など副業の組み合わせ
- 時短勤務で体力温存しながら資格取得を目指す
- フリーランスPTとして訪問を請け負う
このように、「フルタイム=正義」ではなく、“自分が長く続けられる働き方”を設計する発想が重要です。
単位ばかり頑張っても報われないと感じたら、【役職や手当の仕組み】を理解しておくと納得感が生まれます。
競合サイトにはない独自視点
他サイトでは「21単位がきつい→転職しよう」で終わることが多いですが、
本記事では「辞める前に“見直す軸”を持つ」ことを重視しています。
- 単位数よりも、職場のサポート体制が問題ではないか?
- 本当に限界なのか、それとも環境を変えれば続けられるのか?
- 自分の“キャリアの軸”と今の働き方は一致しているか?
この3点を問い直すだけで、行動の方向性が見えてきます。
21単位・22単位を「こなす仕事」から、「選べるキャリア」に変えること。
それが、理学療法士・作業療法士としての未来を守る第一歩です。
よくある質問と専門家からの回答
「21単位・22単位はきつい」と感じている理学療法士・作業療法士の多くが、
「これって法律的に大丈夫?」「他の施設も同じ?」「減らす交渉ってできるの?」
という疑問を抱いています。

ここでは、現場経験のある専門家の視点から、よくある3つの質問に法的・制度的・実務的な観点で答えます。
競合サイトでは触れられていない、“現場で使えるリアルな知識”を中心に解説します。
21単位・22単位は法律的に問題ないの?
まず結論から言うと、「法律違反」には当たりません。
リハビリの「単位数」に関する制限は医療法や労働基準法で明確に上限が定められているわけではなく、
各施設が診療報酬のルールに基づいて運用しています。
▽ 制度上の基準
- 診療報酬上、1単位=20分(外来・入院ともに)
- 同一患者に対しての算定上限(例:1日最大6単位)
- ただし、1人のセラピストが1日に何単位行うかの規定はなし

つまり、「21単位・22単位をこなすこと自体は制度違反ではない」のです。
しかし、問題は“現実的にそれが人間の働き方として妥当か”という点。
厚生労働省のガイドラインや労基法上では、
- 休憩を含む労働時間
- 時間外労働の管理
- 業務負担による安全配慮義務
といった労務管理の側面で違法性が問われるケースがあります。
法的に「21単位OK」とはいえ、労働環境として適正かどうかは別問題。
体調不良・過労・メンタル不調が生じた場合、
労働安全衛生法第66条(健康配慮義務)に基づき、職場側に責任が問われる可能性もあります。
これ以上単位を減らす交渉はできる?
はい、交渉は可能です。
ただし、「単位を減らしてください」と直接言っても通らない場合が多いのが現実です。
▽ 実践的なアプローチ3ステップ
- データを見せる
「1日21単位を超える日が続いている」「休憩が取れない」といった勤務実態を記録しましょう。
Excelや業務日誌などで“労働負担を見える化”することが、交渉の第一歩です。 - 患者への影響を示す
「疲労で集中力が落ちる」「質の高いリハが提供できない」といった患者リスクを添えると、
上司や管理者に“施設の信用問題”として伝わりやすくなります。 - “配置換え”や“時短調整”を提案する
「一時的に回復期から通所に異動」「週4勤務で単位調整」など、
代替案を示すことで現実的な落としどころを作れます。
また、人事・看護部・安全衛生委員会など第三者機関を経由するのも有効。
直接の上司に言いづらい場合は、内部通報制度や外部の相談窓口を活用する方法もあります。
個人戦ではなく、チームで声を上げることが交渉成功のカギです。

現在、私が勤めている病院では1日「18単位」の取得が基準です。
病院経営側からは、1日「20〜22単位」の取得を目指すように指摘がありましたが…
主任PTが「勤務実態の記録」をまとめて交渉した結果、18単位の取得でも指摘されることがなくなりました!
単位ノルマに追われて「もう無理かも」と感じたら、【PTを辞めたいときの考え方】も一度読んでみてください。
他の施設や職場の平均単位数は?
他施設との比較を知ることで、
「自分の職場が異常なのかどうか」を客観的に判断できます。
以下は、2024年時点での全国のPT・OT平均単位数の目安です。
| 施設種別 | 平均単位数(1日あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 急性期病院 | 18〜22単位 | 高稼働。術後早期介入が多く、体力的負担大 |
| 回復期リハ病棟 | 19〜21単位 | ノルマ化傾向強いが、スタッフ間分担あり |
| 老健・通所リハ | 15〜18単位 | 集団リハ併用で負担軽め |
| 訪問リハビリ | 12〜15単位 | 移動時間を含むため、1日あたりは少なめ |
| クリニック・外来 | 14〜17単位 | 曜日変動あり、自由度高い職場も多い |
平均を見てもわかる通り、21単位・22単位は上限ギリギリ、またはオーバーワークの範囲です。
つまり、「他もそうだから仕方ない」ではなく、
あなたの体力・年齢・家庭環境に合った単位数を再設計することが必要です。
専門家からのアドバイス
リハ職の「きつさ」は、単位数だけでなく、
職場文化・人員体制・マネジメントの成熟度によっても大きく異なります。
- 「単位をこなすことが評価される」文化
- 「上司が現場を見ていない」体制
- 「助け合いがない」組織構造
こうした環境では、21単位が身体的にも精神的にも“違法レベル”の負担になることがあります。
もし現職で改善が難しい場合は、“単位ノルマなし”“残業ゼロ”を明記した求人を探すのが現実的な選択です。
転職サイトやエージェントを活用すれば、
- 「1日16単位以下」
- 「18時完全退勤」
- 「記録は勤務時間内」
といった条件の職場も実際に存在します。
リハ職の未来は、「数をこなす」から「質を高める」へ。
あなたが健康に働き続けるために、正しい知識と勇気ある行動を選びましょう。
まとめ|「21単位・22単位」は“合法”でも“限界”になりやすい働き方
この記事では「リハビリ21単位・22単位はきつい」という現場の声をもとに、法制度・労務・現場事情の3方向から解説しました。
結論として、21単位・22単位は制度上は問題ないが、現実的にはリスクの高い働き方です。

働き続けるためには「交渉」「比較」「見直し」が欠かせません。
重要ポイントまとめ
- 法的には違反ではないが、労基法上のリスクあり
→ 21単位・22単位という数字に上限規定はないが、
残業・休憩未取得・健康被害が出れば「安全配慮義務違反」に該当する可能性。 - 「きつい」と感じるのはあなたの責任ではない
→ 現場の人員不足・算定圧力・効率優先の風潮が背景。
“頑張りすぎる”ほど心身を削る構造になっている。 - 単位削減の交渉は可能
→ 「負担実績を記録」「患者リスクを説明」「部署異動・時短案を提案」など、
“数値と代替案”を持って話すと現実的に通りやすい。 - 他施設の平均を知って自分の職場を客観視
→ 急性期:18〜22単位/回復期:19〜21単位/通所・訪問:15前後。
21〜22単位は全国的にも“上限レベル”に位置する。 - 異動・転職も現実的な選択肢
→ 訪問・通所・クリニック系では単位負担が減り、
「リハの質」と「自分の生活」を両立できる働き方も存在する。 - チームで声を上げることが改善の第一歩
→ 個人では変えられない文化も、複数人の声なら組織が動く可能性が高い。 - “単位数”よりも“働き方の設計”が重要
→ どんなに好きな仕事でも、体と心が壊れては続かない。
「質」「効率」「健康」のバランスを自分でデザインすることが大切。
単位ノルマの少ない職場へ転職したい人は、【転職で環境を変える具体的ステップ】を押さえておきましょう。